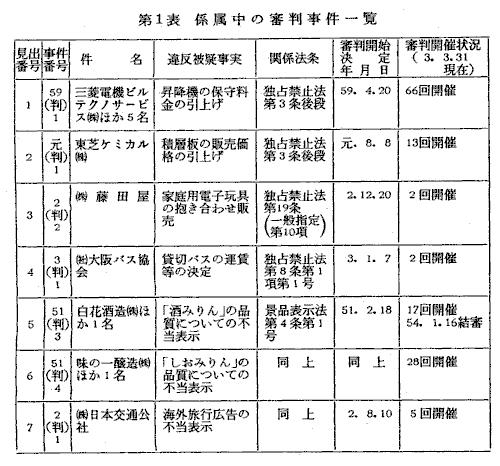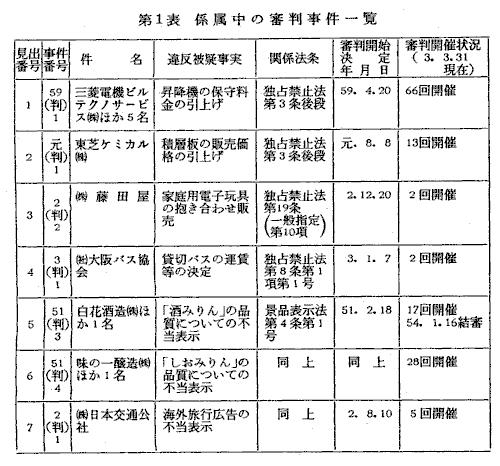| ア |
損害の概念,賠償すべき損害の範囲,違反行為と損害との因果関係に
関する立証の程度等について,不法行為の一般的考え方を踏まえて,独
占禁止法違反行為の場合における考え方を明らかにした。 |
(因果関係に関する立証の程度)
因果関係に関する立証の程度については,一般の不法行為の場合と同
様,独占禁止法違反行為による損害賠償請求訴訟においても,通常人が疑
いを挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし,
かつ,それで足りるものである。また,通常人の確信という概念な,一義
的なものでなく,幅のあるものであり,どのような事項について,どのよ
うな方法によって立証するかにより決定されるものである。
(直接の取引先と間接の取引先)
我が国においては,違反行為と損害との間に相当因果関係が認められる
限り,違反行為者の直接の取引先であると間接の取引先であるとを問わ
ず,損害賠償を請求することを認めているが,直接の被害者の場合には,
違反行為と損害との発生が立証されれば,相当因果関係を立証することは
比較的容易であるが,間接の取引先の場合には,違反行為者と原告(被害
者)との間に,第三者が介在することになり,相当因果関係の立証におい
て,直接の取引先の場合に比べ,立証事項が増えることとなる。 |
| イ |
米国における損害額算定方法の理論である,前後理論,物差理論,市
場占拠率理論について,具体的にどのようなものであるかを紹介すると
ともに,具体的に用いられている事例を紹介している。 |
| ウ |
公正取引委員会の意見の内容は,一般的には,当該違反行為により生
じた財産的損害のうち,通常生ずべき損害についてのものとなる。 |
(因果関係に関する内容)
公正取引委員会の意見の内容のうち,因果関係については,違反行為に
即して,違反行為と原告(被害者)の損害一般との間に相当因果関係があ
るか否かについて,違反行為の特性,市場の状況,商慣行等を踏まえて,
更に経験則等も活用して,意見を述べるとともに,意見の根拠となる資料
を可能な限り添付する。
また,その際,審査の過程等で得た資料等で,裁判所の判断に資すると
考えられる個々の原告(被害者)の個別具体的な取引関係等に関する事情
を知得できた場合には,その事情を意見に含めることも考える。
(損害額に関する内容)
損害額の算定方法については,違反行為に即して,違反行為の特性,市
場の状況,流通の状況等を踏まえた適切な一般的な算定方法をその根拠と
なる資料とともに示すことが期待されており,審査の過程で得た資料等で
具体的な損害の算定が可能であれば,損害額を示すことも考える。 |
| エ |
相当因果関係が認められる範囲については,原告(被害者)が違反行
為者の直接の取引先である場合と間接の取引先である場合とに分けて,
価格引上げ協定,入札談合,取引拒絶及び再販行為の四つの行為類型ご
とに,どの範囲で認められると考えられるかを具体的に示した。 |
(一般的な因果関係が認められる範囲)
原告(被害者)が事業者の場合には,一般的には,違反行為がなければ
存在したであろう利益から現に存在する利益を差し引いたもの(逸失利益)
であり,原告(被害者)が消費者の場合には,価格引上げ協定であれぼ,
一般的には,違反行為期間中の購入価格から想定購入価格を差し引いた金
額に違反行為期間中の購入数量を乗じて得た金額(超過支払額)と考えら
れる。いずれについても,通常,違反行為との間に相当因果関係が認めら
れる。
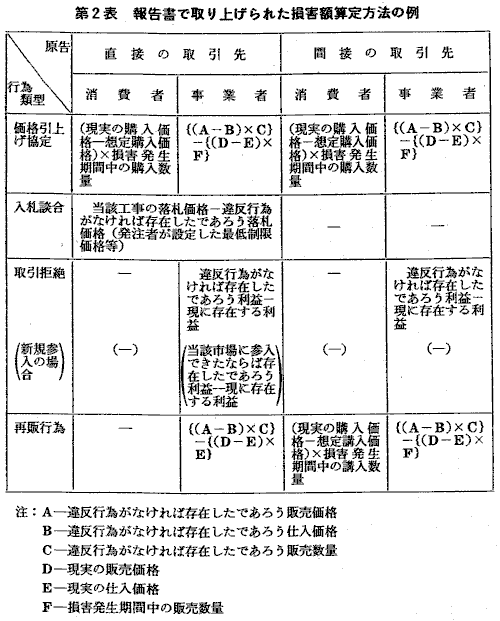
(消費者が価格引上げ協定によって被る損害)
原告(被害者)が違反行為者の間接の取引先である消費者の場合におけ
る価格引上げ協定によって生じた損害については,流通の過程において販
売業者が自己の仕入価格の上昇分を販売価格に上乗せして転売しているこ
とが明らかであるときには,少なくとも協定行為による製造業者の販売価
格の引き上げ分に係る消費者の損害については,一般的に,違反行為との
間に相当因果関係が認められる。また,販売業者が仕入価格の上昇分以上
に自己の販売価格を引き上げた場合のその加算部分については,以下のよ
うなときには,違反行為との間に相当因果関係が認められる。
| ① |
製造業者が,販売業者とともに,原告(消費者)の購入価格の決定
に関与しているとき |
| ② |
製造業者が,希望小売価格を設定し,これを遵守するよう販売業者
を拘束している場合で,違反行為の内容又は実施として希望小売価格
を引き上げたとき |
| ③ |
製造業者が,希望小売価格を設定し,小売業者がおおむねこれで販
売すこるとが商慣行となっている場合で,違反行為の内容又は実施と
して希望小売価格を引き上げたとき |
|
| オ |
損害額を算定する手法として,「現実価格との比較による手法」(例え
ば,価格引上協定において,前後理論により違反行為前の現実の価格を
もって想定価格と推定したり,あるいは,物差理論により違反行為が行
われなかった類似の地域の現実の価格をもって想定価格と推定し,これ
らと違反行為により存在した価格との差を求めて,損害額を算定する手
法)と回帰分析による手法を挙げている。いわゆる石油カルテル鶴岡灯
油訴訟の最高裁判決を踏まえて,原則としては,「現実価格との比較に
よる手法によることが適当であり,「価格の形成に影響を及ぼす顕著な
経済的要因等の変動がある」場合には,回帰分析による手法を利用する
ことも考えられる。 |
| 力 |
損害額の算定方式については,価格引上げ協定,入札談合,取引拒絶
及び再販行為の四つの行為類型ごとに,原告(被害者)が,直後の取引
先か間接の取引先か,消費者か事業者かに分けて,どのような算定方式
が妥当かを,具体的に示した。 |