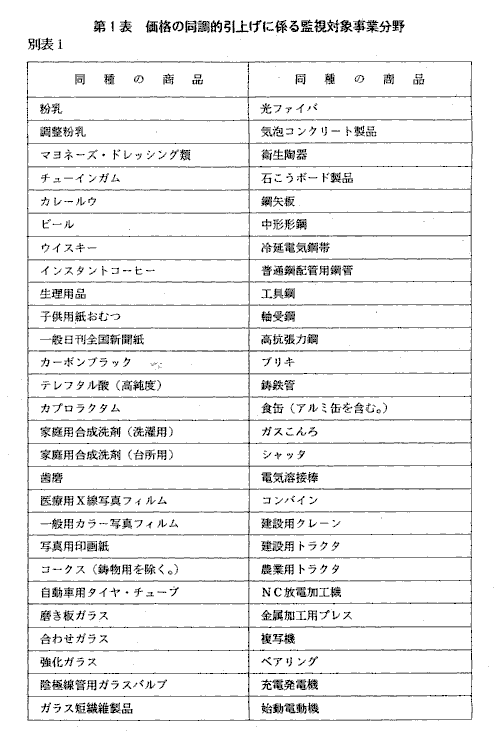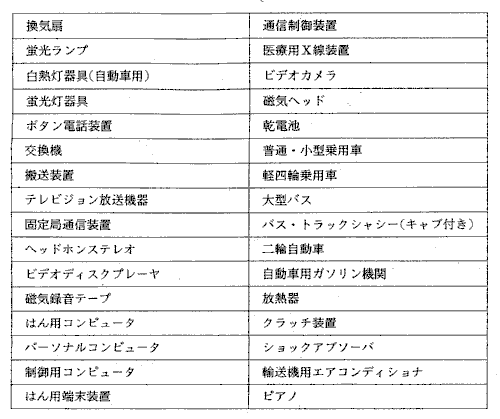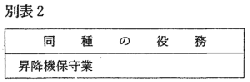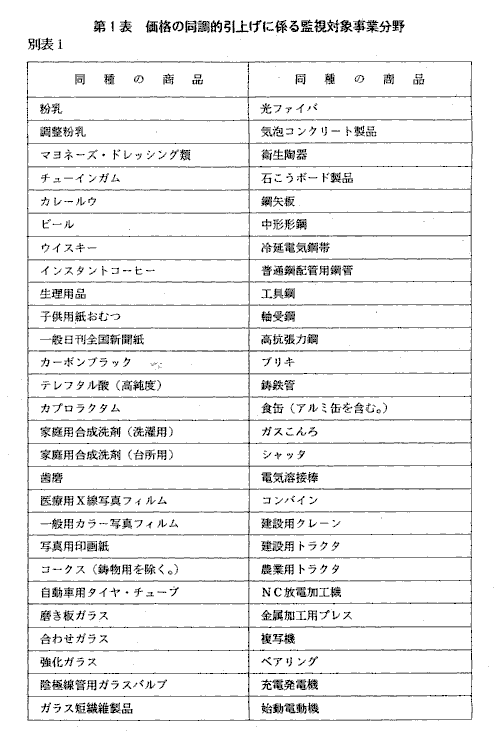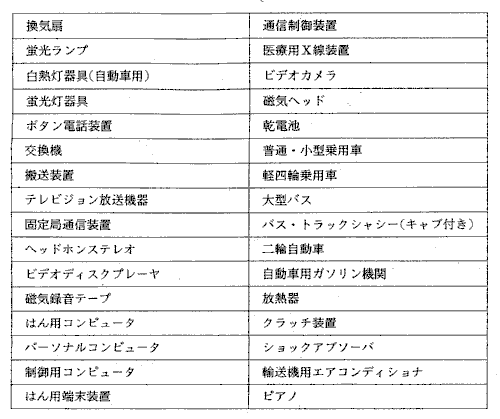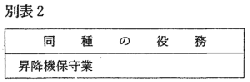第6章 価格の同調的引上げに関する報告の徴収
第1 概 説
独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が600億円超
(平成5年7月23日前は300億円超)で,かつ,上位3社の市場占拠率の合
計が70%超という市場構造要件を満たす同種の商品又は役務につき,首位事
業者を含む2以上の主要事業者(市場占拠率が5%以上であって,上位5位
以内である者をいう。以下この章において同じ。)が,取引の基準として用
いる価格について,3か月以内に,同一又は近似の額又は率の引上げをした
ときは,当委員会は,該当主要事業者に対し,当該価格の引上げ理由につい
て報告を求めることができる。
この規定の運用については,当委員会は,その運用基準を明らかにすると
ともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これを運用基準
別表に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,同別表に掲載された品目につ
いて価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。
第2 運用基準別表の改定
当委員会は,別表の見直しを行うため,市場構造要件について調査を実施
し,次のとおり,運用基準別表の改定を行った(平成5年7月23日公表)。
これは,国内総供給価額及び市場占拠率に関する平成2年の調査結果並びに
平成5年7月23日公布の政令(第1章第1参照)による国内総供給価額の引
上げを踏まえて見直しを行ったものである。
この結果,新たにカレールウ,パーソナルコンピュータ,ビデオカメラな
ど24事業分野が別表に掲載され,魚肉ハム・ソーセージ,魔法びんなど20事
業分野が別表から削除されることとなった。改定後の別表掲載事業分野数は
87である(第1表)。
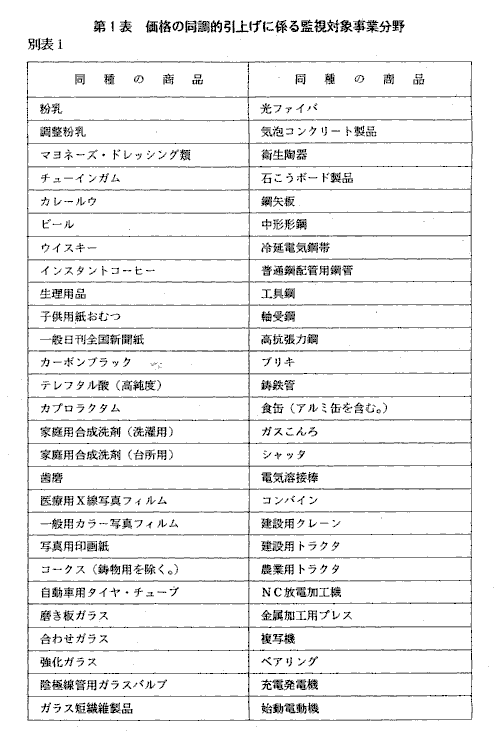 |
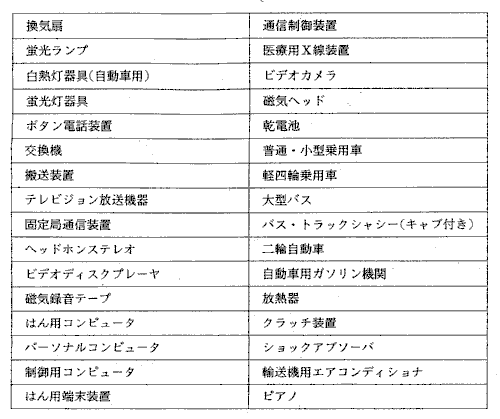 |
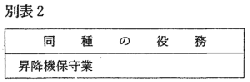
| 備考 |
| (1) |
本表は,当委員会が行った調査に基づき,平成2年の国内総供
給価額が600億円を超え,かつ,上位3社の市場占拠率の合計が
70%を超えると認められる同種の商品及び同種の役務に係る事業
分野(ただし,独占禁止法第18条の2第1項ただし書の規定に該
当する場合及び主要事業者の数が一の場合を除く。)を掲げたも
のである。 |
| (2) |
本表の商品順は工業統計表による。 |
|
|
第3 価格の引上げ理由の報告徴収
平成5年度下期において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的
引上げに該当すると認めてその引上げ理由の報告を徴収したものは,乾電池
の1件である。
平成5年度中に行われた価格の同調的引上げについて,平成6年度上期に
価格の引上げ理由の報告を徴収したものは,一般日刊全国新聞紙の1件であ
る。
また,平成6年度上期に行われた価格の同調的引上げについて,平成6年
度上期に価格の引上げ理由の報告を徴収したものは,ビールの1件である。
各品目の価格引上げ理由の概要は以下のとおりである。
| 1 |
乾 電 池 |
|
乾電池の昭和63年における国内総供給価額は890億円であり,上位3社
の市場占拠率の合計は72.8%である。主要事業者は,松下電池工業株式会
社(以下「松下電池」という。),日立マクセル株式会社(以下「日立マク
セル」という。),東芝電池株式会社,株式会社ソニー・エナジー・テック
及び富士電気化学株式会社の5社であり,首位事業者は,松下電池である。
松下電池は平成5年3月1日から,日立マクセルは同年4月1日から,
それぞれ,乾電池のうち筒形マンガン乾電池の販売価格の引上げを実施し
たが,この価格の引上げは,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調
的引上げに該当すると認められたので,当委員会は,平成5年9月13日,
これら2社に対して価格引上げの理由の報告を求めた。
| (1) |
各社の価格引上げ状況 |
|
松下電池及び日立マクセルの価格引上げの公表日,取引先への通知
日,価格引上げ予定日,実際の価格引上げ日及び代表的な製品(単3形
黒)のメーカー希望小売価格の引上げ率は,下表のとおりである。
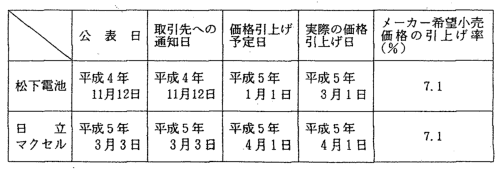 |
| (2) |
各社の価格引上げ理由 |
|
松下電池及び日立マクセルから提出された報告書によると,価格引上
げの理由は,以下のとおりである。
| ア |
松 下 電 池 |
|
松下電池は,筒形マンガン乾電池の価格引上げの主たる理由とし
て,需要がほぼ横ばいで推移しているところ,販売費及び一般管理費
の上昇等により平成3年度(平成3年4月1日~平成4年3月31日)
においては,営業利益額が昭和62年度(昭和62年4月1日~昭和63年
3月31日)と比較して平成3年度売上高の6.0%分減少し,さらに,
平成5年度(平成5年4月1日~平成6年3月31日)までに販売推進
費が平成3年度売上高の2.0%分上昇して,合理化を行っても目標と
する収益が得られないことが見込まれたことを挙げている。 |
| イ |
日立マクセル |
|
日立マクセルは,筒形マンガン乾電池の価格引上げの主たる理由と
して,売上高の減少,販売費及び一般管理費の上昇等により,平成5
年3月21日から同年9月20日までの間の営業利益を1年間に換算して
みると,平成4年3月21日から平成5年3月20日までの間と比較して
44.6%減少することが見込まれ,合理化を行っても電池部門における
設備投資に必要な経費を確保するだけの収益を得ることができないと
判断したことを挙げている。 |
|
|
| 2 |
一般日刊全国新聞紙 |
|
一般日刊全国新聞紙の平成2年における国内総供給価額は5,830億円で
あり,上位3社の市場占拠率の合計は81.6%である。主要事業者は,株式
会社読売新聞社(以下「読売」という。),株式会社朝日新聞社(以下「朝
日」という。),株式会社毎日新聞社(以下「毎日」という。),株式会社日
本経済新聞社(以下「日経」という。)及び株式会社産業経済新聞社の5
社であり,首位事業者は,読売である。
毎日及び朝日は平成5年12月1日から,読売は平成6年1月1日から,
日経は同年2月1日から,それぞれ,新聞購読料の引上げを実施したが,
この購読料の引上げは,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引
上げに該当すると認められたので,当委員会は,平成6年3月11日,これ
ら4社に対して購読料引上げの理由の報告を求めた。
| (1) |
各社の購読料引上げ状況 |
|
毎日,朝日, 読売及び日経の購読料引上げの公表日,公表日に予告さ
れた実施日,実際の実施日及び引上げ状況は,下表のとおりである。
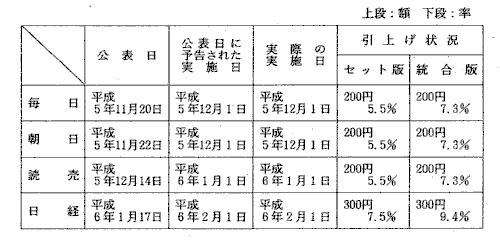
|
| (2) |
各社の購読料引上げ理由 |
|
読売,朝日,毎日及び日経から提出された報告書によると,購読料引
上げの理由は,以下のとおりである。
| ア |
読 売 |
|
読売は,購読料引上げの主たる理由として,広告収入が減少し,設
備投資に伴う償却費等が増加していることから,人件費の抑制等の努
力を行っても平成5年度(平成5年4月1日~平成6年3月31日)に
おいて新聞部門で約35億円の赤字が見込まれたこと及び販売店におけ
る従業員の待遇改善を図る必要があったことを挙げている。 |
| イ |
朝 日 |
|
朝日は,購読料引上げの主たる理由として,
朝日新聞について,平
成5年度上半期(平成5年4月1日~同年9月30日)における広告収
入が平成4年度上半期(平成4年4月1日~同年9月30日)と比較し
て12.5%減少し,コストの圧縮を図っても1か月につき新聞1部当た
り56.8円の黒字から70.6円の赤字へと127.4円の減益となったこと及
び戸別配達網の維持を挙げている。 |
| ウ |
毎 日 |
|
毎日は、購読料引上げの主たる理由として,広告収入の減収が続
き,平成5年度(平成5年4月1日~平成6年3月31日)における会
社全体の経常収支が約100億円の赤字となることが予測され,要員削
減 経費削減及び製作工程の合理化を行っても経営の安定を図れない
事態が予測されたこと並びに販売店における労働力の確保及び従業員
の待遇改善を図る必要があったことを挙げている。 |
| エ |
日 経 |
|
日経は,購読料引上げの主たる理由として,日本経済新聞につい
て,平成5年上半期(平成5年1月1日~同年6月30日)における広
告収入が平成4年上半期(平成4年1月1日~同年6月30日)と比較
して14.0%減少し,それに見合う新聞製作費及び人件費の削減ができ
ず,38.3%の減益となったこと及び販売店における人件費負担が増大
したことを挙げている。 |
|
|
| 3 |
ビ ー ル |
|
ビールの平成2年における国内総供給価額は1兆3,826億円であり,上
位3社の市場占拠率の合計は89.6%である。主要事業者は,麒麟麦酒株式
会社(以下「キリン」という。),アサヒビール株式会社(以下「アサヒ」
という。),サッポロビール株式会社(以下「サッポロ」という。)及びサ
ントリー株式会社(以下「サントリー」という。)の4社(以下「4社」
という。)であり,首位事業者はキリンである。
4社は,平成6年5月1日からビールの販売価格の引上げを実施した
が,この価格の引上げは,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的
引上げに該当すると認められたので,当委員会は,平成6年6月29日,こ
れら4社に対して価格引上げの理由の報告を求めた。
| (1) |
各社の価格引上げ状況 |
|
4社の価格引上げの公表日,取引先への通知日及び価格引上げ日は下
表のとおりである。
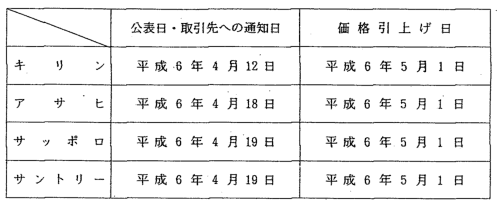
価格引上げの内容を対抗関係にあると認められる製品ごとにみると,
生産者価格,メーカー希望卸売価格及びメーカー希望小売価格のそれぞ
れの引上げ額及び新価格は,4社とも一部例外を除き,同一となってい
る。
4社のビールの主要製品のメーカー希望小売価格について,新価格並
びに引上げ額及び引上げ率を示すと,下表のとおりである。
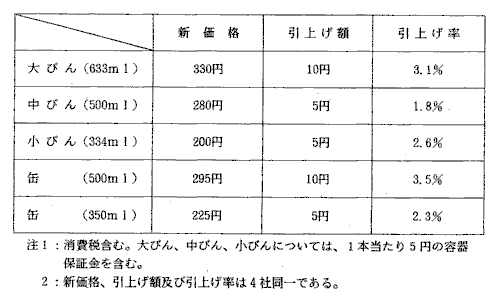
なお,4社がライセンス生産や製品輸入によって取り扱っている外国
銘柄品については,メーカー間で販売価格の引上げ額が同一のものであ
るが,その引上げ額は同容量の国産銘柄品のものに比べて小さくなって
いる。また,価格の引下げや据置きが行われているものもある。 |
| (2) |
各社の価格引上げ理由 |
|
4社から提出された報告書によると,価格引上げの理由は,以下のと
おりである。
| ア |
キ リ ン |
|
キリンは,ビールの価格引上げの主たる理由として,平成6年5月
1日からビールに係る酒税が1kl当たり14,008円(消費税込み)引
き上げられたことを挙げている。価格引上げ額については,増税額を
価格に転嫁すること,従来の慣行どおりメーカー希望小売価格の引上
げ幅を5円単位とすること,製品ごとに差益が生じる場合のメー
カー,卸売,小売間の配分は従来の慣行に基づくこと,全体として
メーカーに余分な差益が生じないようにすること等の考え方に基づい
て,製品ごとに増税額相当分を端数調整し決定したとしている。な
お,外国銘柄品の引上げ額の決定については,メーカー希望小売価格
を国産銘柄品と同一価格にすることをその主たる根拠に挙げている。
端数調整の結果メーカーに発生する差益については,流通業者より
要望の強かった空容器取扱手数料の増額に充てることとしている。 |
| イ |
ア サ ヒ |
|
アサヒは,ビールの価格引上げの主たる理由として,平成6年5月
1日からビールに係る酒税が1kl当たり14,008円(消費税込み)引
き上げられたことを挙げている。価格引上げ額については,消費課税
という酒税の性格から増税相当額は当然価格に転嫁することとし,製
品ごとの内容はキリンに追随したとしている。なお,外国銘柄品の引
上げ額の決定については,バドワイザーの価格を勘案して,国産銘柄
品のメーカー希望小売価格と同一価格にすることをその主たる根拠に
挙げている。
端数調整の結果メーカーに発生する差益については,流通業者より
要望の強かった空容器取扱手数料の増額に充てることとしている。 |
| ウ |
サッポロ |
|
サッポロは,ビールの価格引上げの主たる理由として,平成6年5
月1日からビールに係る酒税が1kl当たり14,008円(消費税込み)
引き上げられたことを挙げている。製品ごとの価格引上げ額について
は,増税に見合う価格の引上げを基本とし,過去の慣行に従ってメー
カー希望小売価格が5円,10円単位となるようにするとともに,キリ
ンの動向を勘案したとしている。
端数調整の結果メーカーに発生する差益については,流通業者より
要望の強かった空容器取扱手数料の増額に充てることとしている。 |
| エ |
サントリー |
|
サントリーは,ビールの価格引上げの主たる理由として,平成6年
5月1日からビールに係る酒税が1kl当たり14,008円(消費税込
み)引き上げられたことを挙げている。価格引上げ額については,消
費課税という酒税の性格から増税相当額は当然価格に転嫁することと
し,製品ごとの内容はキリンに追随したとしている。
端数調整の結果メーカーに発生する差益については,流通業者より
要望の強かった空容器取扱手数料の増額に充てることとしている。 |
|
|