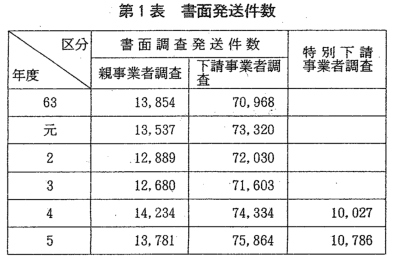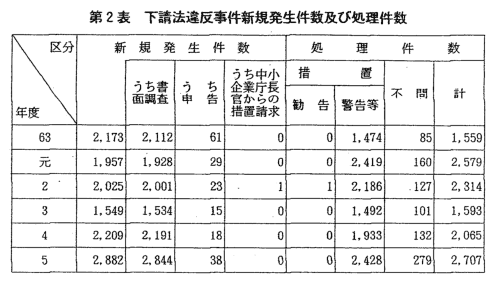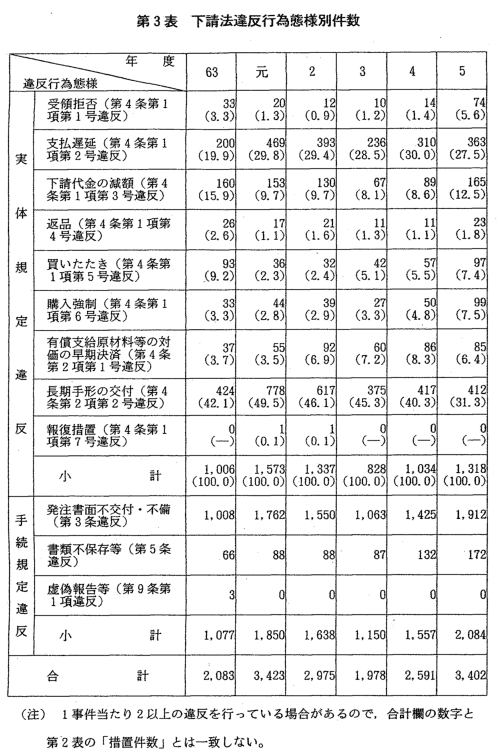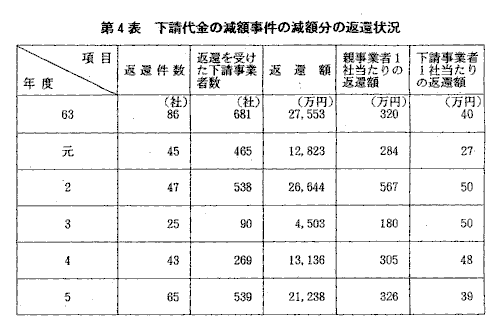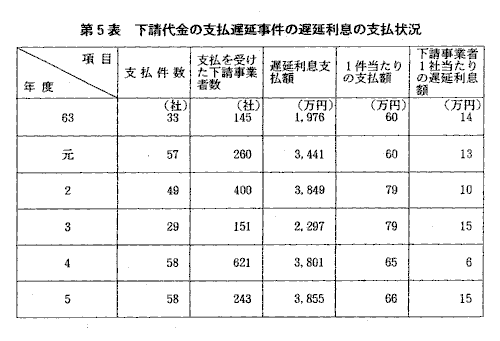第14章 下請代金支払遅延等防止法に関する業務
第1 概 説
下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の
濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図る
とともに下請事業者の利益を保護することを目的として,昭和31年に制定さ
れた独占禁止法の不公正な取引方法の規制の特別法である。
下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1,000万円を超え1億
円以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1,000万円以下の事業者(下
請事業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業
者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びそ
の2年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した
給付の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2
号),③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いたた
き(同項第5号),⑥物品等の強制購入(同項第6号),⑦有償支給原材料等
の対価の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第
2号)などの行為を行った場合には,当委員会は,その親事業者に対し,当
該行為を取りやめ,下請事業者が被った不利益の現状回復措置等を講じるよ
う勧告する旨を定めている。
第2 違反被疑事件の処理
下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告
が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製
造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期
的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施
して違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業が被った不利益の現状回復措置等を講じ
させている(第1表,第2表,附属資料8-1表,
8-2表)。
| 1 |
書 面 調 査 |
|
本年度においては,資本金3,000万円以上の主として製造業者12,781社
及びこれらと取引している下請事業者75,864社を対象に書面調査を行った
ほか,資本金1,000万円超3,000万円未満の製造業者1,000社に対して書廟
調査を実施した(第1表)。
また,円高等の影響が大きいと思われる業種に係る下請事業者につい
て,別途,特別下請事業者調査として,10,786社の下請事業者を対象に書
面調査を行っている。 |
| 2 |
違反事件の新規発生件数及び処理件数 |
|
| (1) |
本年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は2,882件であ
る。このうち,特別下請事業者調査を含む書面調査により機権探知した
ものが2,844件であり,下請事業者からの申告によるものが38件(新規
発生件数全体の1.3%)であった(第2表)。 |
| (2) |
本年度において違反被疑事件として処理した件数は2,707件であり,
このうち,2,428件(89.7%)について違反行為が認められた。これに
ついては,親事業者が,調査・指導の段階で自発的に当該違反行為を取 |
|
りやめるととも
に,下請事業者
に与えた不利益
を解消する措置
を講じたので誓
告等の措置を
探った。また,
下請法違反を
行った親事業者
に対しては,社
内研修,監査等
により違反行為
の再発防止のた
めに,社内体制
を整備するよう
指導した(第2
表)。 |
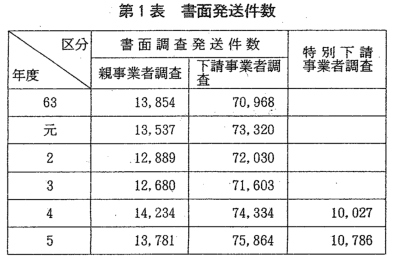
|
|
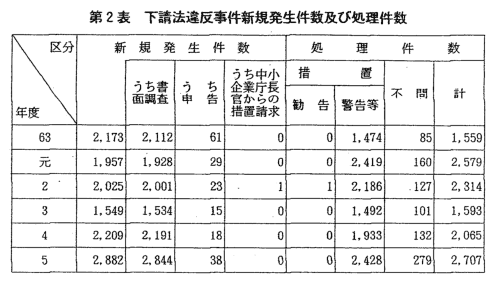 |
|
| 3 |
違反行為態様別件教 |
|
本年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別に見ると,手
続き規定違反が2,084件(違反件数全体の61.3%)となっている。このう
ち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していない
又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が1,912
件(同56‐2%)となっている。
また,実体規定違反は,1,318件(違反件数全体の38.7%)となってお
り,このうち,手形期間が1208(繊維製品の場合は90日)を超える長期
手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号違反)が412件(実
体規定違反件数全体の31.3%),下請代金の支払遅延(第4条第1項第2
号違反)が363件(同27.5%),下請代金の減額(第4条第1項第3号違
反)が165件(同125%),買いたたき(第4条第1項第5号違反)が97件
(同7.4%)となっている〈第3表参照)。
下請代金の減額事件については,本年度中に,親事業者65社により総額
21,238万円が539社の下請事業者に返還されており(第4表参照),支払遅
延が認められた事件については,親事業者58社により総額3,855万円の
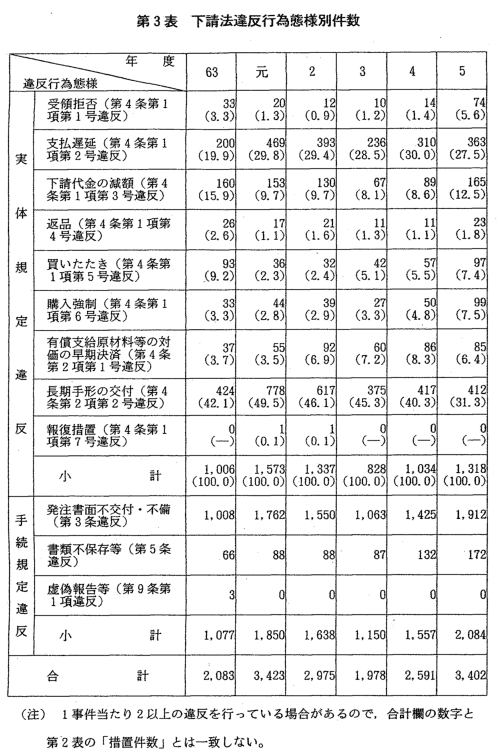
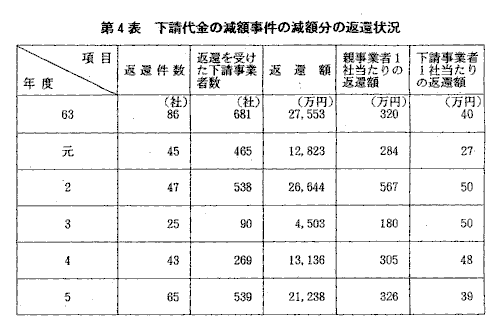
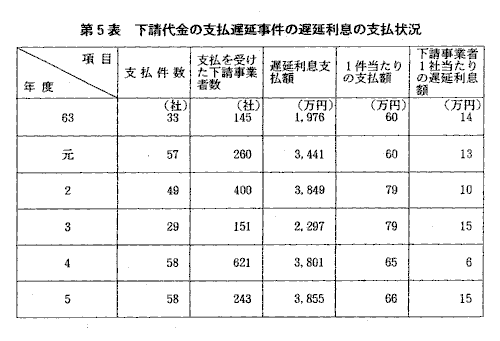
遅延利息が243社の下請事業者に支払われている(第5表参照)。 |
| 4 |
特別下請事業者調査 |
|
平成5年3月,景気低迷の影響が大きいと思われる電気機械器具製造業
及び輸送用機械器具製造業の2業種に係る下請事業者について,毎年定期
的に行っている調査とは別に書面調査を行ったが,これに基づき本年度に
おいて132件の親事業者の行為について警告等の措置を採った。
措置件数のうち,実体規定違反の占める割合が56.1%であり,本年度の
措置件数全体における同割合が38.7%であったのと比べ,高いものとなっ
ている。
実体規定違反のうち多いものは,買いたたき,支払遅延,割引困難な手
形の順となっており,景気低迷の影響により下請単価の引下げが増えてい
ることが反映されている。
10月には円高等の影響が大きいと思われる一般機械器具製造業,精密機
械器具製造業,金属製品製造業,鉄鋼業,繊維工業及び衣服・その他繊維
製品製造業の6業種に係る下請事業者10,786社について書面調査を実施し
た。この調査を踏まえ12月に親事業者等に対し下請法の遵守要請を行うと
ともに,下請法違反の疑いのある行為について所要の調査を行っている。 |
| 5 |
主な違反行為事例 |
|
本年度において,下請法違反の疑いで調査し,警告等の措置を採った主
な事例は次のとおりである。
| (1) |
注文書の不交付等(第3条) |
|
A化学薬品販売業者は,ラベル等の印刷を下請事業者に委託してい
る。
A社は,下請事業者が1社であり,発注内容,支払条件等については
下請事業者も了解しているとして注文書を交付していなかった。
(A社は,注文書を交付することとした。)
注:( )は,親事業者が探った改善措置の概要である(以下同じ。)。 |
| (2) |
受領拒否(第4条第1項第1号) |
|
B電気機械器具製造業者は,電気製品の部品の製造を下請事業者に委
託している。
B社は,自社の生産計画を変更したことを理由として,発注後,下請
事業者に納期の延期を通知し,発注時に定めた納期に下請事業者からの
給付を受領していなかった。
(B社は,下請事業者の責に帰すべき理由がない限り,納期の延期を
行わないこととした。) |
| (3) |
支払遅延(第4条第1項第2号) |
|
| ア |
期日現金払による支払遅延 |
|
C包装資材製造業者は,包装資材の印刷等を下請事業者に委託して
いる。
C社は,原材料の高騰,金利高等により減益の見通しとなったこと
から,手形の発行等に要する必要を節減するため,それまで毎月末日
締切,翌月末日手形払(手形期間100日)であった支払制度を期日現
金払(手形満期相当日に現金で支払う方法)に変更した。このため,
最長100日の支払遅延が生じていた。
(C社は,下請事業者に対しては期日現金払を中止し,支払遅延し
ていた下請代金について遅延刺息を支払った。) |
| イ |
検収遅れ等による支払遅延 |
|
D電気機械器具製造業者は,部品・製品の組立・加工を下請事業者
に委託している。
D社は,当月末日納品締切,翌月末日払とする支払制度を採ってい
たが,検査完了をもって納品があったものとみなし,当月末日までに
納品されたものであっても検査完了が翌月となった場合には翌月に納
品があったものとして翌月の支払対象に計上していたため,一部の下
請代金の支払が,下請事業者の給付を受領してから60日を経過してい
た。
(D社は,当月末日までに納品されたものについては検査完了の有
無にかかわらず当月の支払対象に計上するとともに,支払遅延してい
た下請代金の遅延利息を支払った。) |
|
| (4) |
下請代金の減額(第4条第1項第3号) |
|
| ア |
新単価の遡及適用による減額 |
|
E電気機械器具製造業者は,電気製品の部品の製造を下請事業者に
委託している。
E社は 下請事業者と単価の引下げについて合意したが,合意日以
前に旧単価で発注したものについてまで新単価を遡って適用し,10日
ないし2ヵ月程度の期間における発注分について旧単価と新単価の差
額分を下請代金の額から減額していた。
(E社は,減額した額を下請事業者に返還した。) |
| イ |
収益確保のため協力金を徴収したことによる減額 |
|
F一般機械器具製造業者は,機械部品の製造を下請事業者に委託し
ている。
F社は,収益が悪化してきたため外注費を節減することとし,下請
事業者に対し,各下請事業者の当該年度における納入予定総額に応じ
て一定の額を「協力金」と称して下請代金から減額していた。
(F社は,減額行為を中止するとともに減額した額を下請事業者に
返還した。) |
|
| (5) |
返品(第4条第1項第4号) |
|
G電気製品製造業者は,電気製品の部品の製造を下請事業者に委託し
ている。
G社は,下請事業者からの給付受領後に,返品の理由を明確にしない
で下請事業者の給付に係るものを引き取らせており,この中に良品も含
まれていた。
(G社は,下請事業者の責に帰すべき理由がないものについて返品は
行わないこととした。) |
| (6) |
買いたたき(第4条第1項第5号) |
|
H電気機械器具製造業者は,産業用機械の部品の製造を下請事業者に
委託している。
H社は,下請事業者に2,000個発注することを前提として下請代金の
単価について交渉し,合意した単価に基づいて実際には300個しか発注
しなかったのに2,000個発注することを前提とした単価を適用した。
この行為は,多量の発注をすることを前提として下請事業者と交渉し
下請事業者と合意した単価を 少量しか発注しない場合の単価として下
諸代金の額を定めたものであり,買いたたきに該当するおそれがある。
(H社は,多量の発注を前提として定めた単価を,少量しか発注しな
い場合の単価としないこととした。) |
| (7) |
購入強制(第4条第1項第6号) |
|
I化学製品製造業者は液体石鹸の製造を下請事業者に委託している。
I社は,購買担当者を通じて下請事業者に対し自社製品のギフトセッ
トの購入先の紹介を要請したため,下請事業者の中には自らその商品を
購入することを余儀なくされたものもあった。
(I社は,購買担当者を通じて,下請事業者に自社製品の購入先の紹
介を要請しないこととした。) |
| (8) |
原材料等の対価の早期決済(第4条第2項第1号) |
|
J化学製品製造業者は,化成品,樹脂等の原材料の製造を下請事業者
に委託している。
J社は,化成品,樹脂等の原材料の製造を委託するに当たり,それに
要する原材料を下請事業者に有償で支給しているが,その有償支給した
原材料について加工期間を考慮せず,支給した月の直後の下請代金の支
払日に,それまで支給した原材料代金の全額を下請代金から控除してい
たため,当該原材料を用いて納入する物品に対する下請代金の支払期日
より早く環材料の代金が決済されているものがあった。
(J社は,原材料代金の決済日を下請事業者の加工期間を考慮して設
定し,当該原材料を用いて納入する物品に対する下請代金の支払期日よ
り早く原材料の代金が控除されないようにした。) |
| (9) |
割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号) |
|
K一般機械器具製造業者は,鋳物,鋼材等の製造を下請事業者に委託
している。
K社は,下請代金の支払に当たり一部手形を使用しているところ,得
意先からの支払条件が悪いという理由から一部の手形について手形期間
が6か月のものを交付していた。
(K社は,下請代金に係る手形期間をすべて120日以内とした。) |
|
第3 下請代金の支払状況等
当委員会は,定期調査により報告された結果を基に,昭和33年度以降,毎
年,下請代金の支払状況等を取りまとめ,これを公表している。本年度の親
事業者調査の対象とした資本金3,000万円以上の製造業者のうち,10,364社
(26,437事業所)について,その下請取引の実態及び下請代金の支払状況を
見ると,次のとおりである。
| 1 |
下請取引の実態 |
|
| (1) |
下請取引をしている割合 |
|
| ア |
下請取引をしている事業者の割合は73.9%(7,658社)であった。 |
| イ |
下請取引をしている事業者の割合を業種別に見ると,「精密機械器
具製造業」(93.6%),「電気機械器具製造業」(93.2%),「一般機械器
具製造業」(93.0%),「輸送用機械器具製造業」(92.2%)など機械
関係の業種において9割を超えているが,「窯業・土石製品製造業」
(35.1%),「石油製品・石炭製品製造業」(36.2%),「木材・木製品
製造業」(39.6%)などの業種では低い。 |
|
| (2) |
取引先下請事業者数 |
|
| ア |
親事業者の1事業所当たり取引先下請事業者の数は28社である。 |
| イ |
1事業所当たりの取引先下請事業者の数を業種別に見ると,最も多
いのは「精密機械器具製造業」(1事業所当たり59社の下請事業者と
取引している。),次いで「輸送用機械器具製造業」(同47社),「出版
・印刷・同関連産業」(同46社)であり,一般に下請取引をしている
企業の割合の高い機械関係の業種では取引先下請事業者数も多く,下
請取引をしている企業の割合の低い「石油製品・石炭製品製造業」(同
7社),「木材・木製品製造業」(同10社),「窯業・土石製品製造業」
(同11社)などでは取引先下請事業者数も少ない傾向にある。 |
|
|
| 2 |
下請代金の支払状況等 |
|
| (1) |
支払期間 |
|
| ア |
納品締切日から支払日までの月数(以下「支払期間」という。)を
事業所ごとに見たものの平均は0.81か月(24.3日)となっており,総
体として見ると,納品締切日を月末とした場合,下請代金は翌月25日
までには支払われているということになる。 |
| イ |
支払期間を業種別に見ると,繊維関係の業種において比較的短く,
機械関係の業種において比較的長いという傾向がある。 |
| ウ |
支払期間が1.0か月を超えるもの(この場合は,納品されてからそ
の代金が支払われるまでの期間が60日を超えることがあるので,下請
法第4条第1窮策2号の規定に違反するおそれがあるものである。)
は,248事業所(集計対象事業所数の2.6%に相当)である。なお,こ
れらのケースはすべて違反被疑事件として調査の対象としている。 |
|
| (2) |
現金支払割合 |
|
| ア |
下請代金のうち,現金で支払われる割合(以下「現金支払割合」と
いう。)を事業所ごとに見たものの平均は60.3%であり,総体として
見ると,下請代金の約6割は現金で支払われているということにな
る。 |
| イ |
現金支払割合を業種別に見ると,業種ごとに大きな差異があり,
「衣服・その他の繊維製品製造業」(88.7%),「なめし革・同製品・毛
皮製造業」(80.7%),「石油製品・石炭製品製造業」(78.1%),「食料
品製造業」(78.1%),「繊維工業」(77.2%)などが高いのに対し,
「精密機械器具製造業」(42.6%),「一般機械器具製造業」(43.5%)な .
どは低い。 |
|
| (3) |
手形期間 |
|
| ア |
下請代金を手形により支払っている場合の手形の期間(各事業所が
交付した手形のうち,最も期間の長い手形について集計)を見ると,
手形期間が90日以下のものは16.1%,90日超120日以下のものは
68.7%,120日超のものは15.2%である。 |
| イ |
120日超の手形を交付している事業所の割合が高い主要な業種は,
「プラスチック製品製造業」(35.6%),「家具・装備品製造業」(28.5%),
「窯業・土石製品製造業」(22.3%)などである。 |
|
|
| 3 |
下請代金の支払状況の推移 |
|
下請代金の支払状況の推移を見ると次のとおりであり,長期的には昭和
40年代以降,徐々に改善されてきている。
| (1) |
支払期間は,昭和30年代は1.0か月く締切日から30日)を超えていた
が,昭和40年代に入ると大幅に短縮され,昭和50年代以降は0.8か月(締
切日から24日)前後で推移している。 |
| (2) |
現金支払割合は,昭和40年代前半までは低下傾向にあったが,昭和40
年代後半から徐々に高くなっており,取り分け昭和53年度以降,下請代
金の半額以上が現金で支払われる状態が定着している。 |
| (3) |
120日を超える手形を交付している事業所の割合は,昭和40年代前半
までは増加傾向にあったが,昭和45年度の約60%をピークにそれ以降は
減少傾向にあり,昭和56年度以降は20%前後となっている。特に平成2
年度以降は20%を下回る状態が続いている。 |
|
第4 下請法の普及・啓発等
| 1 |
違反行為の未然防止及び再発防止の指導 |
|
下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効
果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止する
ことも肝要である。
この観点から,本年度においては,以下のとおり各種の施策を実施し,
違反行為の未然防止を図っている。
| (1) |
下請取引適正化推進月間 |
|
毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中小企業庁と共同し
て,新聞,雑誌,テレビ・ラジオ等で広報活動を行うほか,全国各地に
おいて下請法に関する講習会を開催する等下請法の普及啓発に努めてい
る。
本年度は 親事業者を対象に29都道府県(うち当委員会主催分17都道
府県〔17会場〕)において講習会を開催した(受講者は当委員会主催分
1,940名)。
また,当委員会は,下請取引を適正化するためには,取引のもう一方
の当事者である下請事業者にも下請法の趣旨内容を周知徹底する必要が
あることにかんがみ,昭和60年度以降 下請事業者を対象とした下請法
講習会を実施しており,本年度において19都道府県(22会場)で開催し
た(受講者1,091名)。 |
| (2) |
下請法遵守の要請 |
|
長引く景気の低迷と円高の影響等により下請事業者を取り巻く経済環
境は極めて深刻な状況にあり,特に年末の金融繁忙期においては下請中
小企業の資金繰り等が悪化することが懸念されるため,平成5年10月に
行った特別下請事業者調査の状況も踏まえ,平成5年12月8日,公正取
引委員会委員長・通商産業大臣連名で資本金1億円以上の親事業者約
8,500社に対し下請法の遵守を要請し,同時に約430団体に対し,傘下事
業者への下請法の周知徹底等を要請した。 |
| (3) |
広報,相談・指導業務 |
|
購買・外注担当者らに対する社内研修の実施及び購買・外注担当者向
けの下請法に関する遵守マニュアルの作成を積極的に指導したほか,親
事業者,関係団体等の研修会に講師等の派遣,資料の提供を行い,下請
法の普及啓発を行った。 |
|
| 2 |
都道府県との相互協力体制 |
|
下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利
益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と
の協力が必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関する
都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及啓発等の業務につい
て協力を得ている。
本年度においては,平成5年5月に都道府県下請企業行政担当課長会議
を開催するとともに,平成6年2月~3月にブロック別に都道府県下請取
引担当官会議を開催した。 |
| 3 |
下請取引改善協力委員 |
|
下請法の的確な運用に資するため,昭和40年度以降当委員会の業務に協
力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している。本年度におけ
る下請取引改善協力委員は,101名である。
本年度においては,平成5年6月に全国会議を,平成6年2月~3月に
ブロック別会議を,また,平成5年12月には首都圏におい4都県連絡会議
をそれぞれ開催した。 |
第5 ソフトウエア業における委託取引に関する実態調査
近年,非製造業のウエイトが高まっていることから,この分野における委
託取引の実態を明らかにするため昭和60年度から非製造業における委託取引
の実態調査を行ってきており,同調査の一環として平成5年1月から7月に
かけてコンピュータメーカー又はソフトウエア業者とソフトウエア業者との
間のソフトウエア開発に関する委託取引の実態調査を行った。
書面調査対象事業者は,ソフトウエア受託開発業者1,690社である(有効
回答657社,回答率38.9%)。
| 1 |
調査結果 |
|
| (1) |
発注書面の交付 |
|
回答業者の大半は「契約書又は注文書等の発注書面が交付されてい
る」としているが,一部口頭による発注も見受けられる。また,発注書
面が交付されているもののうち,約4割は作業途中に交付されるとして
いる。 |
| (2) |
代金の決定方法,決定時期 |
|
ソフトウエア開発は技術者の能力に依存するところが多く,開発に要
するコストが不確実である上,発注内容(仕様)の詳細が確定されて
も,各開発工程ごとにどの位の技術者が必要となるか,また開発にどの
位の期間を要するか等が不確実なため,委託代金の見積りはかなり難し
いとされる。発注者との間で委託代金はどのような方法で決定している
かについてみると,委託代金は「見積に基づいて話し合って決定する」
とするものが多いが,「コンピュータメーカー(又はソフトウエア業
者)の予算額で一方的に決められる」とするものも一部にみられる。ま
た,回答事業者の約4割は委託代金は作業途中に決定されるとしてい
る。 |
| (3) |
代金の支払制度 |
|
納品後60日を超えて支払う支払制度としているものが4割近くを占め
ており,中には検収制度が探られ,検収に要する期間が長いため,納品
後60日を超えて支払われるものも見受けられた。また,発注者側の都合
等で支払制度どおり支払われず,支払を遅らされたことがあるとするも
のが1割を超えていた。 |
| (4) |
減額(値引き) |
|
コンピュータメーカーとの取引において2割弱,ソフトウエア業者と
の取引においては約8割のものが,支払われた代金が決められていた受
注代金に比べて下回ったことがあるとしている。この中には,受注者の
責に帰すべき理由による減額があるほか,開発作業の特殊性から発注時
に発注内容(仕様)の詳細,委託代金の額等が確定できず,このため発
注後の打合せ等により発注内容(仕様)の詳細を確定し,これに基づき
決定された代金が,発注時の発注内容(仕様)の詳細が定まらない段階
で暫定的に示された大枠の概算額を下回ったことをもってあるとしてい
るものもある。また,納入品に係る瑕疵の存在等を理由とする減額にお
いては,打合せ奏で確定された仕様の詳細に対する双方の認識の違いか
ら,その責任の所在が必ずしも明らかでない場合がある。しかし,その
一方で,一部において受注者の責に帰すべき理由がないのが明らかであ
るにもかかわらず,予算がなくなった等の理由で減額されたとするもの
や,責に帰すべき理由のあることが明らかな場合であっても,若干の納
期遅れに対し,代金を半減されたとするものも見受けられた。 |
| (5) |
発注内容(仕様)の変更 |
|
回答業者の8割弱が発注後の作業途中に発注内容(仕様)の変更の指
示があるとしており,ユーザー,コンピュータメーカー又はソフトウエ
ア業者等発注者側の都合による発注内容(仕様)の変更に伴う追加費用
が受注者に負担させられているケースが一部に見受けられた。 |
| (6) |
受領拒否 |
|
納品の受取を拒まれたり,受取日を延期されたことがあるとするもの
は約1割となっており,受注者の責に帰すべき理由によらない発注者側
の一方的な都合によるものが一部見受けられた。 |
| (7) |
納品後における手直し |
|
納品後における手直しについて4割のものがあるとしている。ソフト
ウエア開発には「バグ」と呼ばれるプログラム上の間違いが出てくるの
はつきものとも言われており,手直しの多くはバグへの対応のものとみ
ることができる。また,発注内容(仕様)との相違等から行われる手直
しについては,前期減額(値引き)におけると同様,発注内容(仕様)
の詳細に対する双方の認識の相違から,その責任の所在が必ずしも明ら
かでない場合がある。しかし,受注者の責に帰すべき理由かないのが明
らかな発注者側の都合による手直しのための費用を負担させられたとす
るものも一部に見受けられた。 |
| (8) |
購 入 強 制 |
|
物品の購入,協賛金の要請等があるとするものが1割程度みられた。
物品の購入要請等は,一般企業との取引において多く,コンピュータ
メーカー又はソフトウエア業者との取引においては少ないものとみられ
る。しかし,一部において取引先コンピュータメーカーの発注担当者か
ら,当該コンピュータメーカーが主催するイベントのチケットの購入の
要請があり,仕方なく購入したとするものも見受けられた。 |
|
| 2 |
関係団体に対する要望 |
|
調査の結果,取引上優越した地位にある者がその地位を利用して行えば
不公正な取引方法(優越的地位の濫用行為)に該当し,独占禁止法上の問
題を生じさせるおそれのある行為がー部に見られたので,平成5年12月に
コンピュータメーカーの団体である社団法人日本電子工業振興協会並びに
ソフトウエア業者の団体である社団法人情報サービス産業協会及び社団法
人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会に対し,傘下会員に独占
禁止法上の問題となる行為が生じることを防止し,委託取引の適正化を推
進するよう指導徹底方を要請した。 |
第6 建設業の下請取引における不公正な取引方法の規制
建設業の下請取引において,元請員人等が下請負人に対し,請負代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認められるとき
は,建設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知
事又は中小企業庁長官が当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措
置を採ることを求めることができることとなっている。
なお,本年度においては,措置請求はなかった。