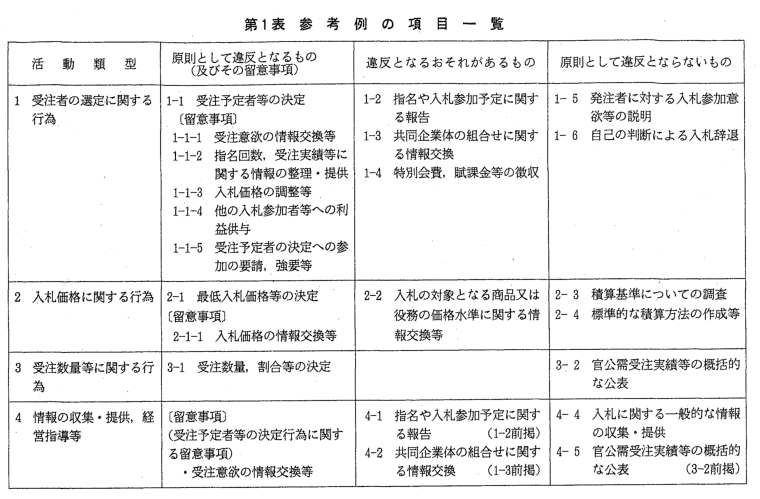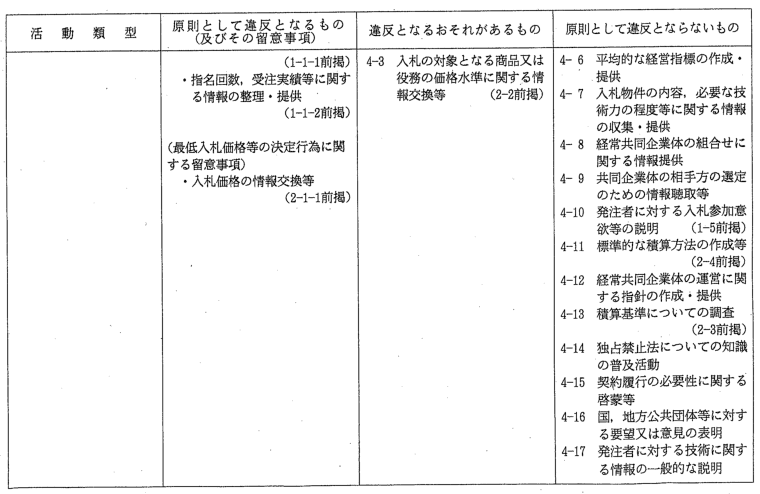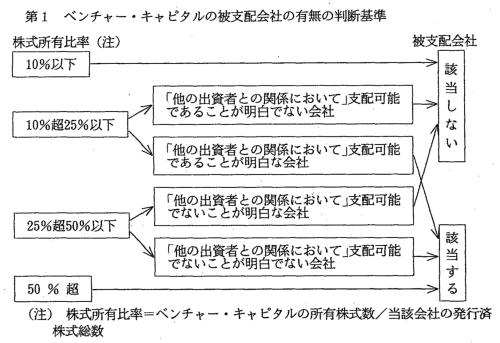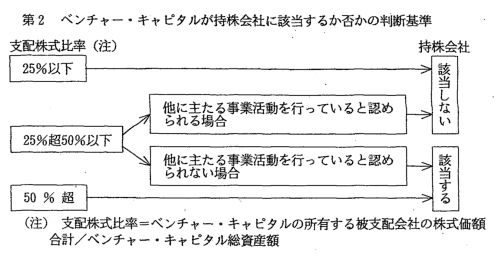第4章 法運用の透明性の確保と独占禁止法違反行為の未然防止
第1 概 説
独占禁止法の運用を効果的なものとするためには,独占禁止法の目的,規
制内容及び運用の方針が国内外における事業者や消費者に十分理解され,そ
れが深められていくことが不可欠である。このような観点から,当委員会
は,各種の広報活動を行うとともに,事業者及び事業者団体の独占禁止法違
反行為を具体的に明らかにした各種のガイドラインを公表し,それに基づい
て,個々の具体的なケースについて事業者等からの相談に応じている。
本年度においては,平成6年6月30日に「行政指導に関する独占禁止法上
の考え方」を,同年7月 5日に「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体
の活動に関する独占禁止法上の指針」をそれぞれ策定した。また,「事業者
団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を全面的に改定することとし,そ
の原案を平成7年4月3日に公表した。
また,「金融会社の株式保有の認可に関する事務処理基準」を作成し,平
成6年6月20日に公表したほか,同年8月18日,「会社の合併等の審査に関
する事務処理基準」及び「会社の株式所有の審査に関する事務処理基準」を
改定・公表した。さらに,「ベンチャー・キャピタルに対する独占禁止法第
9条の規定の運用についての考え方」を作成し,同年8月23日に公表した。
第2 行政指導に関する独占禁止法上の考え方
| 1 |
趣旨及び経緯 |
|
| (1) |
公正取引委員会は,従来から,独占禁止法との関係において問題を生
じさせるおそれがある行政指導について,他の行政機関と調整を図り,
問題点の指摘及び改善の要望をしてきているところである。 |
| (2) |
近年,公正かつ自由な競争の維持・促進を図ることが一層重要とな
り,このような観点からも規制緩和が積極的に進められている。また,
行政指導に関し行政手続法により手続き上の一定のルールが定められた
ところである。
このような状況にかんがみ,当委員会は,これまでの他の行政機関と
の調整事例や独占禁止法違反被疑事件の審査過程等で認められた事例を
踏まえ,行政指導に関する独占禁止法上の考え方を具体的に明らかにす
るため,平成6年6月30日,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」
(行政指導ガイドライン)を作成・公表した。 |
| (3) |
なお,「規制緩和推進計画」(平成7年3月31日閣議決定)において,
規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われる
ことのないよう,関係省庁は本ガイドラインの趣旨を踏まえ,当委員会
と事前に所要の調整を図ることが決定されている。 |
|
| 2 |
行政指導ガイドラインの概要 |
|
本ガイドラインは,「はじめに」,「1 行数指導と独占禁止法との関係
についての基本的な考え方」,「2 行政指導の諸類型と独占禁止法」及び
「3 許認可等に伴う行政指導についての独占禁止法上の考え方」から構
成されており,その概要は次のとおりである。
| (1) |
「はじめに」においては,行政機関が多様な目的のために行っている
行政指導のうち,事業者の参入,退出,商品又は役務の価格,数量,設
備等に直接・間接に影響を及ぼすようなものは,その目的,内容,方法
等によっては,公正かつ自由な競争を制限し,又は阻害するとともに,
独占禁止法違反行為を誘発する場合さえあることに十分留意する必要が
ある旨指摘している。 |
| (2) |
「1 行政指導と独占禁止法との関係についての基本的な考え方」に
おいては,行政指導を法令に具体的な規定がある行政指導と法令に具体
的な規定がない行政指導に分け,それぞれについて,独占禁止法との関
係についての基本的な考え方を示すとともに,行政指導によって誘発さ
れた行為であっても独占禁止法違反行為の要件に該当する場合には,当
該行為に対する同法の適用は妨げられないことを指摘している。 |
| (3) |
「2 行政指導の諸類型と独占禁止法」においては,行政指導の類型
を,①参入・退出に関する行政指導,②価格に関する行政指導,③数
量・設備に関する行政指導,④営業方法,品質・規格,広告・表示等に
関する行政指導に分け,行政機関は,法令に具体的な規定がない行政指
導により公正かつ自由な競争が制限され,又は阻害されることのないよ
う十分留意する必要がある旨指導するとともに,独占禁止法との関係に
おいて問題を生じさせるおそれがある行政指導の具体例を挙げている。 |
| (4) |
「3 許認可等に伴う行政指導についての独占禁止法上の考え方」に
おいては 行政機関は,法令に規定された要件を超えた許認可等の運用
により,事業者の自由な事業活動が制限され,公正かつ自由な競争が制
限され,又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある旨指摘
するとともに,独占禁止法との関係において問題を生じさせるおそれが
ある行政指導の具体例を挙げている。 |
|
第3 公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針
当委員会は,入札談合の防止を図るとともに,事業者及び事業者団体の適
正な活動に役立てるため,平成6年7月 5 日,「公共的な入札に係る事業者
及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(入札ガイドライン)
を策定・公表した。
なお,本ガイドラインの策定に伴い,「公共工事に係る建設業における事
業者団体の諸活動に関する独占禁止法上の指針」(昭和59年2月21日公表)
は,廃止した。
| 1 |
趣旨及び経緯 |
|
| (1) |
入札参加者があらかじめ受注予定者や最低入札価格等を決定すること
によって入札により発注される商品又は役務の取引に係る競争を制限す
るいわゆる入札談合は,入札制度の実質を失わしめるものであるととも
に,競争制限行為を禁止する独占禁止法の規定に違反する行為である。
当委員会としては 従来から,入札談合に対して厳正に対処してき
た。昭和54年度から平成5年度までの入札談合事件の審決は55件あり,
同期間中の独占禁止法第3条及び第8条違反事件の全審決175件の約3
割を占めている。特に最近についてみると,平成4年度及び平成5年度
の入札談合事件の審決は合わせて32件で,同じく全審決58件の過半数を
占める状況となっている。 |
| (2) |
近年このように入札談合事件が数多く生じている状況にかんがみる
と,関係業界等において,独占禁止法についての正しい理解がなお不十
分なところがあるように思われる。このため,当委員会としては,引き
続き入札談合に厳正に対処していくことはもとよりとして,関係の事業
者及び事業者団体に対して,入札に関連した活動と独占禁止法との関係
について明確に示し,その理解を促進することにより,入札談合の未然
防止の徹底を図ることが,極めて重要であると考えている。
入札ガイドラインは,かかる認識に立って,これまでの当委員会の法
連用の経験に基づき,事業者及び事業者団体の入札に関連したどのよう
な活動が独占禁止法上問題となるかについて,その考え方を具体的に示
したものである。 |
| (3) |
当委員会は,平成5年10月21日に入札ガイドラインの策定の方針を公
表した後,内容の検討を進め,平成6年3月4日に同ガイドラインの原
案を作成・公表し,広く内外の関係各方面に,同原案に対する意見を求
めた。
原案に対しては,国内関係機関,外国政府等から多数の意見が寄せら
れた。当委員会は,これらの意見をつぶさに検討し,十分参酌した上,
更に明確で分かりやすいものにするとの観点から,原案の一部を修正
し,本ガイドラインを策定したものである。 |
|
| 2 |
入札ガイドラインの概要 |
|
入札ガイドラインは,「はじめに」,「第1 入札に係る事業者及び事業
者団体の活動に関する独占禁止法の規定の概要」及び[第2 入札に係る
事業者及び事業者団体の実際の活動と独占禁止法」から構成されており,
その概要は次のとおりである。
| (1) |
「第1 入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法
の規定の概要」では,入札に係る事業者及び事業者団体の活動との関係
において,どのような行為が独占禁止法で禁止されているか,また,違
反行為に対してはどのような措置等が採られることとなるかという,独
占禁止法の規定の概要を示している。 |
| (2) |
「第2 入札に係る事業者及び事業者団体の実際の活動と独占禁止
法」は,受注者の選定に関する行為,入札価格に関する行為,受注数量
等に関する行為及び情報の収集・提供,経営指導等の4つの主要な活動
類型によって構成され,これら活動類型ごとに,「原則として違反とな
るもの」,「違反となるおそれがあるもの」及び「原則として違反となら
ないもの」を参考例として示している(第1表)。このうち,
| ア |
「原則として違反となるもの」には,これまでの審決及び課徴金納
付命令における違反行為の内容を整理し,それに基づき,原則として
違反となると考えられる行為を挙げている。
あわせて,「原則として違反となるもの」に挙げられた行為との関
連で,入札談合防止の観点から特に留意すべき事項について記述して
いる。 |
| イ |
「違反となるおそれがあるもの」には,これまでの審決における違
反行為及び違反行為に関連して認定された事実を踏まえ,違反行為に
伴って行われるおそれがある又は違反行為につながるおそれがある行
為を挙げている。 |
| ウ |
「原則として違反とならないもの」には,それ自体では原則として
違反とならないと考えられる行為を挙げている。 |
|
|
| 3 |
入札ガイドラインの普及・啓発 |
|
入札ガイドラインについては,当委員会主催の説明会を行うとともに,
各種業界団体等が実施する研修会等に対して講師として職員を派遣する等
により,積極的に普及活動を行った。
さらに,発注官庁に対しても,平成5年度から実施している公共入札に
関する公正取引委員会と連絡担当官(独占禁止法違反の可能性のある行為
に関する情報提供のために,発注官庁において指名されている者)との会
議の場や,発注官庁,地方公共団体等の調達担当官を対象とした研修の場
等を利用して入札ガイドラインの普及・啓発に努めた。 |
第4 事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針の改定
当委員会は,事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止を図り,そ
の適正な活動に役立てるため,昭和54年8月に「事業者団体の活動に関する
独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイドライン)を策定・公表した。その
後15年以上が経過し,社会経済状況の変動の中で事業者団体の活動内容も変
化しており,事業者団体に係る独占禁止法上の問題にも新しい形のものが出
てきている。
現在,我が国経済社会は,規制緩和の推進,市場開放等を通じた重要な構
造改革の時期にあり,その中で,独占禁止法の有効かつ適切な運用により,
内外事業者の公正かつ自由な競争を促進することが,ますます重要となって
いる。
事業者団体は,各産業分野において,引き続き重要な位置を占めており,
この時期にあって,事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止の一層
の徹底を図り,その活動が競争促進の方向に合致したものとなるよう努力す
ることがより強く求められている。
以上を踏まえ,当委員会としては,事業者団体の公的規制,行政等に関連
した活動,参入制限行為等についての指針を新たに提示する等の方向で,事
業者団体ガイドラインを全面的に改定することとし,平成7年4月3日,その
改定原案を作成・公表し,原案について広く内外の意見を求めた結果,原案
の一部を修正し,10月30日に新ガイドラインを公表した。
第5 合併・株式所有等に関する事務処理基準の明確化等
| 1 |
合併・株式所有等に関する事務処理基準 |
|
| (1) |
事務処理基準の見直しの趣旨及び経緯 |
|
当委員会は,合併・営業譲受等(この節において以下「合併等」とい
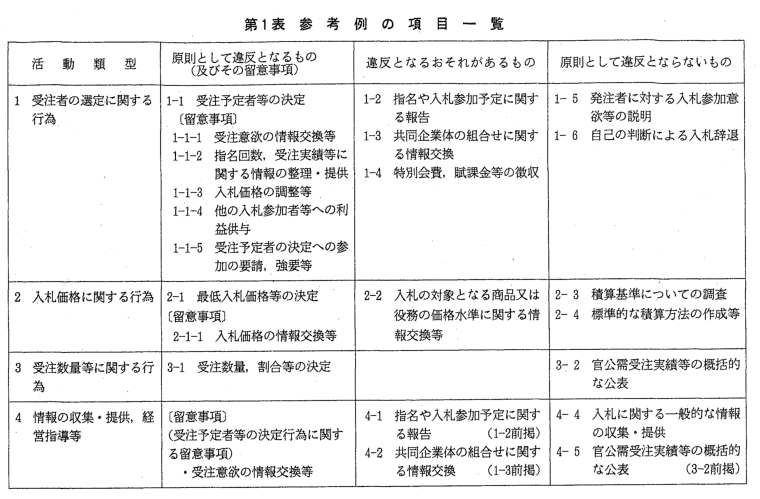
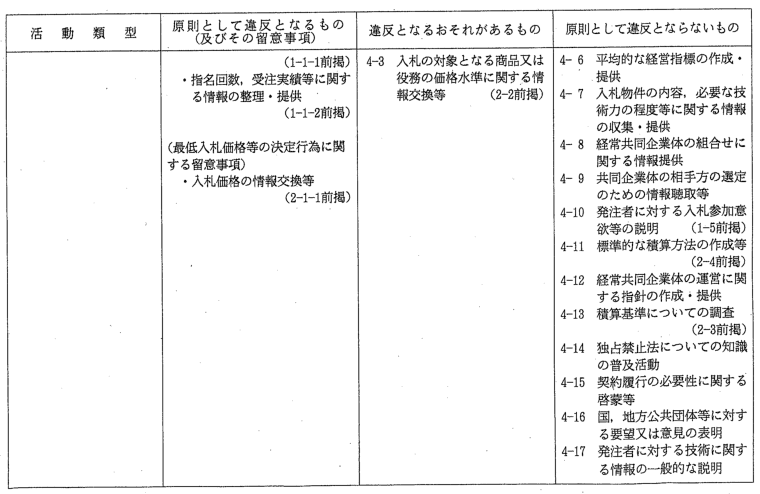
う。)及び株式所有の審査の適正かつ効率的な処理を図り,それらの行
為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか否か
を審査するに当たり重点的に審査する案件の選別基準及び審査するに当
たっての考慮事項を明らかにするため,昭和55年7月に「会社の合併等
の審査に関する事務処理基準」(以下「合併事務処理基準」という。),
昭和56年9月に「会社の株式所有の審査に関する事務処理基準」(以下
「株式事務処理基準」という。)を公表し,これらの基準に基づいて,
これまで各案件の審査を行ってきたところである。合併等の件数は,昭
和55年度の1,641件から平成5年度には,3,070件,株式所有報告書は,
昭和56年度の5,505件から,平成5年度には8,039件といずれも大幅に増
えており,合併等及び株式所有を行う場合の企業サイドの当委員会の判
断に関する予測可能性を高めるため,また,審査をより効率的に行うた
めに,事務処理基準を一層明確化することにより透明性の確保を図る観
点から,各事務処理基準の見直しを行い,平成6年8月18日,改定・公
表した。 |
| (2) |
事務処理基準見直しの概要 |
|
| ア |
合併事務処理基準について |
|
| (ア) |
「一定の取引分野」及び「競争の実質的制限」についての考え方
「一定の取引分野」及び「競争の実質的制限」について,判例,
これまでの審査における考え方等を踏まえて,その解釈を示した。 |
| (イ) |
加算対象となる会社の基準及び選別基準の性格・文言の明確化
| a |
加算対象となる会社の基準の明確化 |
|
加算対象となる「実質的に支配している会社」を,「発行済株
式総数の25%以上の株式を所有している会社」と明確にした。 |
| b |
選別基準の性格の明確化 |
|
選別基準について,いわゆる25%基準に該当する案件は禁止さ
れる等のこれまで指摘されていた誤解を防ぐため,「この基準に
該当することのみで直ちに当該合併が独占禁止法上問題とされる
ものではない」旨,選別基準の性格を明確化した。 |
| c |
選別基準の文言の明確化 |
|
選別基準のうち,以下の文言の明確化を行った。
| (a) |
選別基準の1として「当事会社のいずれかが属する市場にお
いて,当事会社のいずれか1社の市場占拠率又は当事会社の市
場占拠率の合計が,①25%以上である場合,②第1位であり,
かつ,15%以上である場合又は③第1位であり,かつ,第2位
若しくは第3位の会社の市場占拠率と比較して,その格差が大
きい場合」が掲げられているが,このうち「市場占拠率と比較
して,その格差が大きい場合」を,「市場占拠率の差が第1位
の会社の市場占拠率の4分の1以上である場合」に改め,明確
にした。 |
| (b) |
選別基準の3として「当事会社のいずれかが属する市場にお
ける競争者の数が相当程度少数の場合」が掲げられているが,
このうち「競争者が相当程度少数の場合」を「競争者が7以下
である場合」と改め,明確にした。 |
|
|
| (ウ) |
考慮事項の各項目についての考え方等 |
|
| a |
考慮事項の各項目について,審査を行うに当たっての位置付け
を明確にした。 |
| b |
考慮事項の各項目に示された事項の意味及び趣旨について詳細
に示した。 |
|
| (エ) |
考慮事項のうち「当該市場における競争の状況」の箇所における
「輸入の状況」の明示 |
|
経済の国際化に伴い,国内市場における競争に対する輸入の与え
る影響が大きくなっていることから,考慮事項として「輸入の状
況」を明示し,その考え方を示した。 |
| (オ) |
考慮事項のうち「経営状況」の箇所における,いわゆる「倒産寸
前会社(部門)」の明示 |
|
いわゆる「倒産寸前会社(部門)」については従来から考慮して
いるが,その記載が抽象的な表現であることから,今回の改定にお
いていわゆる「倒産寸前会社(部門)」についての考え方を示し
た。 |
| (カ) |
考慮事項のうち「総合的事業能力等」の箇所における「効率性」
の明示 |
|
効率性の改善が達成されるからといって合併による競争制限的効
果が相殺されるものではないが,審査に当たり,効率性を全く考慮
しないものではないため,今回の改定において「効率性」について
明示し,その考え方を示した。 |
| (キ) |
合併禁止期間の短縮についての取扱い |
|
独占禁止法第15条第3項において,届出受理の日から30日を経過
するまでは合併をしてはならないと定められているが,合併禁止期
間の短縮の申出があり,かつ,その案件が独占禁止法上問題がない
ことが明らかな場合であって,短縮の必要性について合理的な理由
があるときに,合併禁止期間の短縮を認める旨明記した。 |
| (ク) |
事前相談の明記 |
|
実務において従来から事前相談を受け付けているところである
が,これを周知し,効率的行政の推進に資する観点から,事前相談
を受け付ける旨明示した。 |
| (ケ) |
営業譲受等における「重要部分」についての考え方 |
|
営業譲受等における「重要部分」について,その解釈を示すとと
もに,譲渡会社の年間総売上高の5%の部分で裾切りを行うことと
し,これに当たらない案件については「重要部分」に該当しないも
のとして取り扱うこととした。しかし,事業規模が大きい会社につ
いては,年間総売上高の5%でもその額が大きくなり,絶対的規模
において重要部分と考えられることからその上限を1億円とした。 |
|
| イ |
株式事務処理基準について |
|
株式事務処理基準については,合併事務処理基準に付加した解釈・
考え方と同様のものを付加するとともに,合併事務処理基準において
形式審査案件の対象となる案件とほぼ同様の案件について,株式審査
においても形式審査案件とする旨 下記のとおり新たに基準を設定し
た。
| (ア) |
当事会社の総資産がいずれも100億円未満である場合の株式所有 |
| (イ) |
当事会社のうち,一方の会社の総資産が100億円以上であって,
かつ,他方の会社の総資産が10億円未満である場合の株式所有 |
| (ウ) |
当事会社のうち,一方の会社が他方の会社の設立時から当該会社
の発行済の株式の総数を所有する場合の株式所有
|
なお,本事務処理基準の見直しの内容は,従来の事務処理基準に,
これまでの審査における考え方を整理・集約して付加する形で示した
ものであり,本事務処理基準の見直しによって,当委員会のこれまで
の考え方を変更するものではない。 |
|
|
| 2 |
金融会社の株式保有の認可に関する事務処理基準 |
|
| (1) |
趣旨及び経緯 |
|
金融会社による国内の会社の株式の保有については,金融会社による
事業支配力の過度の集中を未然に防止し,公正かつ自由な競争を促進す
る観点から,独占禁止法第11条により,その発行済株式総数の5%
(保
険会社の場合は10%)を超えて保有することが禁止されている(同条第
1項)。
他方,金融会社は,事業の性格上又は債権保全の一環として,このよ
うな制限を超えて株式を保有する必要があり,かつ,事業支配力の過度
の集中をもたらすおそれのないような場合も考えられることから,独占
禁止法第11条第1項第1号から第3号に規定されている特定の場合及び
同項ただし書に基づきあらかじめ当委員会の認可を受けた場合は,例外
的に5%(保険会社の場合は10%)を超えて株式を保有できることとさ
れている。
また,独占禁止法第11条第1項第1号又は第2号に該当する株式保有
については,1年を超えて保有しようとするときは,同条第2項に基づ
きあらかじめ当委員会の認可を受けなければならない。
こうした独占禁止法第11条の規定に基づく認可について,当委員会
は,これまで個別の申請ごとにその具体的内容を見て,独占禁止法の趣
旨・目的に照らして問題かないと特に認められるものについて認可を
行ってきたところであるが,そうした認可実績を踏まえ,当委員会の認
可に当たっての考え方について明確化を図るために,「金融会社の株式
保有の認可に関する事務処理基準」を作成し,平成6年6月20日,公表
した。
なお,本事務処理基準の内容は,これまでの認可における考え方を整
理・集約したものであり,本事務処理基準の作成によって,当委員会の
認可に関する従来の考え方を変更するものではない。
また,本事務処理基準は,金融会社を取り巻く現行の法制度,経済情
勢等を勘案して作成されたものである。したがって,今後,そうした状
況に変化が生じるようであれば,当委員会としては,適宜,事務処理基
準の内容について見直しを行い,必要な修正を加えていくこととしてい
る。 |
| (2) |
概 要 |
|
本事務処理基準は,「第1 法第11条第1項ただし書の規定に基づく
認可」及び「第2 法第11条第2項の規定に基づく認可」により構成さ
れている。
「第1 法第11条第1項ただし書の規定に基づく認可」については,
認可を申請する金融会社により株式を保有される会社についての3つの
鶏型(「(1)申請会社が自社の固有の業務に従属する業務を行わせる目的
で株式を保有する会社である場合」,「(2)国内の申請会社が現に営んでい
る金融業以外の金融業に参入する目的で株式を保有する会社である場
合」及び「(3)外国の申請会社が当該設立準拠国において現に営んでいる
金融業を我が国において営む目的で株式を保有する会社である場合」)
について,それぞれの認可要件を明記している。また,上記の3つの類
型に該当しない認可申請については,「個別に認可の可否を検討する」
こととし,その際の審査ポイントを明記している。
「第2 法第11条第2項の規定に基づく認可」については,独占禁止
法第11条に規定された第2項認可の対象となる株式保有を改めて整理し
た上,当該認可の可否の判断に当たっての審査ポイントを明記するとと
もに,第2項認可は「原則として1年以内の期限を付して認可する」こ
とを明記している。 |
|
| 3 |
ベンチャー・キャピタルに対する独占禁止法第9条の規定の運用につい
ての考え方 |
|
| (1) |
趣旨及び経緯 |
|
独占禁止法第9条は,事業支配力の過度の集中を防止する観点から持
株会社の設立等を禁止している。持株会社は,「株式を所有することに
より国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社」と
定義されており(独占禁止法第9条第3項),ベンチャー・キャピタル
は,通常,ベンチャー・ビジネスの株式の取得・所有を行っていること
から,独占禁止法第9条の規定の運用においては,ベンチャー・キャピ
タルが持株会社に該当するかどうかが問題となるものである。
当委員会は,ベンチャー・キャピタルについて独占禁止法第9条の規
定に抵触する可能性が少ない場合の要件等を示すため,昭和47年11月,
「ベンチャー・キャピタルに対する独占禁止法上の取扱について」を公
表し,法運用を行ってきたところであるが,ベンチャー・キャピタルの
実態が当時想定したものとは異なるものとなっていること等から,「ベ
ンチャー・キャピタルに対する独占禁止法第9条の規定の運用について
の考え方」(以下「本考え方」という。)を作成し,平成6年8月23日,
公表した。
なお,本考え方は,一般的な判断基準を示したものであり,個別事案
については,本考え方に基づき,それぞれのベンチャー・キャピタルの
事業活動,株式所有等の実態に即して,持株会社該当性の判断を行うも
のである。
また,本考え方の策定に伴い,「ベンチャー・キャピタルに対する独
占禁止法上の取扱について」(昭和47年11月9日公表)は,廃止され
た。 |
| (2) |
概 要 |
|
ベンチャー・キャピタルが持株会社に該当するかどうかの判断に当
たっては,まずベンチャー・キャピタルが株式所有により事業活動を支
配しているベンチャー・ビジネスその他の国内会社(以下「被支配会
社」という。)を有しているかどうかを判断することとなるが,被支配
会社を有していないと認められる場合には,当該ベンチャー・キャピタ
ルは持株会社には該当しない。被支配会社を有していると認められた場
合には,「株式を所有することにより国内の会社の事業活動を支配する
ことを主たる事業」としているかどうかをみて持株会社に該当するかど
うかを判断することとなる。本考え方は,ベンチャー・キャピタルが
被支配会社を有しているかどうかの判断基準を示すとともに,ベン
チャー・キャピタルが独占禁止法第9条に定める持株会社に該当する会
社であるかどうかの判断基準について,持株会社に該当する場合,該当
するおそれのある場合及び該当しない場合に分類して,具体的な判断指
標を示すとともに,それらの指標においてどの程度の状況であれば持株
会社に該当するか否かを具体的に示したものである。
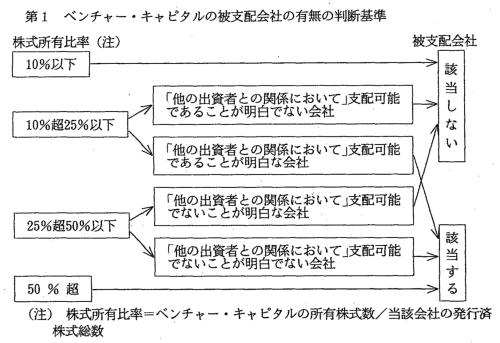
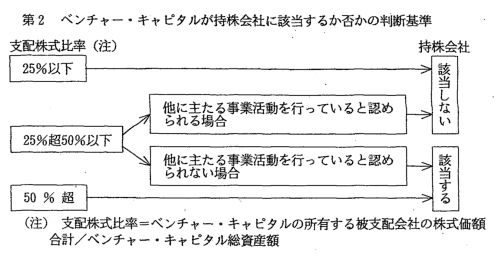
|
|