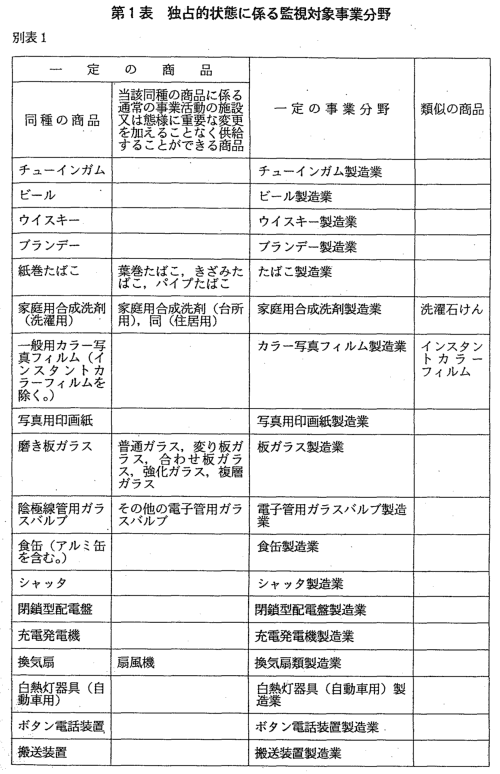
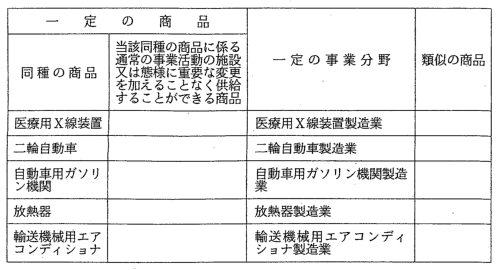
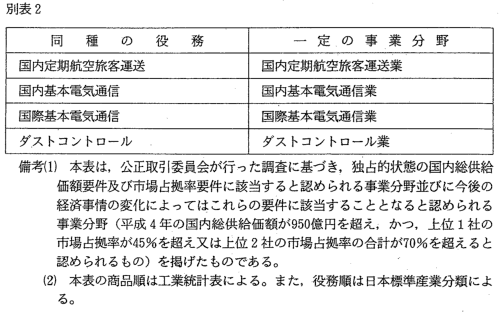
第3 独占的状態調査
独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めている
が,当委員会は,独占禁止法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定
のうち,事業分野に関する考え方について,ガイドラインを公表しており,
その別表には,独占的状態の国内総供給価額要件及び市場占拠率要件(国内
総供給価額が1,000億円超でかつ,上位1社の市場占拠率が50%超又は上位
2社の市場占拠率の合計が75%超)に該当すると認められる事業分野並びに
今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認め
られる事業分野が掲げられている。
平成7年度においては,国内総供給価額及び市場占拠率に関する平成4年
の調査結果を踏まえガイドライン別表の改定を行い,平成7年7月1日から
実施した。
この結果,新たにブランデー製造業,換気扇類製造業,医療用X線装置製
造業及びダストコントロール業の4事業分野を別表に掲載し,インスタント
コーヒー製造業,ビデオディスクプレーヤ製造業,磁気ヘッド製造業及びク
ラッチ装置製造業の4事業分野を別表から削除することとなった。改定後の
別表掲載事業分野数は,商品に係る23事業分野及び役務に係る4事業分野で
ある(第1表)。
これらの別表掲載業種については,公表資料及び通常業務で得られた資料
の整理・分析を行うとともに,特に集中度の高い業種については,生産,販
売,価格,製造原価,技術革新等の動向,分野別利益率等について,関係企
業から資料の収集,事情聴取等を行うことにより,独占禁止法第2条第7項
第2号(新規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,過大な利益
率,過大な販売管理費の支出)の各要件に則し,企業の動向の監視に努め
た。
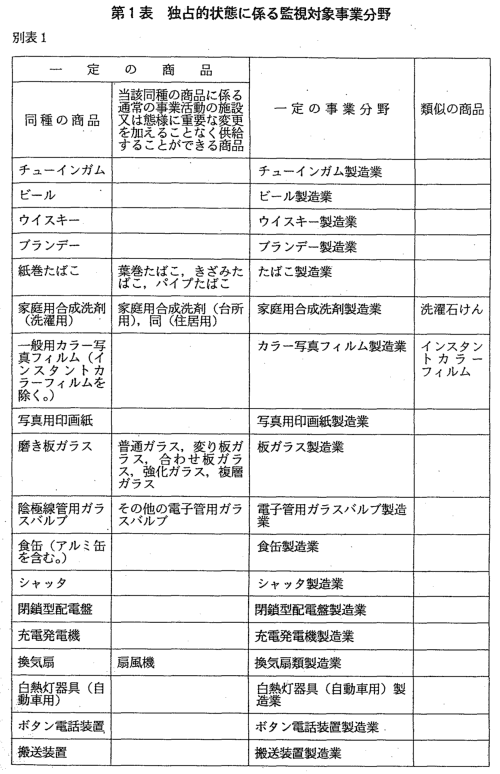 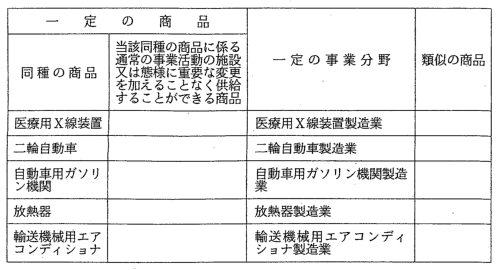 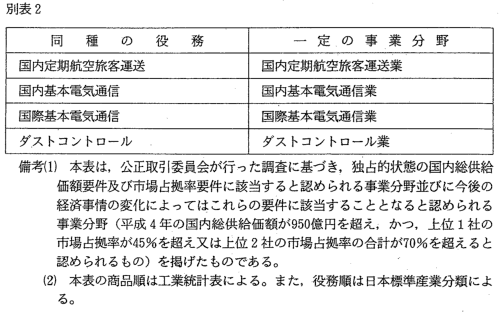
|
第4 一般集中度調査
| 1 | 概説
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 調査の概要
|
第5 生産・出荷集中度調査
| 1 | 概説
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 調査の概要
|
第6 ベンチャー・キャピタルの実態調査
近年,我が国においても中小企業の活性化,なかでもエレクトロニクス,
バイオテクノロジー,新材料技術などの研究開発型ベンチャー・ビジネス育
成の必要性が高まっているといわれている。今後,ベンチャー・ビジネスの
店頭登録基準等の緩和等の制度の改正の進展に伴い,ベンチャー・ビジネス
の育成を図る上でベンチャー・キャピタルの果たす役割は一層増大していく
ものと考えられる。
当委員会は,我が国におけるベンチャー・キャピタルの実態を把握すると
ともに,平成6年8月23日に「ベンチャー・キャピタルに対する独占禁止法
第9条の規定の運用についての考え方」(以下「新基準」という。)を公表し
てから1年が経過したため新基準の評価,ベンチャー・キャピタルの運営上
の支障の有無等について明らかにすることを目的として調査を実施し,その
結果を取りまとめ,平成7年12月に公表した(調査期間平成7年8月25日~
平成7年10月31日)。
1 ベンチャー・キャピタルの実態等について
| (1) | ベンチャー・キャピタル数
|
|||||||||||||||
| (2) | 資本金
|
|||||||||||||||
| (3) | 総資産
|
|||||||||||||||
| (4) | 所有株式額
|
|||||||||||||||
| (5) | 投融資
|
|||||||||||||||
| (6) | 投資事業組合
|
2 新基準に対する評価等について
| (1) | 新基準についての全般的な印象
|
|||||
| (2) | ベンチャー・キャピタルの運営について
|
3 まとめ
| (1) | ベンチャー・キャピタルの支援を受けてベンチャー・ビジネスが我が 国市場で成長することになれば,①新しい市場を創造する原動力となる こと②既存市場に新製品又は新技術による製品をもって新規参入をする ことにより,市場における競争を活発化させることにつながることか ら,競争政策上も積極的に評価できるものである。 |
| (2) | 本調査においては,現在,独占禁止法第9条が持株会社の設立等を禁 止していることがベンチャー・キャピタルの活動の障害となっている実 態は認められなかった。 |
| (3) | しかし,今後,我が国市場の成熟化に伴い,市場の活性化に向けて, ベンチャー・キャピタルによる①初期段階や研究開発型のベンチャー・ ビジネスへの投資の活発化,②ベンチャー・ビジネスへの技術援助・経 営指導の活発化が求められているが,この過程において,ベンチャー・ キャピタルによるベンチャー・ビジネスの株式取得が進むことによっ て,持株会社規制がベンチャー・キャピタル及びベンチャー・ビジネス の発展の障害になる可能性があり,この観点からは,今後,我が国にお けるベンチャー・キャピタルの発展を図るため環境面の整備を行う必要 があると考えられる。 |