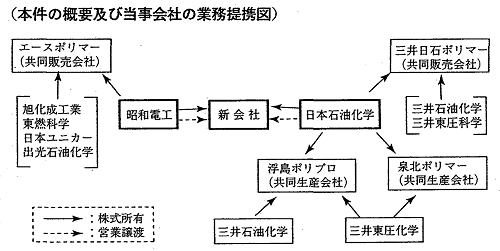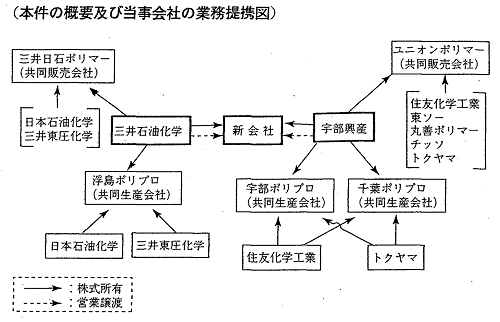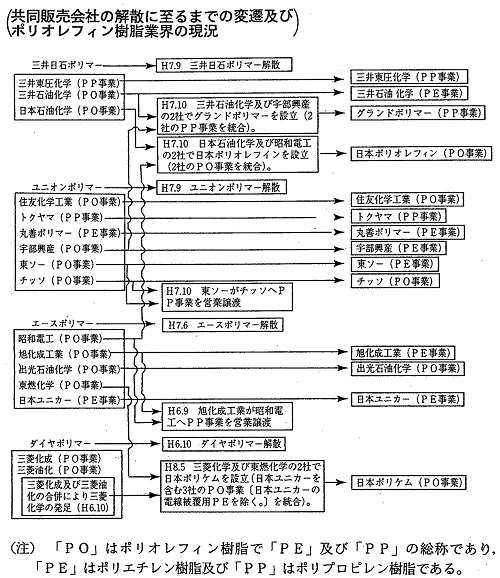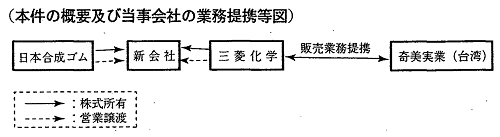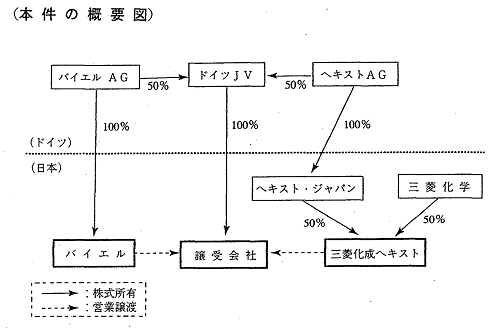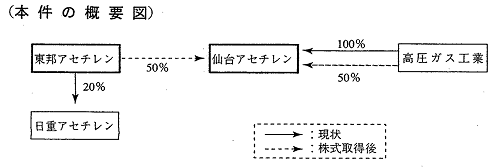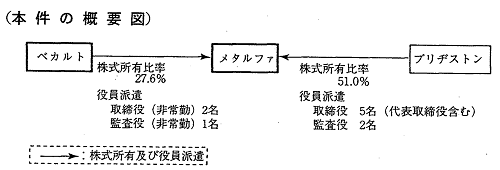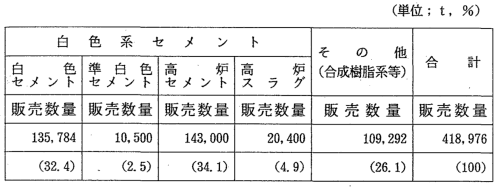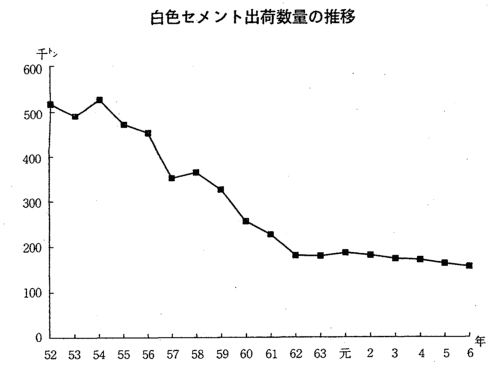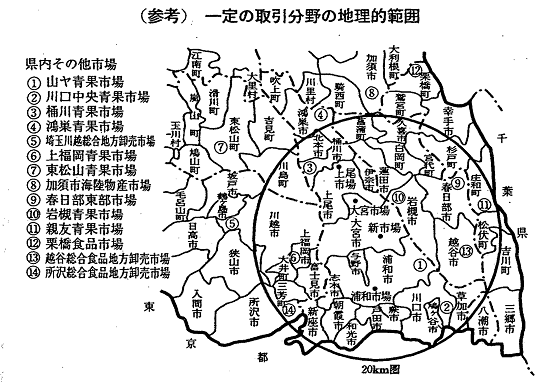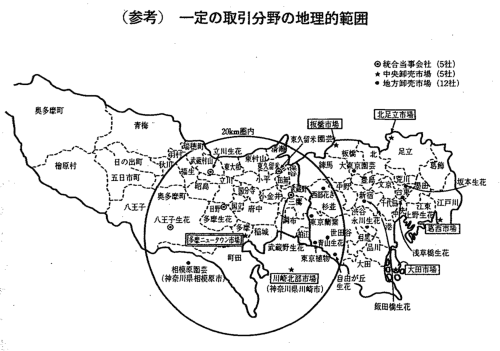第5 主要な事例
本年度の合併・営業譲受け等及び株式保有等の主要な事例は,次のとおり
である。
1 昭和電工㈱及び日本石油化学㈱によるポリオレフィン樹脂事業の統合
(平成7年8月営業譲受け届出受理,10月営業譲受け)
| (1) |
概要
本件は,昭和電工㈱(以下「昭和電工」という。)と日本石油化学㈱
(以下「日本石油化学」という。)が,経営効率化を通じた国際競争力
の強化等を目的として,ポリオレフィン樹脂事業を統合(両社が共同出
資により新会社(日本ポリオレフィン㈱)を設立するとともに,それぞ
れ新会社にポリオレフィン樹脂事業を譲渡)しようとするものである。 |
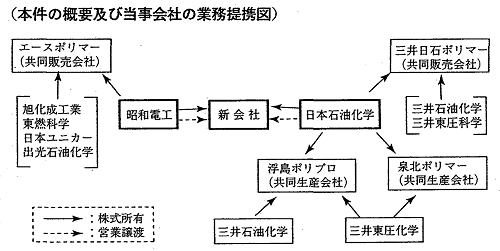 |
| (2) |
一定の取引分野
汎用合成樹脂の一つであるポリオレフィン樹脂は,低密度ポリエチレ
ン樹脂,高密度ポリエチレン樹脂及びポリプロピレン樹脂から構成され
るが, |
| a |
低密度ポリエチレン樹脂は,柔軟性,成形加工性,電気絶縁性等の
特性があり,主にフィルム(食品包装,ゴミ袋等),ラミネート(牛
乳パック,菓子袋等),電線被覆材等に使用されている, |
| b |
高密度ポリエチレン樹脂は,硬質性(ポリエチレン樹脂の中で),
耐熱性,耐水性等の特性があり,主にフィルム,硬質性を活かした容
器(洗剤容器,シャンプー容器,灯油缶等)等に使用されている, |
| c |
ポリプロピレン樹脂は,硬質性,機械的強度性,耐熱性等の特性が
あり,主に自動車用部品,射出成形(コンテナ等),フィルム,押出
成形(文具,バンド,ロープ等)等に使用されている |
ことから,一部用途について代替関係がみられるものの,それぞれ,上
記の特性から主たる用途を異にしていること,その製法又は原料に一定
の差異がみられることから,各品目ごとに「一定の取引分野」が成立す
るものと判断した。 |
|
| (3) |
問題点及び考慮事項
| ① |
問題点
本件行為により,当事会社の高密度ポリエチレン樹脂の販売シェア
が24.2%かつ第1位となる。
また,当事会社は,それぞれ,業務提携図のとおり,他社とポリオ
レフィン樹脂の共同販売の事業提携を行っており,これらの業務提携
関係にある他社の事業能力を考慮すると,本件行為による新会社のポ
リオレフィン樹脂3樹脂のシェアは更に高くなり,また,日本石油化
学は,昭和電工以外の会社とポリプロピレン樹脂の共同生産の事業提
携を行っており,これら当事会社以外の会社の生産能力を考慮する
と,本件行為による新会社のポリプロピレン樹脂の生産能力シェアは
29.8%となる。 |
|
| ② |
考慮事項
| ア |
全国における競争状況等
新会社における高密度ポリエチレン樹脂の販売シェアは24.2%か
つ第1位となるが,10%を超えるシェアを有する有力な競争業者が
複数存在している。
また,高密度ポリエチレン樹脂については,特に東南アジア地区
から低価格等を背景とした輸入が増加している。 |
|
| イ |
共同販売事業の状況
当事会社が参加している共同販売の事業提携のための共同販売会
社であるエースポリマー㈱は平成7年6月30日,三井日石ポリマー
㈱は同年9月30日にそれぞれ解散が予定されている。 |
|
|
| ③ |
当委員会の判断
本件について,当委員会は,当事会社に対し,当事会社以外の会社
と行っているポリプロピレン樹脂の共同生産の事業提携を考慮する
と,新会社の生産能力シェアが高くなることから,ポリプロピレン樹
脂の製造・販売分野における競争を実質的に制限することとなるおそ
れがある旨指摘した。 |
|
| ④ |
当事会社の対応
上記指摘に対し,当事会社において,ポリプロピレン樹脂の共同生
産会社に対する出資について,今後出資を取りやめる等の措置を採る
旨の申出があった。 |
|
|
| (4) |
本件の処理
上記の当事会社の措置等を総合的に勘案すると,本件行為によって,
直ちに一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは
いえないと判断した。 |
|
2 三井石油化学工業㈱及び宇部興産㈱によるポリプロピレン樹脂事業の統
合(平成7年8月営業譲受け届出受理,10月営業譲受け)
| (1) |
概要
本件は,三井石油化学工業㈱(以下「三井石油化学」という。)と宇
部興産㈱(以下「宇部興産」という。)が,国際競争力の強化等を目的
として,ポリプロピレン樹脂事業を統合(両社が共同出資により新会社
(グランドポリマー㈱)を設立するとともに,それぞれ新会社にポリプ
ロピレン樹脂事業を譲渡)しようとするものである。 |
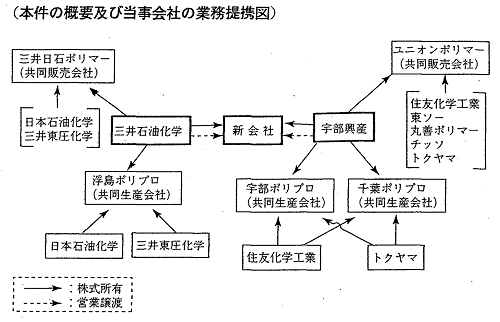
|
| (2) |
一定の取引分野
汎用合成樹脂の一つであるポリプロピレン樹脂は,硬質性,機械的強
度性,耐熱性等の特性があり,主に自動車用部品,射出成形(コンテナ
等),フィルム,押出成形(文具,バンド,ロープ等)等に使用されて
おり,一部用途については,他の樹脂(低密度ポリエチレン樹脂,高密
度ポリエチレン樹脂等)と代替関係がみられるものの,これら樹脂とポ
リプロピレン樹脂は上記の特性から主たる用途を異にしていること,そ
の製法又は原料に一定の差異がみられることから,ポリプロピレン樹脂
の製造・販売分野に「一定の取引分野」が成立するものと判断した。 |
|
| (3) |
問題点及び考慮事項
| ① |
問題点
本件行為により,当事会社のポリプロピレン樹脂の販売シェアが
17.2%かつ第2位となる。
また,当事会社は,それぞれ,他社とポリプロピレン樹脂の共同販
売の事業提携を行っており,これらの業務提携関係にある他社の事業
能力を考慮すると,本件行為による新会社のポリプロピレン樹脂の
シェアは更に高くなり,また,当事会社は,他社とポリプロピレン樹
脂の共同生産の事業提携を行っており,これら他社の生産能力を考慮
すると,本件行為による新会社のポリプロピレン樹脂の生産能力シェ
アは43.4%となる。 |
|
| ② |
考慮事項
| ア |
全国における競争状況等
新会社におけるポリプロピレン樹脂の販売シェアは17.2%かつ第
2位となるが,10%を超えるシェアを有する有力な競争業者が複数
存在している。 |
|
| イ |
共同販売事業の状況
当事会社が参加している共同販売の事業提携のための共同販売会
社である三井日石ポリマー㈱及びユニオンポリマー㈱は,両社とも
平成7年9月30日に解散が予定されている。 |
|
|
| ③ |
当委員会の判断
本件について,当委員会は,当事会社に対し,当事会社以外の会社
と行っているポリプロピレン樹脂の共同生産の事業提携を考慮する
と,新会社の生産能力シェアが高くなることから,ポリプロピレン樹
脂の製造・販売分野における競争を実質的に制限することとなるおそ
れがある旨指摘した。 |
|
| ④ |
当事会社の対応
上記指摘に対し,当事会社において,ポリプロピレン樹脂の共同生
産会社に対する出資について,今後出資を取りやめる等の措置を採る
旨の申出があった。 |
|
|
| (4) |
本件の処理
上記の当事会社の措置等を総合的に勘案すると,本件行為によって,
直ちに一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは
いえないと判断した。
<参考> ポリオレフィン樹脂における共同販売事業の現況
ポリオレフィン樹脂については,昭和58年から,低密度ポリ
エチレン樹脂,高密度ポリエチレン樹脂及びポリプロピレン樹
脂のうち汎用品を対象として,国内16社を四つのグループ(ダ
イヤポリマー㈱,エースポリマー㈱,三井日石ポリマー㈱及び |
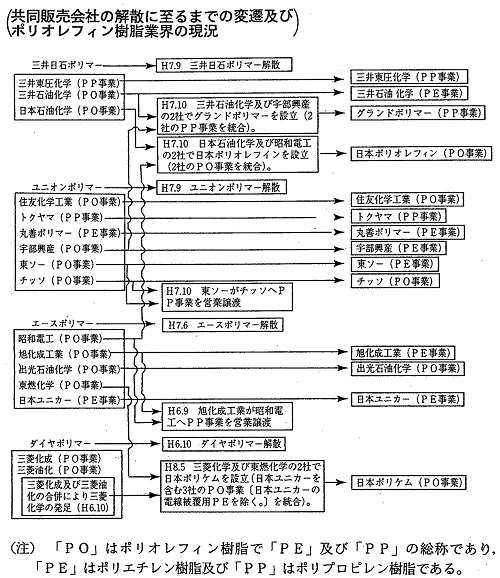
ユニオンポリマー㈱の4共同販売会社)に分けた共同販売事業
が実施されてきた。
しかしながら,ダイヤポリマー㈱については,平成6年10月
の旧三菱化成㈱と旧三菱油化㈱の合併(三菱化学㈱に商号変
更)に伴い平成6年10月に解散し,また,これに続いて,平成
7年10月の昭和電工㈱と日本石油化学㈱のポリオレフィン樹脂
の事業統合(日本ポリオレフィン㈱の設立),同日の三井石油
化学工業㈱と宇部興産㈱のポリプロピレン樹脂の事業統合(グ
ランドポリマー㈱の設立)等に伴い,エースポリマー㈱は同年
6月に,三井日石ポリマー㈱及びユニオンポリマー㈱は同年9
月にそれぞれ解散し,同業界の共同販売会社はすべて解散して
いる。 |
|
3 日本合成ゴム㈱及び三菱化学㈱によるABS樹脂等事業の統合
| (1) |
概要
本件は,日本合成ゴム㈱(以下「日本合成ゴム」という。)と三菱化
学㈱(以下「三菱化学」という。)が,国際競争力の強化等を目的とし
て,ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂)等の
事業を統合(両社が共同出資により新会社を設立するとともに,両社の
ABS樹脂及びAS樹脂〔アクリロニトリル・スチレン樹脂〕並びに日
本合成ゴムのAES樹脂〔アクリロニトリル・エチレンプロピレンラ
バー・スチレン樹脂〕及びMBS樹脂〔メチルメタアクリレート・ブタ
ジエン・スチレン樹脂〕〔以下これら4樹脂を総称して「ABS樹脂
等」という。〕の各事業を新会社に譲渡)しようとするものである。
なお,三菱化学は,ABS樹脂等において世界第1位の生産能力を有
する奇美実業(台湾)とその我が国における販売に関する業務提携を
行っている。 |
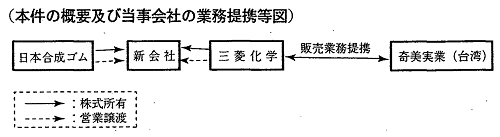 |
| (2) |
一定の取引分野
ABS樹脂等は,スチレンモノマーを主原料に,アクリロニトリル,
ブタジエン,エチレンプロピレンラバー,メチルメタアクリレートの副
原料を用いて製造され,それぞれの樹脂としての特性を異にしており, |
| a |
ABS樹脂は,ポリスチレン樹脂(スチレンモノマーの重合品)の
特性(成形性,透明性)の他に,耐薬品性,耐衝撃性,耐候性等の特
性を有し,主に自動車用部品(インパネ等),家庭用電気機器(掃除
機,エアコン等),一般事務機器(パソコン,電話機等),ゲーム機等
に使用されている, |
| b |
AS樹脂は,ポリスチレン樹脂の特性の他に,耐薬品性等の特性を
有し,主に家庭用電気機器(エアコンのファン等),雑貨(ライ
ター,文房具,化粧品ケース等),自動車用部品(インパネの骨材
等)等に使用されている, |
| c |
AES樹脂は,ABS樹脂の特性のうちの耐候性を改良した樹脂で
あり,主に自動車用部品(フロントグリル,ドアミラー等),家庭用
電気機器(エアコンの室外機等),レジャー用品,看板等に使用され
ている, |
| d |
MBS樹脂は,樹脂単体で使用される上記3樹脂と異なり,主に塩
化ビニル樹脂の衝撃強度を改良するための改質剤として使用されてい
る |
ことから,一部用途について代替関係がみられるものの,それぞれ,上
記の特性から主たる用途を異にしていること,その製法又は原料に一定
の差異がみられることから,各品目ごとに「一定の取引分野」が成立す
るものと判断した。 |
|
| (3) |
問題点及び考慮事項
| ① |
問題点
本件行為により,当事会社の販売シェアが,ABS樹脂については
25.5%かつ第1位,AS樹脂については25.2%かつ第2位となる。 |
|
| ② |
考慮事項
新会社における販売シェアが,ABS樹脂については25.5%かつ第
1位,AS樹脂については25.2%かつ第2位となるが,ABS樹脂に
ついては10%を超えるシェアを有する有力な競争業者が複数存在して
おり,また,AS樹脂については第1位の有力な競争業者(シェア約
30%)及び10%を超えるシェアを有する有力な競争業者が複数存在し
ている。
また,ABS樹脂等の用途のうち,他の樹脂(ハイインパクトポリ
スチレン樹脂等)に代替されているものもあり,これらを考慮する
と,当事会社のシェアは低下することとなる。 |
|
| ③ |
当委員会の判断
本件について,当委員会は,当事会社に対し,奇美実業との我が国
におけるABS樹脂等の販売に関する業務提携により,ABS樹脂等
の製造・販売分野における競争を実質的に制限することとなるおそれ
がある旨指摘した。 |
|
| ④ |
当事会社の対応
上記指摘に対し,三菱化学から,奇美実業との業務提携について
は,その解消を含めて検討すること等の措置を採る旨の申出があった。 |
|
|
| (4) |
本件の処理
上記の当事会社の措置等を総合的に勘案すると,本件行為によって,
直ちに一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは
いえないと判断した。 |
|
4 バイエル㈱及び三菱化成ヘキスト㈱の繊維用染料事業の統合(平成7年
5月営業譲受け届出受理,7月営業譲受け)
| (1) |
概要
世界的な総合化学メーカーであるバイエルAG(ドイツ法人)及びヘ
キストAG(ドイツ法人)がドイツにおいて繊維用染料事業に関する合
弁会社(以下「ドイツJV」という。)を設立し,平成7年7月1日を
目途に両社の全世界における繊維用染料の研究開発,生産及び販売事業
をドイツJVに統括させることを計画しているところ,日本国内におい
ても,同日を目途に,ドイツJVが100%出資するダイスター・ジャパ
ン㈱(以下「譲受会社」という。)が,①バイエルAGの100%出資子会
社であるバイエル㈱(以下「バイエル」という。)及び②ヘキストAG
の100%出資子会社であるへキスト・ジャパン㈱(以下「ヘキスト・
ジャパン」という。)及び三菱化学㈱との合弁会社である三菱化成へキ
スト㈱(以下「三菱化成へキスト」という。)から,繊維用染料事業に
関する営業を譲り受けようとするものである。 |
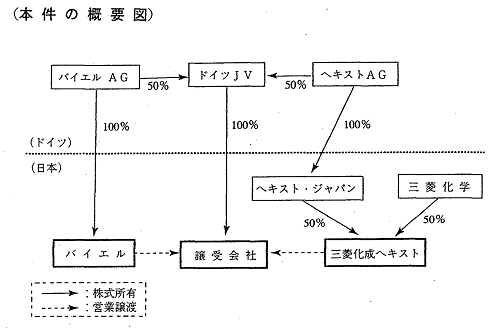 |
| (2) |
一定の取引分野
一般的に,染色しようとする繊維の種類によって用いられる繊維用染
料が異なり,さらに,特定の繊維(セルロース,ウール及びナイロン)
の染色においては,染色工程作業の難易度,染色後の堅牢度(染色後の
色落ちの程度),発色の鮮明さ等によって使用される染料が異なってい
るところから,繊維用染料は反応染料,分散染料等の11種に大別され
る。それぞれの繊維用染料間に代替関係がみられないことから,本件に
おいては,11種の繊維用染料ごとに「一定の取引分野」が成立するもの
と判断した。 |
|
| (3) |
問題点及び考慮事項
| ① |
問題点
本件行為により,譲受会社の販売シェアが,反応染料については
28%かつ第1位となり,分散染料については21%かつ第1位となる。 |
|
| ② |
考慮事項
| ア |
繊維用染料全体における競争の状況
繊維用染料は製造面の技術的障壁が低く,他の会社も特許権が消
滅した後は同種の商品(ゾロ品)を容易に製造することが可能であ
り,また,近年,特に中国,韓国,台湾,インドから特恵税率が適
用された低価格の繊維用染料が輸入されており,国内の価格形成に
相当な牽制力を有している。
また,現在,バイエル及び三菱化成へキストの繊維用染料部門の
収益は悪化している状況にある。 |
|
| イ |
繊維用染料における競争の状況
反応染料については,譲受会社の販売シェアは28%かつ第1位と
なるが,約20%のシェアを有する有力な競争業者及び約15%のシェ
アを有する有力な競争業者が存在している。また,本件行為に伴う
シェアの増加は小さく,かつ,最近では直接染料等の他のセルロー
ス繊維用染料の品質の向上に伴い,反応染料と他のセルロース繊維
用染料の間に代替関係がみられるようになっており,セルロース繊
維用染料としてみると譲受会社の販売シェアは,第2位となる。
分散染料については,譲受会社は販売シェアは21%かつ第1位と
なるが,10%を超えるシェアを有する有力な競争業者が存在してい
る。また,本件行為に伴うシェアの増加は小さく,かつ,バイエル及
び三菱化成へキストを合計した販売シェアは近年低下傾向にある。
|
|
|
|
| (4) |
本件の処理
上記の点を総合的に勘案すると,本件行為によって,直ちに一定の取
引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断
した。 |
|
5 東邦アセチレン㈱による仙台アセチレン㈱の株式取得
| (1) |
概要
本件は,高圧ガスの製造・販売業者である東邦アセチレン㈱(以下
「東邦アセチレン」という。)が,高圧ガスの製造・販売業者である高
圧ガス工業㈱(以下「高圧ガス工業」という。)の100%出資会社であ
り,高圧ガスの一種である溶解アセチレンの製造業者の仙台アセチレン
㈱(以下「仙台アセチレン」という。)の発行済株式総数の50%に相当
する株式を高圧ガス工業から取得しようというものである。 |
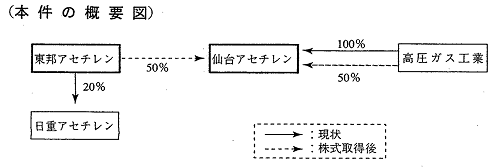 |
| (2) |
一定の取引分野
東北地区内で製造される溶解アセチレンは,そのほとんどが東北地区
内で使用されており,仙台アセチレンが製造する溶解アセチレンも東北
地区で販売されていることから,本件においては,東北地区における溶
解アセチレンの製造・販売分野に「一定の取引分野」が成立するものと
判断した。 |
|
| (3) |
問題点及び考慮事項
| ① |
問題点
| ア |
仙台アセチレン(シェア36.2%)と東邦アセチレン(シェア
25.3%)を合算した生産シェアは61.5%となる。 |
| イ |
高圧ガス工業(シェア6.8%)と東邦アセチレン(シェア
36.8%)を合算した販売シェアは43.6%となる。 |
| ウ |
東邦アセチレンは,日重アセチレン㈱(東邦アセチレン20%,日
本酸素10%等の共同出資会社。以下「日重アセチレン」という。)
にも出資しているため,高圧ガス工業・東邦アセチレン・日重アセ
チレン(シェア18.2%)の3社を合算した販売シェアは61.8%とな
る。 |
|
| ② |
考慮事項
| ア |
溶解アセチレンの製造分野において,仙台アセチレンと東邦アセ
チレンを合算した生産シェアは61.5%となるが,仙台アセチレン
は,高圧ガス工業,東邦アセチレン等から受託した数量の溶解アセ
チレンを製造するものであり,受託会社にすぎない。 |
| イ |
溶解アセチレンの販売分野において高圧ガス工業と東邦アセチレ
ンを合算した販売シェアは43.6%と高くなるが,高圧ガス工業と東
邦アセチレンは,仙台アセチレンに対し,それぞれ必要とする数量
の溶解アセチレンの製造を委託するものであり,両社は製品を引き
取って,それぞれ独自に販売するものである。 |
| ウ |
東北地区における溶解アセチレンの販売分野には,他に日本酸素
(シェア24%)という有力な競争業者が存在する。 |
|
| ③ |
当委員会の判断
本件について,当委員会は,当事会社に対し,東北地区内における
溶解アセチレンの販売について,東邦アセチレン・高圧ガス工業・日
重アセチレンの間に株式所有を通じた協調関係が生ずることになれ
ば,東北地区における溶解アセチレンの製造・販売分野における競争
を実質的に制限することとなるおそれがある旨の指摘を行った。 |
|
| ④ |
当事会社の対応
| ① |
当事会社は,仙台アセチレンにおける溶解アセチレンの製造に直
接必要な範囲を超えて情報交換をしないこと, |
| ② |
当事会社は,仙台アセチレンから購入した溶解アセチレンを独自
に販売することとし,販売先,販売数量,販売価格等に係る協調的
行動をとらないこと, |
| ③ |
東邦アセチレンは,日重アセチレンの株式を第三者に処分するこ
ととの措置を採る旨の申出があった。 |
|
|
| (4) |
本件の処理
上記の当事会社の措置等を総合的に勘案すると,本件行為によって,
直ちに一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは
いえないと判断した。 |
|
6 N.V.ベカルトS.A.によるブリヂストンメタルファ㈱の役員兼任
| (1) |
概要
| ① |
欧州最大のタイヤ用スチールコードメーカーであるN.V.ベカル
トS.A.(以下「ベカルト」という。ベルギー法人。)は,タイヤ
メーカーである㈱ブリヂストン(以下「ブリヂストン」という。)と
の合弁会社であり,タイヤ用スチールコードメーカーであるブリヂス
トンメタルファ㈱(以下「メタルファ」という。)の発行済株式を
27.6%所有し,かつ,その役員を兼任している。 |
| ② |
ベカルトとブリヂストンの間で締結されていた合弁契約は平成8年
3月26日に終了した。合弁終了契約により,現在,ベカルトはタイヤ
用スチールコードの日本における市場に進出することが可能であり,
また,ベカルトはメタルファの株式を10%以上所有している間は役員
兼任関係を継続することとしている。 |
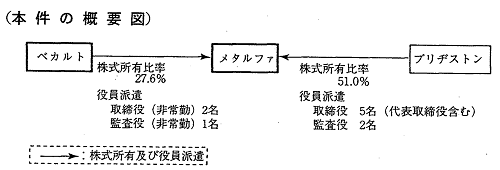 |
| (2) |
一定の取引分野
タイヤの補強材であるタイヤコードとして現在主に使用されているも
のは,ナイロンコード,ポリエステルコード及びスチールコードであ
る。このうち,ラジアルタイヤの主な補強材として使用されているのが
スチールコードであり,タイヤコードの全消費量に占めるスチールコー
ドの割合は約69%と高く,タイヤのラジアル化率の増加に伴い今後とも
タイヤコードの消費量に占めるスチールコードの割合は増加するものと
思われる。ナイロンコード及びポリエステルコードは,スチールコード
と部分的に代替関係がみられるものの,スチールコードの特性から主た
る用途を異にしていることもあり,本件においては,スチールコードの
製造・販売分野に「一定の取引分野」が成立するものと判断した。 |
|
| (3) |
問題点等
| ① |
問題点
| ア |
ベカルトとブリヂストンの間で締結している合弁終了契約によれ
ば,ベカルトがメタルファの株式を10%以上所有している間は,ベ
カルトはメタルファに役員を派遣することとしており,ベカルトと
メタルファとの間には株式所有及び役員兼任により結合関係が生じ
ている。 |
| イ |
現在,ベカルトは国内においてスチールコードを販売していない
ことから,メタルファとベカルトは競合関係にない。 |
| ウ |
しかし,合弁契約終了から2年経過した後(平成8年3月27日以
降)は,ベカルトは日本市場においてスチールコードを販売するこ
とが可能であるため,両社は潜在的な競争関係にある。 |
|
| ② |
当委員会の判断
本件について,当委員会は,当事会社に対し,ベカルトが国内のス
チールコード市場に参入後どのくらいのシェアを有することとなるか
は現段階では不明であるが,世界において有力なスチールコードメー
カーであり,日本においても有力な競争業者となり得るベカルトと,
国内のスチールコード市場において販売シェア46.6%で第1位のメタ
ルファの間に株式所有及び役員兼任による結合関係がみられることに
より,スチールコードの製造・販売分野における競争を実質的に制限
することとなるおそれがある旨の指摘を行った。 |
|
| ③ |
当事会社の対応
| 上記指摘に対し,当事会社から,次のとおりの申出があった。 |
| ア |
メタルファの株式所有比率が10%未満となるよう可及的速やかに
処分すべく最善の努力をする。 |
| イ |
株式を10%未満となるよう処分するまでの間,
| a |
ベカルトのスチール・コード部門又はワイヤー・コード部門の
いずれにも属していない者を役員として派遣する, |
| b |
これらの役員は,メタルファとの間で市場情報を共有したり,
メタルファから他の競争業者より有利に競争できるような情報を
入手したり,また,メタルファからスチール・コード又はワイ
ヤー・コードに関する販売先,技術,費用,価格及びマーケティ
ングに関する一切の情報を入手しない。 |
|
|
|
| (4) |
本件の処理
上記の当事会社の措置等を総合的に勘案すると,本件行為によって,
直ちに一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは
いえないと判断した。 |
|
7 秩父小野田(株)及び日本セメント㈱による白色セメントの共同生産会社の
設立(平成8年2月営業譲受け届出受理,4月営業譲受け)
| (1) |
概要
本件は,秩父小野田㈱(以下「秩父小野田」という。)と日本セメン
ト㈱(以下「日本セメント」という。)が折半出資により設立を予定し
ている新会社に対し,両社が行っている事業のうち,需要が減退してい
る白色ポルトランドセメント(以下「白色セメント」という。)の製造
に係る営業を譲渡しようとするものであり,本件行為後,白色セメント
の製造メーカーは新会社1社となり,その製造シェアは白色セメントで
は100%,準白色セメント,高炉セメント及び高炉スラグを含めた白色
系セメント分野では43.8%となる。 |
|
| (2) |
一定の取引分野
白色セメントは,最終製品として消費者に供給されるものではなく,
加工業者に原料用として販売されており,白色セメントを使用する商品
には,代替品として準白色セメント,高炉セメントの一部及び高炉スラ
グの一部も使用されていることから,本件においては,これらを含めた
白色系セメントの販売分野に「一定の取引分野」が成立するものと判断
した。 |
|
| (3) |
問題点及び考慮事項
| ① |
問題点
本件行為により,白色系セメント分野における販売シェアが,数量
では43.8%,金額では70.
0%となる。 |
|
| ② |
考慮事項
| ア |
部分的な競争関係にある合成樹脂系材料等を含めてみれば,下表
のとおり,秩父小野田の白色セメントの数量シェアは約18.0%,日
本セメントのシェアは約14.4%であり,その合算シェアは32.4%と
なる。 |
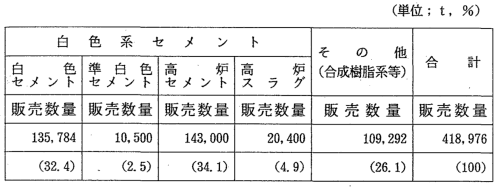
| イ |
白色セメントは,もともと製造メーカーが3社(昭和62年までは
小野田セメント,日本セメント及び秩父セメント)と少なく,しか
も,昭和62年以降は,秩父セメントが小野田セメントへ全量製造委
託する形で製造部門から撤退したことにより2社(販売は3社)と
なり,その後,平成6年10月1日の小野田セメントと秩父セメント
の合併により,現在は製造・販売メーカーとも2社となっている。
|
| ウ
| 製造メーカーは新会社1社となるものの,販売は両社がそれぞれ |
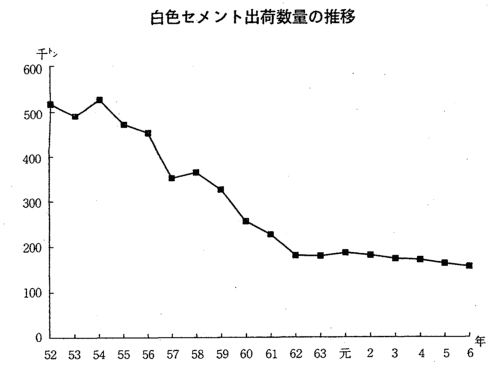
|
独立して行うものである。 |
| エ
| 白色セメントは,上図のとおり,年々需要が減退しており,この
傾向は今後も継続すると予想される。
|
| オ
| 白色セメントの製造は,原料調達も容易であり,既存設備を改造
(改造費用5億円~10億円)すれば容易に新規参入できる。
|
|
|
| (4)
| 本件の処理
上記の点を総合的に勘案すると,本件行為によって,直ちに一定の取
引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断
した。
|
|
8 (株)三菱銀行と㈱東京銀行との合(平成8年1月合併届出受理,4月合併)
| (1)
| 概要
本件は,㈱三菱銀行(以下「三菱銀行」という。)と㈱東京銀行(以
下「東京銀行」という。)が国内外の拠点網の充実を通じた国際競争力
の強化等を目的として,合併しようとするものである。
|
|
| (2)
| 一定の取引分野
本件は,業法上は外国為替銀行と普通銀行という異業態の銀行間の合
併であるが,合併後の存続銀行は普通銀行であり,両行は,相応の資本
力をもって広域の店舗展開により銀行業務を営むいわゆる都市銀行であ
ることから,都市銀行間の主として全国ベースでの競争に及ぼす影響を
検討した。
なお,他の業態に属する銀行との関係で,都市銀行を一定の取引分野
と認定した理由は,以下のとおりである。 |
| ア
| 長期信用銀行及び信託銀行
| (ア)
| 長期信用銀行及び信託銀行は,預金の受入れが制限されているこ
と。
|
| (イ)
| 長期信用銀行及び信託銀行は,債券発行,貸付信託の取扱い等都
市銀行にはない資金調達手段が認められている反面,店舗設置の面
で制約を受けており,その結果,個人客との取引基盤が都市銀行と
は異なること。
|
|
| イ
| 地方銀行及び第二地方銀行
都市銀行と地方銀行及び第二地方銀行は,いずれも普通銀行である
上,近年,都市銀行の中小企業向け貸出比率が上昇する等,融資先の
同質化が進展しているが,
|
| a |
地方銀行及び第二地方銀行の営業店舗は,主として本店所在地の
都道府県に配置され,主に当該都道府県内の顧客と取引を行ってい
ること。
|
| b |
都市銀行は,一部上場会社等の大企業のメインバンクとなること
が多いのに対し,地方銀行及び第二地方銀行は,主に地元企業が中
心となっていること。 |
以上を踏まえ,本件における「一定の取引分野」を下記のとおりとし
た。
|
|
| ①
| 業態
都市銀行11行とした。ただし,外国為替取引については,市場価格
がリアルタイムで全市場参加者に伝えられ,瞬時に裁定が働く仕組み
となっていることなどから,外国為替公認銀行全行を対象とした。
|
|
| ②
| 商品市場
預金・貸出業務を対象とするが,本件は当事行の一方が外国為替銀
行であるため,国内における外国為替業務についても対象とした。 |
|
| ③
| 地理的市場
全国市場を中心とするが,本件行為により預金・貸出業務のシェア
が高くなる地域の有無について,都道府県単位でも検討を行った。
|
|
|
| (3)
| 問題点及び考慮事項
| ①
| 問題点
| ア
| 国内の預金・貸出における都市銀行の中でのシェアは,それぞれ
14.2%,14.7%かつ第2位となる。 |
| イ
| 国内店舗数は,都市銀行中第4位となる。
|
| ウ
| 大企業等に対する新銀行の貸出における都市銀行の中でのシェア
は,19.1%かつ第1位となる。
|
| エ
| 外国為替取引について,豊富な人材,ノウハウを有する東京銀行
が都市銀行上位行と合併することにより,国内の外国為替取引にお
ける新銀行のシェアが高まることとなる。
|
|
| ②
| 考慮事項
| ア
| 新銀行の全国の預金・貸出のシェアは,いずれも15%(預金:
14.2%,貸出:14.7%)を下回り,第3位銀行との格差も2%(預
金:1.5%,貸出:2.0%)に止まる。
|
| イ
| 特定地域において預金・貸出のシェアの顕著な上昇は生じない。
|
| ウ
| 大企業等に対する貸出において,新銀行のシェアが19.1%と,都
市銀行中第1位となるが,第2位とのシェア格差が2.6%に止まっ
ているほか,大企業の場合,信用リスクが小さく,安定的な取引先
であることから,銀行間の貸出競争が活発に行われている上,近
年,企業側は自らの信用力を活用して低利のコマーシャル・ペー
パー,社債の発行等による資金調達を増やし,銀行借入を返済する
動きをみせており,これら直接金融手段と銀行貸出との競争が増大
している。
|
| エ
| 預金・貸出等の銀行業務については,企業部門の資金調達に占め
る銀行借入比率の低下(直接金融の増大)や銀行業務についての金
利規制,業務規制等の競争制限的規制の緩和ないし撤廃に伴い,銀
行間の競争が活性化するものと見込まれる。
|
| オ
| 国内の外国為替取引における新銀行のシェアは,インターバンク
取引,対顧客取引のいずれにおいても15%を下回っている(イン
ターバンク取引:12.3%,対顧客取引:8.1%)ほか,外国為替取
引については,今後,外国為替市場の取引時間の延長,情報通信技
術の発展等により,東京市場と海外市場との相互の影響が更に強ま
り,グローバルな競争が活発化するものと見込まれる。
|
|
|
| (4)
| 本件の処理
上記の点を総合的に勘案すると,本件行為によって,直ちに一定の取
引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断
した。
|
|
9 埼玉中央卸売市場(新設)へ入場予定の青果物卸売業者3社の合併
| (1)
| 本件の概要
本件は,浦和市において青果の卸売業を営む浦和中央青果市場㈱(以
下「浦和中央青果」という。),大宮市において同業を営む㈱大宮中央青
果市場(以下「大宮中央青果」という。)及び上尾市において同業を営
む埼玉県中央青果㈱(以下「埼玉県中央青果」という。)の3卸売業者
(それぞれ地方卸売市場の開設者でもある。)が合併し,合併後の新会
社(以下「新会社」という。)が,埼玉県,浦和市,大宮市及び上尾市
(本件相談後,与野市も参加)が開設する埼玉県中央卸売市場(以下
「新市場」という。)に単一の卸売業者として入場しようとするもので
ある。
なお,新市場の開設は平成12年の予定である。
|
|
| (2)
| 一定の取引分野
本件における一定の取引分野については,新市場を中心とする3社の
小売買参人の分布状況及び取扱額による依存状況をみると,3社の小売
買参人は,20km圏内に大部分が分布しており,また,3社の取扱額から
みた小売買参人への依存状況も20km圏内で大部分であることから,新市
場を中心とする埼玉県内の20km圏内における青果物の卸売分野に「一定
の取引分野」が成立するものと判断した。 |
|
| (3)
| 問題点及び考慮事項
| ①
| 問題点
本件行為により,新会社は,一定の取引分野(新市場を中心とす
る埼玉県内の20km圏内における青果物の卸売分野)においてシェア
41.8%かつ第1位となる。
|
|
| ②
| 考慮事項
| ア
| 20km圏内の地域における3社の小売買参人に対して,東京都内の
各卸売市場(都内7市場の合計20.6%),県内その他市場(14市場
の合計18.7%)及び全農集配センター(11.9%)が有力な競争業者
として販売を行っている。
|
| イ
| 同圏内のうち埼玉県内の小売買参人の市場登録延べ数に占める3
社の小売買参人の登録数の割合は33.9%であって,他の市場が新市
場の有力な競争業者となり得ることを示していると考えられる。
|
| ウ
| 埼玉県は,本件統合により単一卸売人となることによる弊害を未
然に防止する観点から,次の措置を講じることとしている。
| (ア)
| 開設者は,卸売業務が「公開」,「公正」,「公平」に行われるよ
う,指導,監督の徹底を図る。 |
| (イ)
| 「中央卸売市場開設運営協議会」を設置し,学識経験者による
審議・調査を通じて卸売業務の運用等の適正化を図る。 |
| (ウ)
| 新会社,仲卸業者及び小売買参人で構成する「卸売市場取引検
討委員会」を設置し,取引ルール等の確立に係る主体的な監視・
調整体制を整備する。
|
| (エ)
| 新会社に対し,次の事項の周知・徹底を図る。
| a |
専門小売店に対する十分な供給量を確保すること。 |
| b |
品目はもとより,産地,規格等多様な品揃えに配慮するこ
と。
|
| c |
集荷方法,販売方法等について,仲卸業者及び小売買参人か
らの意見聴取に努めること。
|
| d |
パッケージ等のサービス機能や情報提供機能の充実・強化を
図ること。
|
|
| (オ)
| 新会社及び仲卸業者に対し,次の事項の遵守方を指導する。
| a |
従来からの当事会社との関係,小売買参人の規模等により不
当に差別しないこと。
|
| b |
他の卸売業者等と取引することを制限しないこと。 |
|
|
|
|
| (4)
| 本件の処理
上記の点を総合的に勘案すると,本件行為によって,直ちに一定の取
引分野における青果物卸売分野の競争を実質的に制限することとなると
はいえないと判断した。
|
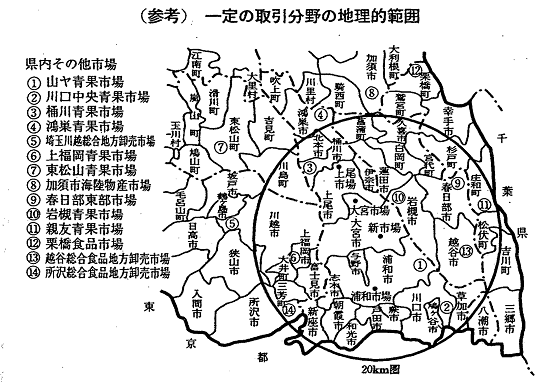 |
10 多摩ニュータウン市場花き部へ入場予定の卸売業者5社の合併
| (1)
| 本件の概要
本件は,東京都が,平成13年に中央卸売市場として多摩ニュータウン
市場花き部(以下「多摩市場」という。)の開場を予定しているとこ
ろ,㈱武蔵野生花市場,㈱多摩生花市場,㈲立川生花市場,㈱八王子生
花市場及び㈱東久留米園芸の5社(以下「5社」という。)が合併し,
合併後の新会社(以下「新会社」という。)が多摩市場に単一の卸売業
者として入場しようとするものである。
|
|
| (2)
| 一定の取引分野
本件における一定の取引分野については,多摩市場を中心とする5社
の小売買参人の分布状況及び取扱額による依存状況をみると,5社の小
売買参人は,20km圏内に70.6%が分布しており,また,5社の取扱額か
らみた小売買参人への依存状況も同地区で72.9%であることから,多摩
市場を中心とする20km圏内における花きの卸売分野に「ー定の取引分
野」が成立するものと判断した。
|
|
| (3)
| 問題点及び考慮事項
| ①
| 問題点
本件行為により,一定の取引分野(多摩市場を中心とする20km圏内
における花き卸売分野)においてシェア32.1%かつ第1位となる。 |
|
| ②
| 考慮事項
| ア
| 多摩市場の周辺には,平成11年に世田谷市場(卸売業者2社)と
して統合の上,同市場に入場を予定している㈱自由ケ丘生花市場
(8.8%),青山生花市場㈱(6.3%),東京蘭葉市場㈱5.7%)ら6
地方卸売市場(計29.2%)が存在するほか,川崎市中央卸売市場北
部市場(卸売業者1社,4.3%).などの有力な競争市場が存在す
る。
|
| イ
| 東京都が多摩市場開設について実施した小売買参人に対するアン
ケート調査の結果によれば,5社の小売買参人であって,5社以外
の周辺の卸売市場の小売買参人として重複して登録しており,統合
後は,距離的に不便を生じるとして多摩市場を利用しないとするも
のが26%あり,これらのものは板橋市場等の他の競合市場を利用す
るとしている。
|
| ウ
| 東京都は,本件行為により単一卸売人となることによる弊害を未
然に防止する観点から,新会社及び仲卸業者に対し,次の事項の遵
守方を指導するとしている。
| a |
小売買参人の規模等により不当に差別しないこと。
|
| b |
他の卸売業者等と取引することを制限しないこと。 |
|
|
|
| (4)
| 本件の処理
上記の点を総合的に勘案すると,本件行為によって,直ちに一定の取
引分野における花き卸売分野の競争を実質的に制限することとなるとは
いえないと判断した。
なお,本件処理後の平成8年2月12日,入場を予定していた5社のう
ち㈲立川生花市場及び㈱多摩生花市場は,統合しても採算面での改善が
見込めないとの理由で入場を辞退することとした。
|
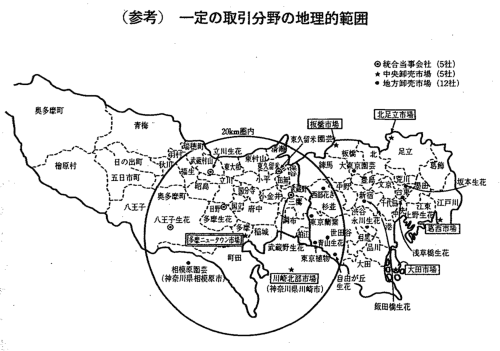 |
11 生コンクリート製造業者による共同生産会社の設立
| (1)
| 概要
本件は,鹿児島県姶良郡栗野地区,大口地区及び加治木地区を地区と
する姶良伊佐地区生コンクリート協同組合(以下「姶良協組」とい
う。)の組合員で,栗野地区において生コンクリート製造業を営む福地
産業㈱,牧園生コンクリート㈱,栗野生コンクリート㈱及び土佐屋生コ
ンクリート㈱(以下「4社」という。)が,生コンクリート工場の集約
化を目的として,共同出資により姶良北部生コンクリート㈱(以下「姶
良北部生コン」という。)を設立し,同社に対し生コンクリートの製造
委託を行おうとするものである。
|
|
| (2)
| 一定の取引分野
姶良協組は,生コンクリートの共同販売を行っており,生コンクリー
トの性質上,運送時間の制約があるため,栗野地区に所在する当事会社
の生コンクリートの需要者のほとんどは協同組合の栗野地区内の建設業
者に限られている。したがって,本件においては,栗野地区内における
生コンクリートの販売分野に「一定の取引分野」が成立するものと判断
した。
|
|
| (3)
| 問題点及び考慮事項
| ①
| 問題点
協同組合が行う共同販売等の共同経済事業は,一定の要件の下に独
占禁止法の適用が除外されているが,組合員の株式所有等について
は,適用除外とはなっていない。
また,共同販売事業が行われている場合,これに参加している組合
員間に販売面における競争はみられないとしても,生産面における競
争は行われており,生産量の多寡が販売シェアの割当ての変更を通じ
て販売面に影響する上,組合員は共同経済事業に参加しないこととし
たり,協同組合から脱退することもできることから,組合員間に競争
関係がみられる。本件行為により,栗野地区に所在する生コンクリー
ト製造業者は従来の4社から1社のみとなり,栗野地区における出荷
シェアは82.4%となる。
|
|
| ②
| 考慮事項
| ア
| 当事会社は,栗野地区において共同販売事業を実施してきたもの
の,需要が漸減傾向にあるため当事会社の出荷実績が落ち込んでき
たことから,共同出資により共同生産会社を設立し,工場の集約化
を図ろうとするものである。
|
| イ
| 当事会社は,姶良協組による割決(共同販売事業を行う協同組合
が受注した物件を組合員に割り当てることをいう。)によって受注
した生コンクリートを姶良北部生コンに製造委託し,生産された生
コンクリートは同協同組合に独自に販売委託するものである。
|
 |
| ③
| 当委員会の判断
本件について,当委員会は,当事会社に対し,従来4社4工場で生
コンクリートの製造,販売をそれぞれ独自に行っていたものを当事会
社4社による共同生産会社1社(2工場)に集約することは,栗野地
区での生コンクリートの販売分野における競争を実質的に制限するこ
ととなるおそれがある旨の指摘を行った。
|
|
| ④
| 当事会社の対応
上記指摘に対し,当事会社から,4社による共同生産会社1社(2
工場)を,それぞれ出資会社2社による共同生産会社1社(1工場)
とする旨の申出があった。
|
|
|
| (4)
| 本件の処理
上記の当事会社の措置等を総合的に勘案すると,本件行為によって,
直ちに一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは
いえないと判断した。
|
|
第6 独占禁止法第4章の見直し
1 規制緩和推進計画の内容
独占禁止法第4章については,近時,事業者の負担軽減等の観点から見
直すべきであるとの要請があり,規制緩和推進計画では,①持株会社の禁
止について,事業支配力の過度の集中を防止するとの趣旨等を踏まえつ
つ,検討を行い,結論を得ること,②合併,営業譲受け等の届出制度,株
式所有の報告制度等について,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直
しを図ること,③独占禁止法第9条の2の規定により株式保有総額の制限
を受ける大規模会社の規模要件である資本金及び純資産の引上げを図るこ
ととされた。
これを受けて,独占禁止法第9条の2の規定により株式保有総額の制限
を受ける大規模会社の規模要件である資本金及び純資産を引き上げるた
め,独占禁止法施行令が改正され,独占禁止法第9条の2の規定により株
式保有総額の制限を受ける大規模会社は,資本金100億円以上又は純資産
300億円以上の株式会社(金融業を除く。)から,資本金350億円以上又は
純資産1400億円以上の株式会社(金融業を除く。)とされた(平成7年4
月26日公布・施行)。
なお,改定された規制緩和推進計画では,①合併・営業譲受等の届出制
度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届出制度について,制度の趣旨・
目的,企業の負担軽減,国際的整合性の確保等の観点から,裾切り要件の
導入,引上げ等を含め,見直しを図る,②持株会社規制について,企業の
リストラの促進,ベンチャー企業の振興等を図るため,独占禁止政策に反
しない範囲で持株会社を解禁すべく見直しを行い,所要の措置を講じ,大
規模会社の株式保有制限についても,この見直しに伴い必要な検討を行う
こととされた。
2 独占禁止法第4章改正問題研究会における検討
当委員会は,独占禁止法第4章に規定されている企業結合規制全般の在
り方に関する幅広い課題について検討を行うために,平成7年11月から
「独占禁止法第4章改正問題研究会」(座長:館龍一郎 東京大学名誉教
授)を開催している。
| (1)
|
同研究会においては,各界の関心が非常に高く,規制緩和の流れの中
で早急に検討する必要性が高いと考えられることから,持株会社問題に
ついて最初に検討が行われ,当委員会は,平成7年12月,同研究会が持
株会社問題に関して取りまとめた報告書を公表した。その概要は,以下
のとおりである。
| ア
| 持株会社禁止制度の目的
持株会社禁止制度は,事業支配力の過度の集中の防止を図るための
ものである。
我が国においては,大規模な企業集団等が存在し,上場企業の発行
済株式に占める法人所有株式の比率が極めて高く,企業間の株式保有
関係と取引関係との間には一定の相関関係がみられる。このような経
済実態の下で,持株会社を全面的に容認した場合,株式保有を通じた
企業間関係がより強固なものになり,公正かつ自由な取引が行われ難
くなる可能性があるなど,市場メカニズムの機能が妨げられるおそれ
がある。また,我が国市場の開放性・透明性を向上させることが求め
られていることも併せて考えると,持株会社制度については事業支配
力の過度の集中の防止を図るという枠組みを基本的に維持することが
重要である。
|
|
| イ
| 制度見直しの視点
これまでの持株会社の設立等が全面的・一律に禁止されてきたこと
から,持株会社禁止制度の目的に反しないと考えられる場合にまで,
その利用を制限してきたおそれがあることは否定できない。我が国特
有の雇用慣行等に照らしてみれば,持株会社方式による新規事業の展
開,事業の統合といった選択肢が増えることにより,企業が競争力を
高め,競争が活性化される可能性がある。
したがって,持株会社禁止制度については,事業支配力の過度の集
中の防止という独占禁止法第1条の目的規定を踏まえ,これに反しな
い範囲内で見直すことが妥当である。
|
|
| ウ
| 制度の目的に反しないと考えられる類型
公正取引委員会により一定の監視のための措置が講じられるように
しておけば,持株会社禁止制度の目的に反しないと考えられる類型の
持株会社としては次のようなものが考えられる。
|
| (ア)
| 一定規模以下
|
| (イ)
| 純粋分社化
|
| (ウ)
| ベンチャー・キャピタル |
| (エ) |
一定の金融持株会社
|
なお,公正取引委員会は,持株会社の設立又は持株会社の転化の段
階で個別に審査をするようにすべきである。
|
|
| エ
| 公正取引委員会の事後監視措置
持株会社は経済力集中の手段となりやすいことから,いったん認容
された持株会社がその性格を変えないか等について,公正取引委員会
が監視する必要があり,また,公正取引委員会はその運用の透明性を
確保するため,運用基準を作成・公表することが望ましい。
|
|
| オ
| 第9条の2及び第11条との関係
持株会社禁止規定のほかに,事業支配力の過度の集中を防止を図る
ための規定として,第9条の2(大規模会社の株式保有総額の制限)
と第11条(金融会社の株式保有制限)があるが,これらについても,
その枠組みを基本的に維持し,かつ,それぞれが有効に機能するよう
にすることが重要である。
|
|
なお,当委員会では,この報告書等の趣旨を踏まえて,法案改正作業
を進めたが,持株会社に係る独占禁止法改正法案の第136回国会提出に
は至らなかった。
|
|
| (2)
|
同研究会においては,次期検討課題として,合併等の届出制度・株式
保有の報告制度など第4章の手続面を中心とする検討を行うこととさ
れ,平成8年6月から,「企業結合規制見直しに関する小委員会」(座
長:正田 彬上智大学法学部教授)を同研究会の下に設けて検討を行っ
ているところである。
|