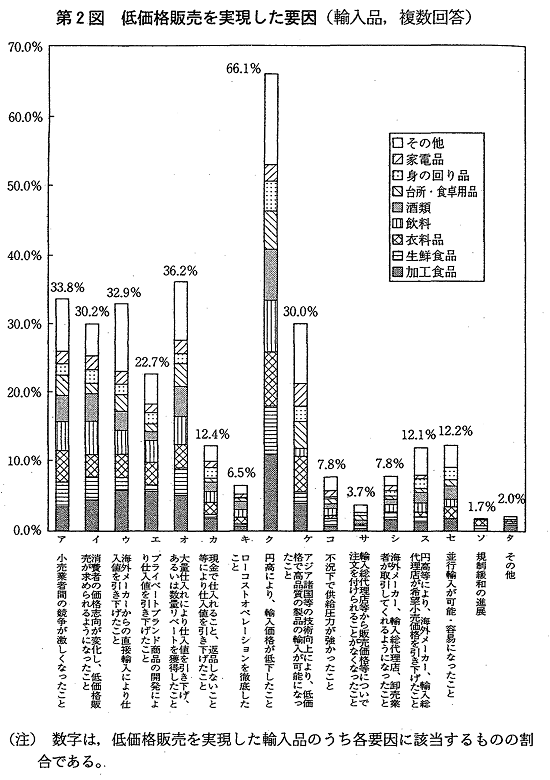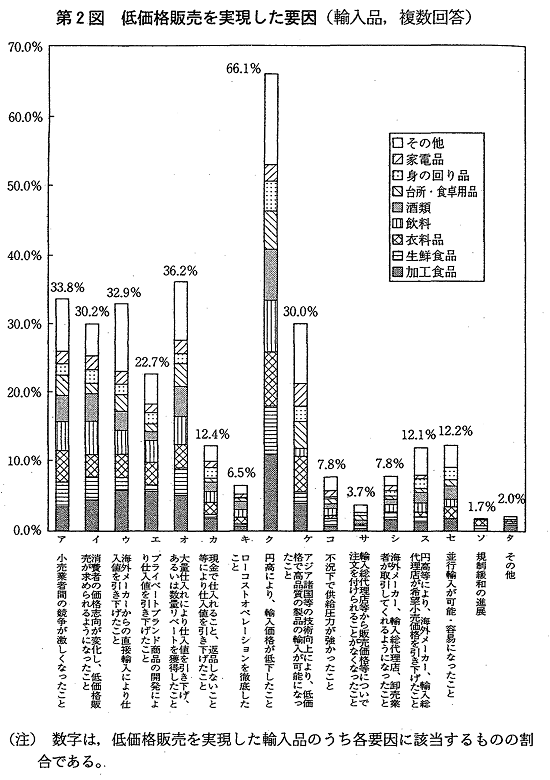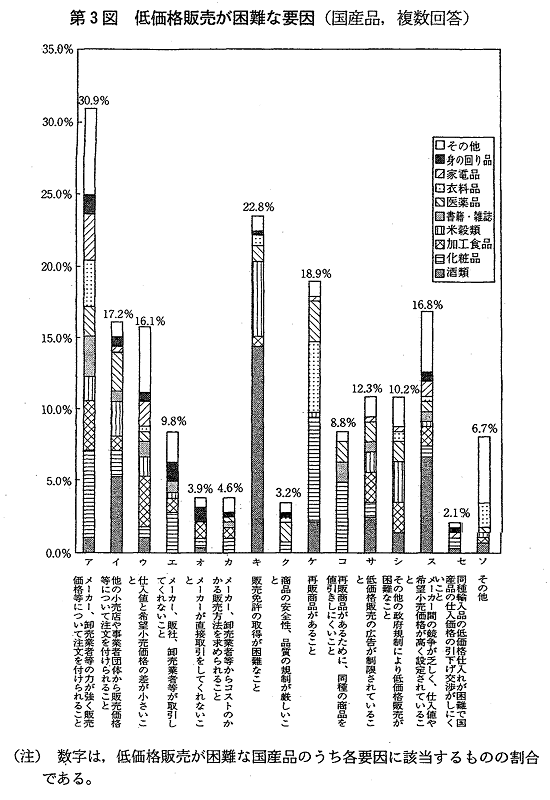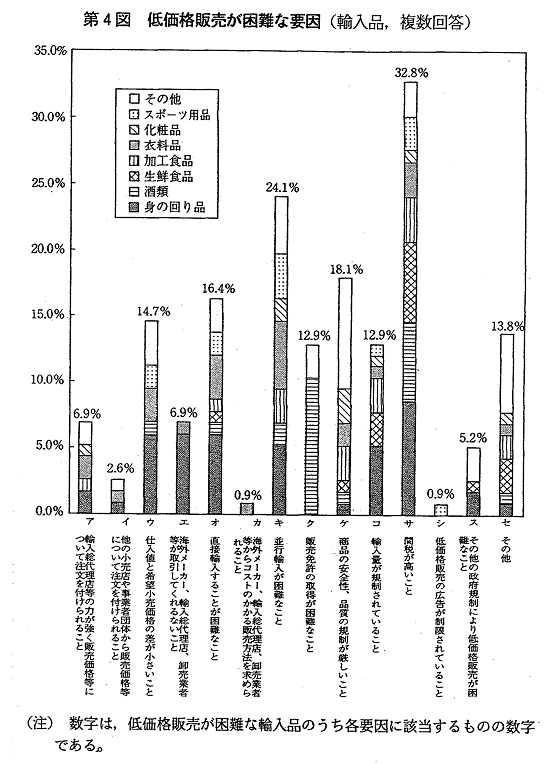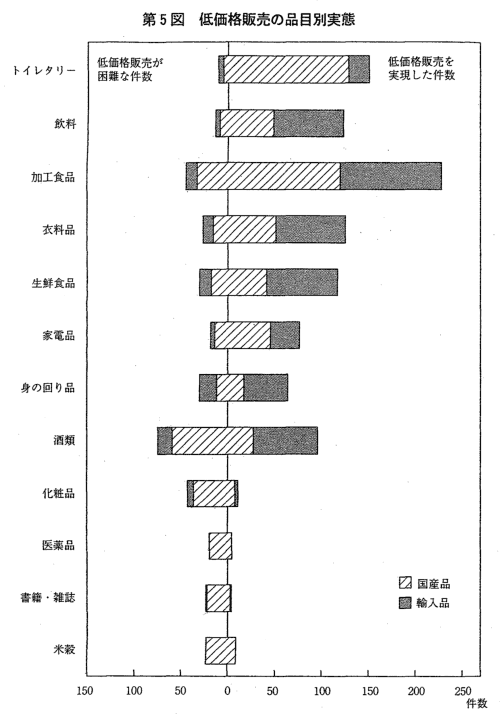第11章 不公正な取引方法の指定
及び運用
第1 概 説
独占禁止法は,不公正な取引方法の規制として第19条において事業者が不
公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が
不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際契約を締結すること,事
業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするこ
と,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有
すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社
が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条第
1項,第8条第1項,第10条第1項,第13条第2項,第14条第1項,第15条
第1項等)。
不公正な取引方法として規制される行為の具体的内容は,当委員会が法律
の枠内で告示により指定することとされている(第2条第9項,第72条)。
不公正な取引方法に関しては,上記規定に違反する事件処理のほか,不公
正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法の防止のための指導業
務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に
応じることにより違反行為の未然防止に努めている。
第2 不公正な取引方法等に関する実態調査及び改善指導
1 国産品及び輸入品の低価格販売に関する調査
| (1) |
調査の趣旨
近年,ディスカウントストア等の進出に伴い小売業者間の競争が活発
化し,従来ないような低い価格で継続的に販売する小売業者が増加して
いる。このような低価格販売は内外価格差の縮小に資するものと考えら
れるが,低価格販売が常に円滑に行われるとは限らない。
そこで,今般,流通問題研究会(座長 鶴田俊正専修大学教授)にお
いて,比較的低価格販売の広がりがみられるチェーンストア及びディス
カウントストアを対象として,国産品及び輸入品の低価格販売の実態,
最近1年間で低価格販売を実現した要因及び低価格販売が困難な要因を
把握し,競争政策上の問題点を探ることを目的として調査,検討を行
い,「国産品及び輸入品の低価格販売に関する調査」として取りまと
め,平成7年6月,これを公表した。
同研究会の取りまとめた調査結果の概要と,同研究会の指摘した競争
政策上の評価と問題点は,次のとおりである。 |
|
| (2) |
調査結果の概要
| ア |
低価格販売を実現した要因
最近1年間で従来より低価格販売を実現した品目は,国産品ではト
イレタリー関連品(21.1%),加工食品(19.7%)が多く,次いで衣
料品(8.5%),飲料(8.1%),家電品(7.5%)と続いており,輸入
品では加工食品(15.7%),生鮮食品(10.9%),衣料品(10.8%),
飲料(10.8%),酒類(10.1%)が多い。
低価格販売を実現した要因としては,第1図,第2図のように,ま
ず,消費者の低価格志向を背景として小売業者間の競争が激しくなっ
たことにより,円高やアジア諸国等の技術向上の下で,チェーンスト
ア,ディスカウントストア等が,メーカーとの直接取引,プライベー
トブランド商品の開発,大量仕入れによる仕入値の引下げ等を行った
ことが大きい。またメーカーも,チェーンストア,ディスカウントス
トア等を取引相手として認知し,直接取引やプライベートブランド商
品の開発に応じたことも大きな要因として挙げられるほか,国産品の
オープン価格化や並行輸入の容易化も挙げられる。 |
|
| イ |
低価格販売が困難な要因
低価格販売が困難な品目は,国産品では酒類(20.0%),化粧品
(12.3%),加工食品(10.5%)が多く,次いで米穀類(8.1%),書
籍・雑誌(7.7%),医薬品(6.7%)と続いており,輸入品では身の |
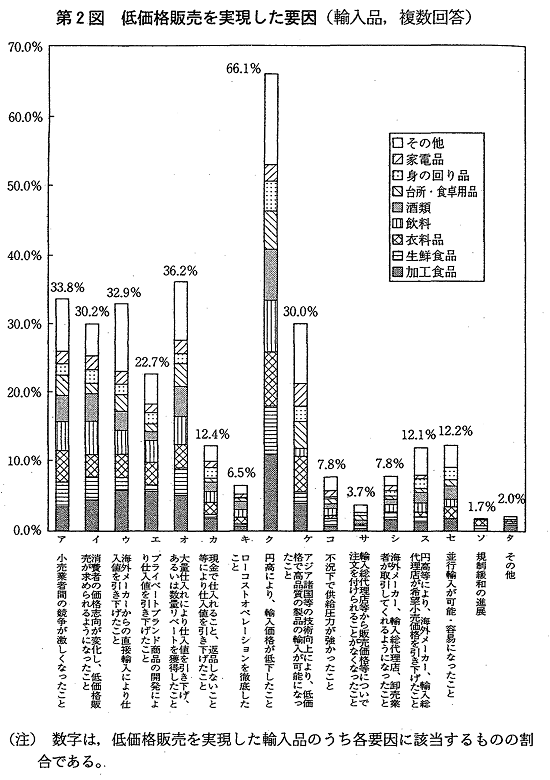
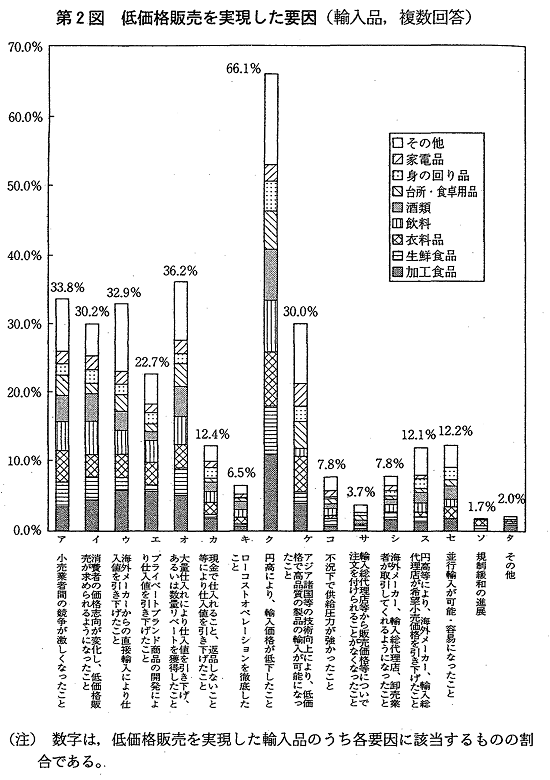
回り品(16.4%),酒類(13.8%),生鮮食品(11.2%),加工食品
(11.2%)が多い。
低価格販売が困難な要因としては,第3図,第4図のように,ま
ず,政府規制が挙げられる。このうち,国産品については販売免許の
取得困難,再販制度,価格広告の制限等が大きく,輸入品については
関税,輸入数量制限,安全性・品質の規制等が大きい。また,メー
カーや他の小売店,事業者団体による販売価格等への関与も主に国産
品において大きな要因である。さらに,メーカー等のマーケティング
方法の影響もある。このうち,仕入値と希望小売価格の差が小さいこ
との影響が国産品,輸入品ともかなりあるほか,取引先の選別や販売
方法の制限も要因として挙げられ,また,輸入品については,直接取
引の困難の影響もかなりある。さらに,並行輸入が困難なことも大き
い。これらの流通取引慣行については,メーカー等による販売価格等へ
の関与,取引先の選別,直接取引の困難等,チェーンストアよりもディ
スカウントストアにとってより困難な要因となっているものが多い。 |
|
| ウ |
低価格販売の品目別実態
第5図のように,チェーンストア,ディスカウントストアの認識か
らは,全体として低価格販売の広がりがみられ,特に,トイレタリー
関連品,飲料については低価格販売がおおむね円滑に進んでいると考
えられる。また,加工食品,衣料品,生鮮食品,家電品,身の回り品
については,低価格販売が広がっていると考えられるが,障害もかな
りうかがえる。一方,酒類については,国産品で低価格販売の障害が
大きいと考えられる。さらに,化粧品,医薬品,書籍・雑誌,米穀に
ついては,低価格販売が広がっていないといえる。 |
| (ア) |
トイレタリー関連品
消費者の低価格志向を背景として小売業者間の競争が激しくなっ
たことにより,円高やアジア諸国等の技術向上の下で,チェーンス
トア,ディスカウントストア等が,メーカーとの直接取引,プライ
ベートブランド商品の開発,大量仕入れによる仕入値の引下げ等の |
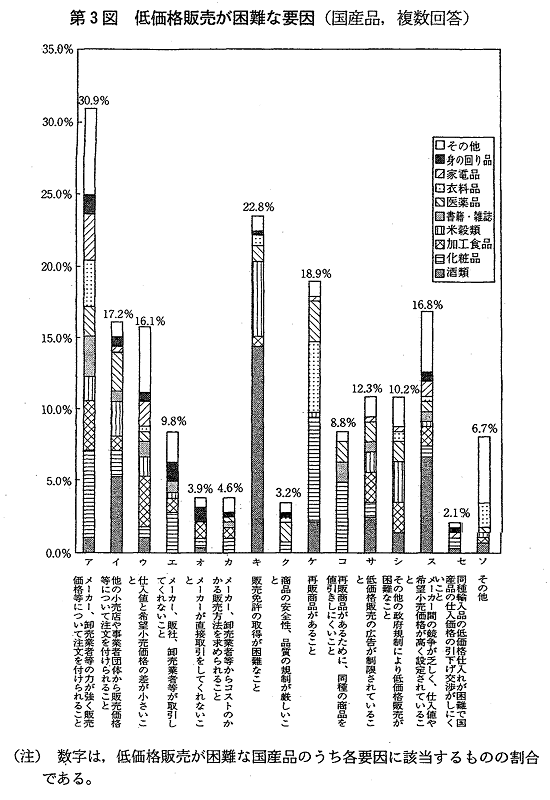
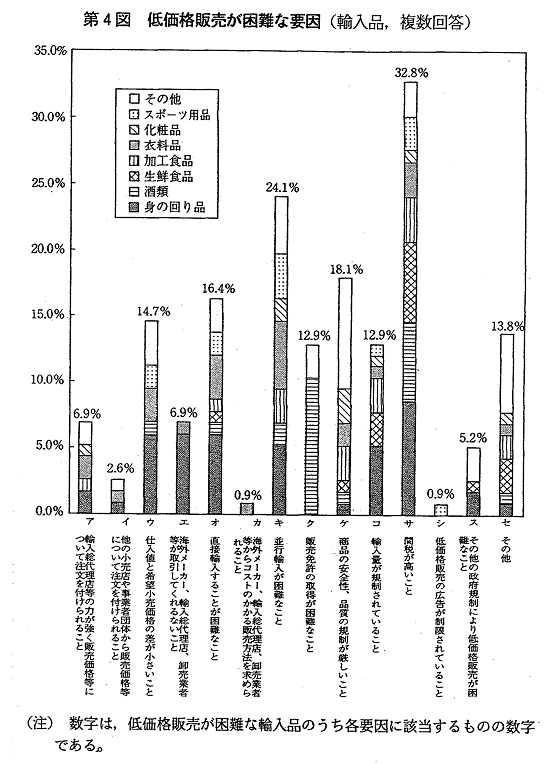
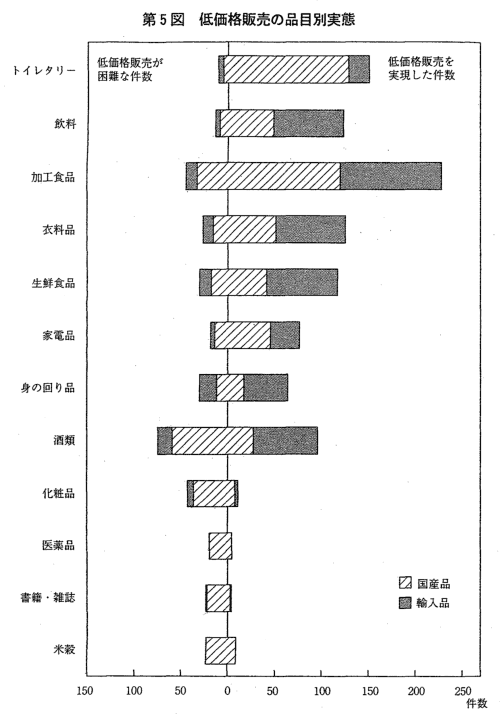
販売政策をとったことが主な要因となって,低価格販売が進んでい
る。また,国産品については,ナショナルブランド商品の希望小売
価格が低下している。 |
|
| (イ) |
飲料
トイレタリー関連品と同様の要因に加え,国産品については現金
仕入れ等による仕入値の引下げもあって,低価格販売が進んでい
る。 |
|
| (ウ) |
加工食品
トイレタリー関連品と同様の要因に加え,国産品については輸入
原材料の価格低下もあって,低価格販売が広がっている。
しかし,低価格販売が困難な要因として,メーカー等による販売
価格等への関与,仕入値と希望小売価格の差が小さいことを挙げて
いる小売業者(チェーンストア,ディスカウントストア)も多い。 |
|
| (エ) |
衣料品
トイレタリー関連品と同様の要因に加え,並行輸入の容易化や国
産品については輸入原材料の価格低下もあって,低価格販売が広
がっている。
しかし,低価格販売が困難な要因として,並行輸入が困難なこと
やメーカー等による販売価格等への関与を挙げている小売業者
(チェーンストア,ディスカウントストア)も多い。 |
|
| (オ) |
生鮮食品
トイレタリー関連品と同様の要因により低価格販売が広がって
いるが,プライベートブランド商品の開発を挙げている小売業者
(チェーンストア,ディスカウントストア)は少ない。
一方,低価格販売が困難な要因として,関税が高いことが挙げら
れている。 |
|
| (カ) |
家電品
トイレタリー関連品と同様の要因により低価格販売が広がってい
るが,国産品については,プライベートブランド商品の開発は少な
く,現金仕入れ筆による仕入値の引下げを挙げる小売業者(チェー
ンストア,ディスカウントストア)が多い。また,メーカー等によ
る販売価格等への関与がなくなったことを挙げる小売業者(チェー
ンストア,ディスカウントストア)も多いが,一方で,そのような
関与があるというものも多い。 |
|
| (キ) |
身の回り品
トイレタリー関連品と同様の要因により低価格販売が広がってお
り,さらに並行輸入が容易になったという要因を挙げる小売業者
(チェーンストア,ディスカウントストア)も多い。
しかし,一方で,低価格販売が困難な要因として,並行輸入が困
難なことを挙げる小売業者(チェーンストア,ディスカウントスト
ア)もあり,また,輸入品については,海外メーカーからの直接輸
入が困難なこと,海外メーカー等が取引してくれないこと,仕入値
と希望小売価格の差が小さいこと,関税が高いことが挙げられてい
る。 |
|
| (ク) |
酒類
低価格販売を実現した要因はトイレタリー関連品と同様である
が,販売政策としては大量仕入れによる仕入値の引下げが特に多
く,並行輸入が容易になったという要因も多い。
しかし,販売免許の取得困難が国産品で非常に多く,輸入品につ
いても多い。また,事業者団体等による販売価格等への関与が国産
品について多く,関税が高いことを挙げる小売業者(チェーンスト
ア,ディスカウントストア)もある。 |
|
| (ケ) |
化粧品
低価格販売が困難な要因として,国産品について,再販商品であ
ること及び再販商品があるために同種の商品を値引きしにくいこと
を挙げる小売業者(チェーンストア,ディスカウントストア)が多
い。また,メーカー等による販売価格等への関与やメーカー等が取
引してくれないことを挙げる小売業者(チェーンストア,ディスカ
ウントストア)も多い。 |
|
| (コ) |
医薬品
低価格販売が困難な要因として,メーカー,事業者団体等から
の販売価格等への関与及び再販商品であることを挙げる小売業者
(チェーンストア,ディスカウントストア)が多い。 |
|
| (サ) |
書籍・雑誌
低価格販売が困難な要因として,再販商品であることを挙げる小
売業者(チェーンストア,ディスカウントストア)が多い。 |
|
| (シ) |
米穀
低価格販売が困難な要因として,販売免許の取得困難やメー
カー,事業者団体等からの販売価格等への関与を挙げる小売業者
(チェーンストア,ディスカウントストア)が多い。 |
なお,平成7年11月から施行される食糧法の下で,卸売業者・小
売業者について従来の許可制を登録制に改めることに加え,多様な
流通を可能とするなどの規制緩和が推進されることとなる。 |
|
|
| (3) |
競争政策上の評価と問題点
| ア |
低価格販売の進展
近年,チェーンストアやディスカウントストアによる低価格販売が
広がっているが,これは,品目によって程度の差はあるものの,消費
者の低価格志向を背景としてチェーンストアやディスカウントストア
等の小売業者間の競争が激しくなったことが大きな要因となってい
る。このため,競争政策として流通業界において公正かつ自由な競争
が活発に行われる環境を整備していくことが重要である。また,大規
模小売店舗法の緩和等によりチェーンストア,ディスカウントストア
等の出店が増加し,競争が活発化している地域もあるため,大規模小
売店舗法を始めとして政府規制の緩和を進めることが必要である。 |
|
| イ |
競争政策上の課題
| (ア) |
政府規制
チェーンストアやディスカウントストアが低価格販売が困難な要
因とする政府規制には,出店や当該商品の販売を免許制や許可制と
することにより市場への参入の自由を制限するもの,商品の安全
性・品質を規制することにより実質的に並行輸入等を困難とするも
の,輸入量の規制により大量仕入のメリット等を阻害したり関税に
より輸入品の価格を割高とするもの,再販売価格維持を独占禁止法
の適用除外とし小売業者による自由な価格形成を直接制限するもの
などがある。
このため,これらの政府規制について,流通への参入を容易に
し,市場における競争を活発化させるため,規制緩和の方向で積極
的に見直しが行われることが望ましい。 |
|
| (イ) |
メーカー,事業者団体等による販売価格への関与
チェーンストアやディスカウントストアの販売力の増大に伴い,
メーカーがこれらを無視できなくなったこと,ナショナルブランド
製品とプライベートブランド製品や輸入品との競争が激しくなった
こと等から,低価格販売に対するメーカー,販社等の関与は減少し
ている。
しかし,このような関与があるというチェーンストアやディスカ
ウントストアがまだ多い。これらのチェーンストアやディスカウン
トストアによれば,ブランド力のある商品のメーカー等の中には,
低価格販売を行う小売店の周辺小売店のクレームを受け当該店に低
価格販売を控えるよう求めるものがある。
また,当該小売店の仕入先の卸売業者の方にメーカーからクレー
ムを付けられる,小売店組合等から低価格販売やその広告をやめる
よう求められるとするチェーンストアやディスカウントストアもあ
る。
小売業者の中にはその販売価格についてメーカー,小売店組合等
の意向を気にかけるものもみられるが,小売業者の販売価格は小売
業者が自主的に決定すべきものである。一般にメーカーの人為的手
段によって,流通業者がメーカーの示した価格で販売するように
なっている場合や,事業者団体が自ら又はメーカー,卸売業者等を
通じて競争的行為をしないようにさせる場合には独占禁止法上問題
となることから,公正取引委員会は今後とも実態を注視し,独占禁
止法に違反する行為があれば,厳正に対処する必要がある。 |
|
| (ウ) |
メーカー等のマーケティング方法
チェーンストアやディスカウントストアの販売量が増大したこと
等により,メーカーはこれらを取引相手として認知したり,直接取
引に応じたり,さらには,プライベートブランド商品の開発に協力
するようになってきている。また,希望小売価格についてもオープ
ン価格化を行うメーカーが出てきている。
しかし,メーカーの中には,ブランドイメージ維持等のために一
部の商品を系列店や百貨店等向けに限定し,低価格販売を行う小売
業者(チェーンストア,ディスカウントストア)には扱わせないも
のや,小売業者に対して対面販売を指示する等,販売方法を制限す
るものがあるというチェーンストアやディスカウントストアが少な
くない。
一般に,メーカーが卸売業者に対して,安売りを行うことを理由
に小売業者へ販売させないようにすることは,これにより当該商品
の価格が維持されるおそれがあり,原則として独占禁止法上問題と
なり,また,メーカーの小売業者に対する販売方法の制限が,小売
業者の販売価格の制限の手段として用いられる場合等には独占禁止
法上問題となることから,公正取引委員会は,今後とも実態を注視
し,メーカー等による独占禁止法に違反する行為があれば,厳正に
対処する必要がある。 |
|
| (エ) |
並行輸入
円高もあり,並行輸入業者等を通じて並行輸入を行っている
チェーンストアやディスカウントストアが多い。
しかし,ブランド力のある海外メーカーの商品等の中には,総代
理店の市場への影響力が強く,他のルートから仕入れることが困難
なものがある。
したがって,総代理店の行為が,価格を維持するため,並行輸入
を不当に阻害するものと認められる場合には独占禁止法上,厳正に
対処する必要がある。 |
|
|
|
2 クレジットカード業界の実態調査
| (1) |
調査の趣旨
当委員会は,近年のクレジットカード業界のカード会社間の提携,フ
ランチャイジー獲得競争,加盟店獲得競争等により再編成や系列化が進
んでいることに伴い,カード業界の系列化,カード会社間の手数料競
争,金利競争の状況,加盟店の勧誘,消費者の勧誘・優遇等の状況を調
査し,これらの動きに伴う問題点を把握し,調査結果を今後の競争政策
の運営に資することを目的とするため,「クレジットカード業界の実態
調査」として取りまとめ,平成7年7月にこれを公表した。
なお,カードには,①発行元が不特定多数の小売・サービス業と契約
するものと②発行元が契約先を自社グループの子会社や系列関連先に限
定するもの(ハウスカード)の2種類があるが,本調査は,利用範囲が
限定されず,汎用性の高い①のカードを中心に調査を行った。 |
|
| (2) |
実態調査結果の概要
| ア |
クレジットカード業界の規模・構造等
| (ア) |
カードの発行枚数(1億9596万枚,成人1人当たり2.1枚)及び
家計消費支出(267兆円)に比べた年間取扱高(17兆円)は,安全
対策上カードのキャッシュレス決済機能に対して強いニーズがある
米国に比べて少ない。 |
| (イ) |
年間取扱高を発行主体別にみると,銀行系カード会社が全体の5
割強を占めて最も多く,次いで,流通系カード会社と信販会社がそ
れぞれ2割程度と続いている。また,加盟店数を発行主体別でみる
と,銀行系カード会社及び信販会社で9割強を占めている。
年間取扱高の中で大手カード会社の占める割合は,非常に大きく
なっており,カード市場は大手中心の構造になっている。 |
|
| イ |
クレジットカード業界の提携,系列化等の状況
| (ア) |
銀行系カード会社,信販会社及び中小小売商団体の間の提携の状
況をみると,銀行系カード会社と中小小売商団体はそれぞれ同じ発
行主体同士の提携が最も多く,信販会社は中小小売商団体との提携
が最も多くなっている。 |
| (イ) |
昭和55年5月,住友クレジットが中心となってビザジャパンを設
立し,ビザグループによるフランチャイズ展開が行われグループ化
が進められた。こうした状況にジェーシービー,ディーシーカー
ド,ミリオンカード・サービス及びユーシーカードの4社は,それ
ぞれのフランチャイズ展開を開始し,フランチャイジーの獲得競争
が行われている。しかし,現在銀行系カード会社によるフランチャ
イズ展開はほぼ収束期にあるといわれている。 |
|
| ウ |
クレジットカード会社と加盟店との取引
| (ア) |
標準的な加盟店手数料率をみると,カード会社のうち,加盟店の
業種によって差を設けていないものでは3%以上5%未満が8割を
占め,加盟店の業種によって差を設けているものでも3%以上5%
未満が多い。
ヒアリングによれば,他のカード会社が進出して競争が激しくな
り,加盟店手数料率が低下しているというカード会社があり,料率
は低下傾向にあるが,米国に比べると,日本の料率は高い。これ
は,日本と違い米国におけるバンクカードはリボルビング払方式が
主となっており,カード会員からの手数料(金利)収入が大きいこ
との影響もある。
加盟店手数料率の決定方法については,カード事業のコスト等を
参考として決めているカード会社が過半数となっている。 |
| (イ) |
クレジットカード会社と加盟店の契約において,カード利用会員
と現金客の差別取扱いの禁止を規定するカード会社が8割である。
その理由としては,カード利用を促進するためというものがほとん
どであり,この規定に特に問題となる影響は無いとする加盟店が大
部分である。
また,他のカード会社へ重複加盟しない旨を規定するカード会
社,及び加盟店が当該カード会社の提携先カード会社にも加盟して
いるときに決済カードは自社とするよう要請するカード会社は,共
に少ない。 |
| (ウ) |
力ード会社の加盟店の勧誘方法としては,会員数の多さ等をPR
するものが8割あり,加盟店がカード会社の勧誘に応じた動機をみ
ても,会員数が多く利用増が見込めるというものが8割を占める。 |
|
| エ |
クレジットカード会社と消費者との取引
| (ア) |
一般カードの年会費をみると,1,250円というカード会社が7割
を占め,カード会社間でばらつきが少ないが,米国における年会費
に比べると低い水準にある。 |
| (イ) |
ショッピング及びキャッシングの手数料率(金利)は,カード会
社間で手数料率のばらつきはあまりなく,米国のように料率の引下
げ競争が激化しているという状況ではない。これには,米国のバン
クカードはリボルビング払が主になっているのに対し,日本では
ショッピングについて1回払,ボーナス一括払等,手数料のかから
ない支払方法をとる会員がほとんどであることの影響もある。 |
| (ウ) |
カード入会を勧誘する手段として加盟店の多さ等をPRすること
が最も効果が大きいと考えるカード会社が最も多い。これに対し,
消費者が現在のカードを選んだ理由をみると,カード利用に伴う加
盟店の割引特典が魅力的なためを挙げるものが最も多く,次が加盟
店が多いためとなっている。 |
| (エ) |
会員のカード利用を促進する手段としてカード利用に伴う加盟店
の割引特典を提供することが最も効果が大きいと考えるカード会社
が半数近い。消費者も,このような利用促進策のあるカードを,現
金払や他のカードよりも優先的に利用するものが8割を占めてい
る。 |
|
| オ |
情報ネットワーク化について
| (ア) |
ほとんどのカード会社が,カード会社のコンピュータと加盟店に
設置されるCAT(信用照会端末)相互間を接続するクレジット・
オンラインのためのデータ通信システムとして,CAFIS(NT
Tが開発・運用)又はCATNET(日本IBMが開発・運用)を
利用しており,これらのシステムの利用に際して差別的な取扱い等
の不利益を受けたとするものは無かった。
また,加盟店等との間のデータ・事務処理は,顧客情報のプール
等のために提携グループの中心となるカード会社がまとめて行って
おり,情報化投資も進めている。 |
| (イ) |
加盟店における情報ネットワークの利用状況について,CATを
導入している加盟店が大部分を占め,その過半数がカード会社から
無償で提供されている。CAT導入のメリットとしては,信用照会
が手軽にかつ確実にできることを挙げる加盟店がほとんどである。
一方,CAT導入のデメリットとしては,利用頻度と経費を対比す
るとコスト高であることを挙げる加盟店が最も多い。 |
|
|
| (3) |
競争政策上の評価と今後の対応
| ア |
クレジットカード会社の提携・系列化
カード会社が加盟店を獲得するためには会員数の多さが最も効果的
であり,逆に会員を獲得するためには加盟店の多さが有力な手段と
なっているように,カード事業では規模の大きさが重要である。この
ような事情もあって,カード会社間の提携・系列化が進んでおり,例
えば,銀行系カード5社は地方銀行系カード会社をフランチャイジー
としている。また,信販会社と中小小売商団体の間や中小小売商団体
同士の間などで提携が行われている。
米国においては,ビザ及びマスターカードの二大系統のバンクカー
ドと,アメリカン・エキスプレスの三者のカード会社がほとんどを占
めている状況にあるが,我が国の場合にはそれほど統合が進んでいる
とはいえない。しかし,我が国の場合には米国のような加盟店の相互
開放だけでなく,データ・事務処理の一体化等も行われており,提携
カード会社間の結び付きは米国よりも緊密である。
カード会社が提携先やフランチャイジーに対して他のカード会社と
の取引を制限するような状況はみられないが,銀行系カード会社にリ
ボルビング払が認められたこと等により,今後もカード業界の再編,
統合が進むと予想されるため,これに伴い公正な競争を阻害するよう
な行為が行われないように注視していきたい。 |
|
| イ |
情報ネットワーク
情報システムの整備やデータ・事務処理については,米国では専門
業者が担う場合が増えているのに対し,日本では提携グループの中心
となるクレジットカード会社が行っている。
データ・事務処理等のサービスが外部化され市場で自由に利用でき
る方が,参入が容易であり競争促進的と考えられる。もっとも,日本
においても,情報システムの利用について差別取扱いはみられない
が,今後も情報システム化やカード業界の再編・統合が進むと予想さ
れるため,差別取扱い等が生じないように注視していきたい。 |
|
| ウ |
加盟店手数料率,年会費,金利等
加盟店手数料率は,クレジットカード会社の提示どおりではなく,
加盟店との交渉により決定されることが多く,料率にはカード会社間
でばらつきがみられる。また,カード会社,加盟店とも加盟店手数料
率よりも会員数の多さを重視するものがほとんどであり,料率は米国
よりも高いが,カード会社間の競争が激しくなっていることに伴い,
低下傾向にある。今後,日本でも,米国のように加盟店手数料率が最
大の競争手段となっていく可能性がある。
一方,会員の年会費及び金利はカード会社間でばらつきが少なく,
例えば銀行系カード会社5社の年会費及び手数料率は同率になってい
る。
ただし,年会費は米国よりも低く,無料というカード会社も少なく
ない。また,金利についても,ショッピングについて1回払,ボーナ
ース一括払等,金利のかからない支払方法がほとんどであるため,消費
者も金利を余り重視しないという事情がある。
銀行系カード会社にリボルビング払が認められたこと等に伴い,今
後金利のかかる支払方法のウェイトが上昇し,米国のように金利の低
さが最大の勧誘手段になっていく可能性がある。
しかし,加盟店手数料率や会員年会費・金利について,加盟店や消
費者に不満がみられ,また,主要カード会社の会員の年会費,金利が
同率になっていることから,独占禁止法に違反する行為が行われない
よう,今後とも実態を注視していきたい。 |
|
|
3 役務の委託取引に関する調査
下請法は物品の製造及び修理の委託を適用対象としているところ,かね
てから中小企業の団体等から役務の委託取引について,下請法又は独占禁
止法で規制すべきであるとの意見・要望があること,近年の我が国経済の
景気低迷の長期化による影響が非製造業の委託取引分野についても生じ,
独占禁止法上の問題が生じているのではないかと思われることから,非製
造業分野においても下請法の適用対象となる取引については,下請法を適
用することによって下請取引の適正化を図っていく一方で,下請法の適用
対象となっていない役務の委託取引についても14業種を選定し,平成8年
2月以降アンケート調査及びヒアリング調査により実態調査を実施し,問
題点の把握と対応策の検討を行っている。
4 新聞
新聞業においては,独占禁止法及び景品表示法に基づく告示により,押
し紙(注文部数を超えて新聞を供給すること)及び拡材(販売部数拡大等
のために用いられる景品類)・無代紙(購読者に無償で供給される新聞)
の提供等の行為は禁止されているにもかかわらず,これらに係る違反事例
の申告や情報提供が跡を絶たない。このため,当委員会は,これらの全国
的・全般的な事態を把握し,併せて新聞業における取引の公正化を図るこ
とを目的として,従来から各種の調査を実施するとともに,新聞公正取引
協議委員会に対して随時,指導を行ってきている。
当委員会は,平成7年度においては,平成6年度に引き続き,当委員会
の消費者モニターに対し,拡材・無代紙の提供の有無等についてアンケー
ト調査を実施するなど正常化の監視に努めるとともに,その調査結果を踏
まえて,新聞公正取引協議委員会に対し,問題点の改善指導及び正常化の
推進について要望を行った。
第3 不公正な取引方法に関する相談状況
当委員会は,独占禁止法の不公正な取引方法に関する電話・来庁等による
一般からの相談に対して,従来から積極的に応じてきている。また,平成元
年2月には,「特許・ノウハウライセンス契約における不公正な取引方法の
規制に関する運用基準」に基づき,平成3年7月には「流通・取引慣行に関
する独占禁止法上の指針」(流通・取引慣行ガイドライン)に基づき,それ
ぞれ特許・ノウハウライセンス契約,流通・取引慣行に係る事前相談制度を
設けている。
さらに,平成7年10月には,流通・取引慣行ガイドライン等に対する理解
を一層深めるため,相談のあった事例のうち,主要な事例を相談事例集とし
て取りまとめ,公表するとともに,事業者等に対し説明会を実施した。