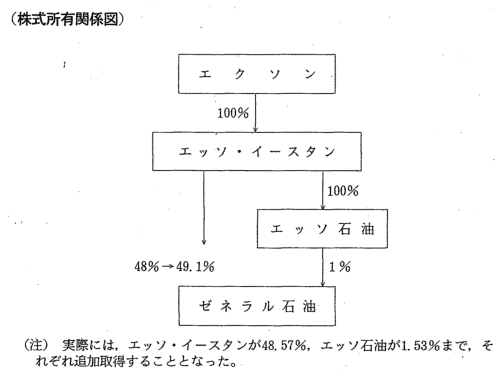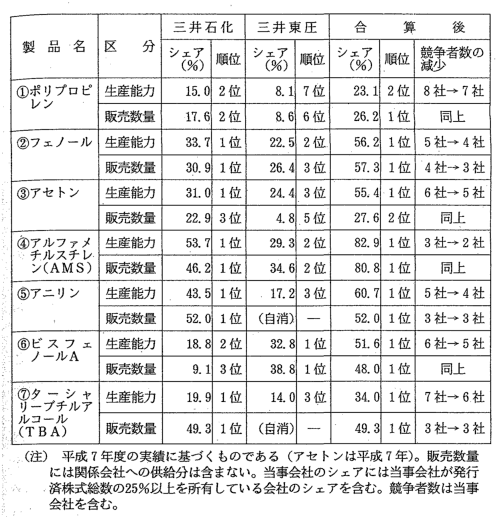| 1 |
日本紙業㈱と十條板紙㈱との合併(平成9年8月合併届出受理,10月合
併)(新会社名 日本板紙㈱) |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,紙,板紙が主体の製造販売業者である日本紙業㈱と板紙の製
造販売業者である十條板紙㈱が,厳しい経営環境に対処し,企業基盤の
一層の強化を図ること等を目的として合併しようとするものである。 |
| (2) |
一定の取引分野 |
|
紙,板紙については,一般的には,品種ごとに原料の配合割合,製造
方法,用途等が異なるため,各品種について一定の取引分野が成立する
と考えられる。
本件においては,合併により生産数量シェアが15%以上かつ第1位と
なる品種であって,いずれも「一定の取引分野」が成立するものと判断
される,外装用ライナー(ジュート)及び黄板紙チップボールのそれぞ
れの全国における製造・販売分野について重点的に検討を行った。 |
| (3) |
問 題 点 等 |
|
| ア |
問 題 点 |
|
| (ア) |
合併新会社の外装用ライナー(ジュート)の生産数量シェアが,
16.0%かつ第1位となるとともに,十條板紙㈱の親会社である日本
製紙㈱のグループ会社(25%超の株式所有関係にある会社)を含め
てみると20.9%かつ第1位となる。 |
| (イ) |
合併新会社の黄板紙チップボールの生産数量シェアが22.9%かつ
第1位となる。 |
|
| イ |
考慮事項 |
|
外装用ライナー(ジュート)及び黄板紙チップボールについては,
それぞれ有力な競争業者が存在する。 |
|
| (4) |
当委員会の判断 |
|
上記の点を総合的に勘案すると,本件合併は,直ちに一定の取引分野
における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断した。 |
|
| 2 |
三井石油化学工業㈱と三井東圧化学㈱との合併(平成9年7月合併届出
受理,10月合併)(新会社名 三井化学㈱) |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,石油化学品メーカーである三井石油化学工業㈱(以下「三井
石化」という。)と,総合化学品メーカーである三井東圧化学㈱(以下
「三井東圧」という。)が,海外展開におけるキャッシュフローの確
保,研究開発の強化等を目的として,合併しようとするものである。 |
| (2) |
一定の取引分野及び問題点 |
|
| ア |
両社の生産・販売する製品を製法,形状,特性,用途等の点から区
分し,そのうち競合関係があり生産能力又は販売数量のシェアを合算
すると15%以上かつ第1位となる次表の7品目(以下「7品目」とい
う。)について重点的に検討を行った。
7品目についてそれぞれ一定の取引分野を検討すると次のとおりで
ある。
ポリプロピレンについては,その用途において一部ポリエチレン,
ポリスチレン等の合成樹脂と部分的に代替関係があるが,それぞれ基
本的な物性や用途が異なる。
アセトンについては,その用途の25%を占める溶剤等の分野では酢
酸エチルやメチルエチルケトンと代替関係があるが,それぞれ価格や
基本的な特性が異なる。
フェノール,アニリン,ビスフェノールA及びTBAについては,
これらと直接に競合又は代替関係にある製品は見当たらない(フェ
ノールについてはクメン法とトルエン法,アニリンについてはニトロ
ベンゼン法とハルコン法という異なる製法があるが,製品の品質差や
価格差はない。)。
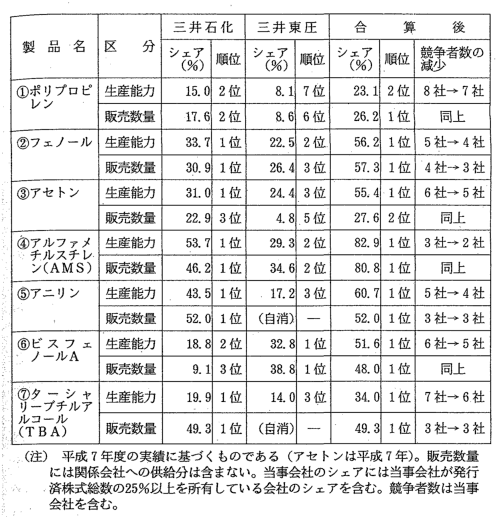
したがって,これら製品ごとに一定の取引分野が成立すると判断し
た。
AMSについては,その用途のほとんどを占めるABS樹脂の耐熱
向上剤の分野ではPMI(フェニルマレイミド)と代替関係があり,
PMIを含めた取引分野における競争についても検討する必要がある
と判断した。 |
| イ |
石油化学製品はエチレン等の基礎製品から誘導品までは1コンビ
ナートの中で流れており,一般的に,エチレン等を供給する石油化学
メーカーは,エチレン等から誘導品までを生産している。
このような中,両社の生産する石油化学製品は7品目以外にも重点
審査を行う対象とする選別基準に該当する品目が多数あり,本件の合
併によって,相互に関連性のある品目がより集積することとなって石
油化学工業における当事会社の総合的事業能力が拡大し,石油化学製
品それぞれにおける競争に影響を及ぼすことが考えられる。 |
|
| (3) |
考慮事項 |
|
| ア |
7品目に係る考慮事項は,次のとおりである。 |
|
| (ア) |
輸入品の存在 |
|
フェノールについては,メーカーによる品質の差はなく,ユー
ザーの使い慣れ等の問題もないこと,ロット・荷姿・運搬・保管の
面で問題が少なく,主なユーザーに輸入の経験があることから,
ユーザーは容易に輸入を増やすことができると考えられ,また,輸
入価格,輸出価格及び国内価格が近年ほぼ同水準で推移しており,
国内市場及び海外市場共通の価格形成が行われているとみられるこ
とからも,合併後の当事会社の販売シェアが高くても,国内市場に
おける価格や数量をコントロールする力はないとみられる。
フェノールの輸入比率は平成7年度で1.7%にすぎないが,国内
生産能力が低かった時期には輸入比率は現在よりも高かったことを
考慮すると,輸入比率の低さは,国内価格が海外価格とほぼ同水準
であり,かつ,現在は国内メーカーの供給余力があるため,わざわ
ざ輸入するまでもないことによるものとみられる。また,大手ユー
ザーの中には,国内メーカーとの価格交渉を有利に行う等の目的か
ら,輸入価格の方がある程度高くても輸入を維持する方針を採って
いるところもあった。
このほか,アセトン(輸入比率4.8%),アニリン(同8.2%)及
びビスフェノールA(同28.3%)についても,おおむね同様の事情
にあるとみられる。 |
| (イ) |
競争業者の存在 |
|
ポリプロピレンについては,生産能力シェアで第1位の競争業者
が販売数量シェアでも20%を超えており,このほか生産能力シェア
又は販売数量シェアで10%を超える競争業者がそれぞれ複数存在し
ている。
フェノールについては,近年,新日鐵化学㈱,三菱化学㈱(旧三
菱化成㈱)及び出光石油化学㈱が相次いで参入しており,生産能力
シェア及び販売数量シェアで20%を超える競争業者が存在してい
る。
アセトンについては,販売数量シェアで第1位で30%を超える競
争業者が存在し,このほか20%を超える競争業者が存在している。
アニリンについては,販売数量シェアで20%を超える競争業者が
存在し,その生産能力シェアは30%を超えている。
ビスフェノールAについても,近年新規参入が相次いでおり,当
事会社のシェアは年々低下している。
TBAについては,販売数量シェアで40%を超える競争業者が存
在している。 |
| (ウ) |
代替品の存在 |
|
AMSについては,ABS樹脂の耐熱向上剤の用途面で徐々にP
MIと置き換わっているとみられ,販売数量は年々低下している。 |
| (エ) |
ユーザーの意見 |
|
フェノールの大手ユーザー及び中小ユーザーは,いずれも海外価
格をみながら価格交渉を行っているとしており,本件合併により取
引数量・価格面で不利になることはないとしている。
アセトン,アニリン及びビスフェノールAについてもおおむね同
様の事情にあるとみられる。 |
| (オ) |
自己消費 |
|
アリニン及びTBAについては,三井東圧は生産量の全量を次工
程に投入しており出荷設備はなく,本件合併の国内市場に対する影
響は小さいとみられる。 |
|
| イ |
当事会社の総合的事業能力 |
|
石油化学工業の分野においては,その売上高及びエチレンの生産能
力シェアで第1位の三菱化学㈱のほか,他に有力な事業者が存在して
いる。 |
|
| (4) |
当委員会の判断 |
|
上記の点を総合的に勘案すると,本件合併によって,直ちにそれぞれ
の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと
判断した。
なお,今後,輸入を含めた競争環境を一層整備するため,特に集中度
が高い品目を中心に関税の早期引下げ・撤廃が図られることが望ましい
と考え,この旨関係当局に要望した。 |
|
| 3 |
三井東圧化学㈱及び住友化学工業㈱によるポリスチレン事業の統合 |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,三井東圧㈱と住友化学工業㈱が,コスト競争力の確保等を目
的として,平成9年10月を目途に両社が出資して設立する会社(日本ポ
リスチレン㈱。以下「合弁会社」という。)に両社のポリスチレン事業
を譲渡し,統合しようとするものである。
なお,三井東圧は同時に,三井石化との合併を予定している(事例2
参照)が,同社はポリスチレン事業を営んでいないので,本件では当
該合併とは別個に検討を行った。 |
| (2) |
一定の取引分野 |
|
ポリスチレンは,石油基礎製品であるエチレン及びベンゼンを原料に
して生産されるスチレンモノマーを重合(分子量の比較的小さい化合物
を結合させて大きな分子量の化合物とすること)して製造される。ポリ
スチレンには,一般成形用としての一般用ポリスチレン(以下
「GPPS」という。),耐衝撃性ポリスチレン(以下「HIPS」とい
う。)及び発泡用としての発泡ポリスチレン(以下「FSPS」とい
う。)とがある。
一般成形用のGPPS及びHIPSは,電気機器,一般機器,産業用
資材,包装資材,日用雑貨等に使用されているが,GPPSは,成形
性,加工性,透明性,電気絶縁性が良く,着色や発泡が容易であるとい
う特徴を持っており,一方,HIPSは,対衝撃性を高めるため,
GPPSにゴム分(ブタジエンゴム)を混入して製造され,ゴム含有量
の割合が多くなるほど耐衝撃性が高くなり,透明性が失われる。このよ
うに,GPPS及びHIPSは,その特性に差異が認められるが,各
メーカーはユーザーの要求する強度に対応した各種グレードを段階的に
製造していること,GPPSとHIPSとを併用して使用するユーザー
も少なくないこと及び各メーカーとも両者を取りそろえて製造している
状況にあることから,本件においては,ポリスチレンのうち,GPPS
及びHIPSを合わせた製造・販売分野に「一定の取引分野」が成立す
ると判断した。
なお,FSPSについては,GPPS及びHIPSとは用途が異なる
ことや本件の当事会社は生産していないことから本件で検討すべき一定
の取引分野には含まれないと判断した。 |
| (3) |
問 題 点 等 |
|
| ア |
問 題 点 |
|
本件事業統合により,GPPS及びHIPSの分野における販売数
量シェアは18.2%かつ第2位となり,生産能力でのシェアは15.5%か
つ第2位となる。
|
| イ |
考慮事項 |
|
| (ア) |
GPPS及びHIPSの製造・販売分野には,販売数量シェア,
生産能力シェアともに20%を超え第1位である競争業者が存在する
ほか,販売数量シェアで10%を超える競争業者,生産能力シェアで
10%を超える競争業者がそれぞれ複数存在している。 |
| (イ) |
合弁会社設立後,三井東圧は,販売数量シェア,生産能力シェア
ともに10%を超える競争業者とのポリスチレンの共同生産事業を解
消することとしている。また,本件合弁会社は,今後生産設備を削
減し生産能力を引き下げるとしており,その結果,GPPS及びH
IPSの生産能力シェアは,15.5%から12.3%(第2位から第5
位)に低下する。 |
|
|
| (4) |
当委員会の判断 |
|
上記の点を総合的に勘案すると,本件ポリスチレン事業統合は,直ち
に一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえ
ないと判断した。 |
|
| 4 |
エクソン・グループによるゼネラル石油㈱の株式取得 |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,米国のエネルギー関連総合会社であるエクソン・コーポレー
ション(以下「エクソン」という。)が,自己の子会社であるエッソ・
イースタン・インコーポレーテッド(米国法人。以下「エッソ・イース
タン」という。)及びエッソ石油㈱(日本法人。以下「エッソ石油」と
いう。)を通じて株式を所有しているゼネラル石油㈱(以下「ゼネラル
石油」という。)について,さらにエッソ・イースタンをして株式を追
加取得し,エクソン・グループとして50%超の株式を保有しようとする
ものである。 |
|
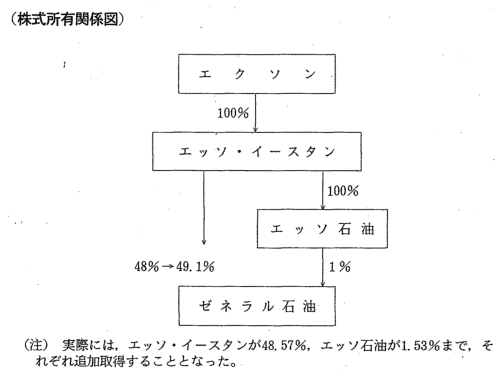 |
| (2) |
一定の取引分野 |
|
エッソ石油及びゼネラル石油は,全国で事業活動を行っている石油製
品の元売業者であり,通常,石油精製業者から仕入れて各地のガソリン
スタンド等の販売業者に販売している。石油製品は,揮発油,灯油,軽
油等の油種ごとに用途が異なる。
したがって,本件においては,全国及び各都道府県における石油製品
(揮発油,灯油,軽油及びC重油)の各々の元売分野に「一定の取引分
野」が成立すると判断した。 |
| (3) |
問 題 点 等 |
|
| ア |
問 題 点 |
|
| (ア) |
本件株式取得により,エッソ石油とゼネラル石油の沖縄県におけ
る石油製品の販売シェアを合計すると,揮発油で42.6%かつ第1
位,灯油で37.4%かつ第1位,軽油で36.6%かつ第1位,C重油で
58.8%かつ第1位となる。 |
| (イ) |
沖縄県においては,石油精製業者は2社しか存在しないところ,
そのうちの1社は ゼネラル石油がその株式の過半を所有する南西
石油㈱(以下「南西石油」という。)であるため,本件株式保有に
よりエッソ石油及びゼネラル石油が南西石油の経営を支配すること
ができるようになることから,他の元売業者の参入阻害につながる
おそれがある。 |
|
| イ |
考慮事項 |
|
| (ア) |
各石油製品の沖縄県における元売分野において,シェアが25%を
超える有力な競争業者がそれぞれ1社存在する。 |
| (イ) |
沖縄県の石油製品の元売分野に参入するためには,精製能力を持
たない元売業者等でも,県内の石油精製業者から商品を調達するこ
とができる。油槽所等の設備についても,県内の既存の元売業者の
備蓄設備を利用することが可能である。 |
| (ウ) |
沖縄県の石油元売業者のほとんどか同県の石油精製業者から石油
製品を仕入れて販売しており,当該石油精製業者は,親会社の石油
元売業者以外の有力な元売業者に対しても出荷している。 |
|
| ウ |
問題点の指摘 |
|
本件について,当委員会は,当事会社に対し,上記事項を考慮して
も,上記問題点のうち,南西石油の経営支配により他の元売業者の参
入阻害につながるおそれがある旨の指摘を行った。 |
| エ |
当事会社の対応 |
|
上記指摘に対し,ゼネラル石油からは,沖縄県の各石油製品の元売
分野における新規参入が制限されることのないよう,南西石油の取引
先の決定には関与しない等の措置を採る旨の申出があった。 |
|
| (4) |
当委員会の判断 |
|
上記の当事会社の措置等を総合的に勘案すると,本件株式取得は,直
ちに一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはい
えないと判断した。 |
|
| 5 |
林薬品㈱とオーク薬品㈱との合併(平成9年8月合併届出受理,10月合
併)(新会社名 ㈱エバルス) |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,中国地区において医薬品卸売業を営む林薬品㈱(山口県内に
おいては動物用医薬品のみ)とオーク薬品㈱が,経営体質の強化等を目
的として合併しようとするものである。 |
| (2) |
一定の取引分野 |
|
通常,医薬品卸売業者は,メーカーから商品を仕入れ,取引先医療機
関又は小売店から注文を受けて商品を納入しているため,受注活動及び
配送拠点として支店等を置いており,これら支店等の営業範囲が事業活
動の範囲と考えられる。当事会社は,おおむね中国地区内の各県ごとに
支店等を設置しているため,各県及び中国地区のそれぞれにおいて競争
が行われているとみられる。
また,医療用医薬品,一般用医薬品及び動物用医薬品では販売先が異
なる。
したがって,本件においては,当事会社の営業区域内である県及び地
域ブロックにおける医療用医薬品,一般用医薬品及び動物用医薬品の
各々の卸売分野に「一定の取引分野」が成立すると判断した。 |
| (3) |
問 題 点 等 |
|
| ア |
問 題 点 |
|
合併新会社のシェア等は,以下のとおりとなる。
| (ア) |
医療用医薬品について,営業区域内の各県(山口県を除く。以下
同じ。)及び中国地区において,いずれも販売シェアが2
5%以上
かつ第1位となるとともに,上位3社の販売シェアが50%超とな
る。 |
| (イ) |
一般用医薬品について,営業区域内の各県及び中国地区におい
て,いずれも販売シェアが25%以上かつ第1位となるとともに,上
位3社の販売シェアが50%超となる。 |
|
| イ |
考慮事項 |
|
| (ア) |
平成4年度以降,医薬品業界の取引慣行改善(仕切り価格の引下
げ等)により,卸売業者がメーカーから独立して事業活動を行う傾
向にあり,卸売業者は,さらに取扱商品及び営業区域を拡大して相
互参入が行われることが予想される。 |
| (イ) |
医療用医薬品については,卸売業者の医療機関に対する価格交渉
力は弱く,また,営業区域内の各県及び中国地区においてそれぞれ
有力な競争業者が存在する。 |
| (ウ) |
一般用医薬品については,営業区域内の各県及び中国地区におい
てそれぞれ有力な競争業者が存在することに加え,医薬品メーカー
の中には小売店に対し直接販売を行っている者が存在し,メーカー
直販分を加えて小売店向け医薬品販売分野として営業区域内の各県
及び中国地区における合併新会社の販売シェアをみると,ほぼ半分
又は半分以下に低下する。 |
|
|
| (4) |
当委員会の判断 |
|
上記の点を総合的に勘案すると,本件合併は,直ちに一定の取引分野
における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断した。 |
|
| 6 |
㈱富士銀行による安田信託銀行㈱の株式取得 |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,安田信託銀行㈱(以下「安田信託」という。)が財務体質を
強化するため,第三者割当て増資を行うこととし,この一部を㈱富士銀
行(以下「富士銀行」という。)が引き受けるに当たり,富士銀行は,
安田信託の株式を16.9%保有することになるため,あらかじめ当委員会
に対し第11条第1項ただし書の規定による認可申請を行ったものであ
る。 |
| (2) |
認可の考え方 |
|
第11条の規定においては銀行が他の会社の株式を5%を超えて保有
することは原則として禁止されており,例外として,あらかじめ同条第
1項ただし書の規定に基づき公正取引委員会の認可を受けた場合等が定
められている。この認可の基準に係る第11条ガイドラインによれば,金
融会社が他の金融会社の株式を保有する場合として,次の2つの場合に
該当しない限り,認可を行うこととされている。
| ① |
第9条ガイドラインにおける「事業支配力が過度に集中すること」
の考え方に照らし,認可申請会社,株式発行会社及び認可申請会社が
株式の所有により事業活動を実質的に支配している国内の会社の事業
支配力が過度に集中することとなること。 |
| ② |
申請会社又は株式発行会社の株式保有により一定の取引分野におけ
る競争を実質的に制限することとなること。 |
本件の株式取得については,上記①又は②に該当するかどうかについ
て次のとおり検討を行った。
| ア |
事業支配力の過度の集中について |
|
第9条ガイドラインにおいては,事業支配力が過度に集中すること
となる場合として3つの類型を禁止類型として挙げているが,本件株
式所有比率からみて,株式発行会社(安田信託)は認可申請会社(富
士銀行)の子会社又は事業活動を実質的に支配している会社であると
はいえないので,この要件は問題とならない。 |
| イ |
一定の取引分野における競争の実質的制限 |
|
富士銀行と安田信託はその子会社も含めてみた場合には,貸出,預
金及び信託の各分野で競合関係に立つものであるが,これら当事会社
全体でみた場合のシェアが比較的高いものではないこと等を踏まえる
と,本件株式取得により一定の取引分野における競争を実質的に制限
することとなるとはいえないと判断した。 |
|
| (3) |
当委員会の判断 |
|
上記の点を総合的に判断すると,本件株式取得については,第11条第
1項ただし書の規定に基づいて認可するのが相当であると判断した。 |
|
| 7 |
㈱三和銀行による山一證券投資信託委託㈱の株式取得 |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,山一證券投資信託委託㈱(現パートナーズ投信㈱)(以下
「山一證券投資信託委託」という。)の株主であった山一證券㈱の廃業
に伴い,同社及びその関連会社が山一證券投資信託委託の株式を売却す
ることとなり,当該株式を㈱三和銀行(以下「三和銀行」という。)が
引き受けるに当たり,三和銀行は,山一證券投資信託委託の株式を49.3
%保有することになるため,あらかじめ当委員会に対し第11条第1項た
だし書の規定による認可申請を行ったものである。 |
| (2) |
認可の考え方 |
|
本件は,銀行が他の会社の株式を5%を超えて保有する場合であり,
事例6で述べたとおり,第11条第1項ただし書の規定に基づく当委員会
による事前の認可が必要となる。
山一證券投資信託委託は,投資信託委託業及び投資顧問業を営むもの
であり,投資信託委託業及び投資顧問業は金融業ではないが,金融資産
運用サービスを顧客に提供するという点で取引形態が金融取引に類似し
ている業務といえる。
したがって,本件については,第11条ガイドラインにおいて認可類型
に掲げられたもののうち,株式発行会社が金融会社固有の業務に準ずる
業務を営む会社である場合に該当するため,次の2つの場合に該当しな
い限り,認可を行うこととなる。
| ① |
第9条ガイドラインにおける「事業支配力が過度に集中すること」
の考え方に照らし,認可申請会社,株式発行会社及び認可申請会社が
株式の所有により事業活動を実質的に支配している国内の会社の事業
支配力が過度に集中することとなること。 |
| ② |
申請会社又は株式発行会社の株式保有により一定の取引分野におけ
る競争を実質的に制限することとなること。 |
本件の株式取得については,上記①又は②に該当するかどうかについ
て次のとおり検討を行った。
| ア |
事業支配力の過度の集中について |
|
第9条ガイドラインにおいては,事業支配力が過度に集中すること
となる場合として3つの類型を禁止類型として挙げている。三和銀行
による山一證券投資信託委託の株式所有比率は49.3%となる予定であ
り,山一證券投資信託委託は三和銀行の子会社ではないが,三和銀行
が実質的に支配している国内の会社に該当するものであり,また,三
和銀行は,100%出資子会社として三和証券㈱及び三和信託銀行㈱の
金融会社並びに三和銀行の従属業務を営む子会社を所有しており,こ
れらの会社について禁止される3つの類型に該当するかどうかについ
て検討した。
第1類型に関しては,単体総資産の額が3000億円を超える会社が2
社のみであること,第2類型に関しては,金融又は金融と密接に関連
する業務を営む会社以外の大規模な会社が存在しないこと及び第3類
型に関しては,個々の事業分野において売上高のシェアが10%以上又
は上位3位となる会社が存在しないことから,禁止されている3つの
類型には該当しないため,本件株式取得により事業支配力が過度に集
中することとはならないと判断した。 |
| イ |
一定の取引分野における競争の実質的制限 |
|
三和銀行と山一證券投資信託委託は競合関係に立つものではないこ
となどから,本件株式取得により一定の取引分野における競争を実質
的に制限することとなるとはいえないと判断した。 |
|
| (3) |
当委員会の判断 |
|
上記の点を総合的に判断すると,本件株式取得については,第11条第
1項ただし書の規定に基づいて認可するのが相当であると判断した。 |
|
| 8 |
大山証券㈱と日ノ丸証券㈱との合併(平成9年8月合併届出受理,10月
合併)(新会社名 大山日ノ丸証券㈱) |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,鳥取県内の証券会社である大山証券㈱と日ノ丸証券㈱とが,
今後実施される株式委託手数料の自由化など金融制度改革を控え,経営
基盤の強化と合理化を図るために合併しようとするものである。 |
| (2) |
一定の取引分野 |
|
証券取引法第28条は,大蔵大臣の免許を受けた株式会社でなければ証
券業務を営んではならないとしている。同法第28条の規定に基づく免許
は,業務別に,
| ア |
有価証券の売買を行うディーラー業務(同条第2項第1号) |
| イ |
有価証券の売買の媒介,取次ぎ,代理等を行うブローカー業務(同
項第2号) |
| ウ |
有価証券の引受け及び売出しを行うアンダーライター業務(同項第
3号) |
| エ |
有価証券の募集及び売出しの取扱いを行うセリング業務(同項第4
号) |
に分けられており,両当事会社は,ア,イ及びエの免許を有している。
このうちアについては,証券会社の自己売買であるのに対し,イ及びエ
については,顧客の売買を取り次ぐといった違いが存在する。顧客は証
券会社で口座を開設しなければならない。また,株式,公社債及び投資
信託は,それぞれ元本の安全性,収益の確実さ,換金の容易さ等商品の
性格が異なり,顧客はこれらを区別して取引を行っていると考えられ
る。
したがって,本件については,両当事会社の店舗設置状況等から,鳥
取県における株式,公社債及び投資信託それぞれのイ及びエに係る取引
について「一定の取引分野」が成立すると判断した。 |
| (3) |
問題点等 |
|
| ア |
問 題 点 |
|
合併新会社の鳥取県における上記(2)イ及びエに係る株式売買高の
シェアが38.6%かつ第1位となる。 |
| イ |
考慮事項 |
|
鳥取県においては,全国展開している大手証券会社3社が店舗を設
けて上記(2)のア~エのすべての免許を有して営業活動を行っており,
鳥取県におけるこれら3社の株式売買のシェアは,それぞれ10%ない
し20%を超え,有力な競争業者であるといえる。 |
|
| (4) |
当委員会の判断 |
|
上記の点を総合的に勘案すると,本件合併は,直ちに一定の取引分野
における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断した。 |
|
| 9 |
A社ほか3社によるX製品に係る共同生産会社の設立 |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,X製品の有力な販売業者であるA社及びその子会社でありX
製品の製造業者であるB社が,0地区におけるX製品の生産について,
当該地区においてX製品を製造販売しているC社及びD社とともに,X
製品の共同生産会社を設立しようとするものである。
なお,C社及びD社は,0地区においてX製品の原料供給元であるE
社が工場閉鎖のため原料の供給を受けられなくなることから,本件共同、
生産会社を設立しようとするものであり,これに伴いX製品の生産から
撤退する。 |
| (2) |
一定の取引分野 |
|
X製品にはその商品特性から販売地域に限界があることから,本件に
おいては,0地区におけるX製品の製造・販売分野に「一定の取引分
野」が成立するものと判断した。 |
| (3) |
問題点等 |
|
| ア |
問 題 点 |
|
| (ア) |
出資会社各社のX製品の販売合算シェアは88.8%となる。 |
| (イ) |
本件共同生産会社の設立により,A社(及びB社)とその競争業
者であるC社及びD社との間の結合関係がそれぞれ形成又は強化さ
れることとなり,それぞれの会社間に協調関係が醸成されやすくな
る。 |
| (ウ) |
出資会社各社が共同生産会社の製造するX製品の引取数量をあら
かじめ定めることとなる。 |
|
| イ |
考慮事項 |
|
| (ア) |
X製品については,近年,ユーザーが自社生産を行う傾向が強
まっていることから,メーカーが大幅な値上げを行うことは困難で
ある。 |
| (イ) |
C社及びD社は,X製品の原料の供給を受けられなくなることか
ら,X製品の生産から撤退する。 |
| (ウ) |
X製品は他の関連商品と合わせて顧客に販売されており,本件共
同生産会社が設立されない場合,関連商品を含めた市場におけるC
社及びD社の競争力が減退する。 |
| (エ) |
出資会社各社は,独自にX製品の販売を行う。 |
|
| ウ |
問題となり得る点についての指摘 |
|
本件について,当委員会は,当事会社に対し,本件当事会社の合算
シェア,市場の状況等を考慮し,本件行為によって当事会社はX製品
の価格・数量をコントロールする力を強化することとなり,一定の取
引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の
指摘を行った。 |
| エ |
当事会社の対応 |
|
上記指摘に対し,当事会社からは,本件行為を行わない旨の申出が
あった。 |
|
|
| 10 |
F社によるG社への役員派遣等 |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,Y製品の有力な製造・販売業者であるF社が,競争の激化に
より経営が悪化した同業者G社の再建・安定化を図るため,同社に役員
2名を派遣したものである。
なお,F社は,G社の発行済株式総数の約30%(株主順位第2位)の
株式を保有している。 |
| (2) |
一定の取引分野 |
|
F社及びG社の取扱商品はY製品であり,Y製品には特に代替関係に
ある商品が存在しないことから,本件においては,Y製品の国内におけ
る製造・販売分野に「一定の取引分野」が成立するものと判断した。 |
| (3) |
問題点等 |
|
| ア |
問 題 点 |
|
F社は,G社の発行済株式総数の約30%の株式を保有していること
に加えて,G社に2名の役員を派遣することになったことから,F社
とG社の間に結合関係が認められるが,F社とG社を合算したY製品
の販売シェアは約60%となり,第2位の事業者のシェア(約20%)を
大きく上回ることとなる。 |
| イ |
考慮事項 |
|
| (ア) |
当該役員派遣及び株式所有は,G社からの要請によるものであ
る。 |
| (イ) |
Y製品の市場は,停滞傾向が続いており,G社の平成8年3月期
の決算では相当額の赤字となっている。 |
|
| ウ |
問題となり得る点についての指摘 |
|
本件について,当委員会は,当事会社に対し,F社が,G社に役員
を派遣し,同社の発行済株式総数の約30%に相当する株式を保有する
ことによりF社とG社の間に結合関係が生じており,Y製品の製造・
販売分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨
の指摘を行った。 |
| エ |
当事会社の対応 |
|
上記の指摘に対して,当事会社からは,役員兼任関係を解消する旨
及びF社がG社の株式所有割合を発行済株式総数の25%未満とする旨
の申出があった。 |
|
|
| 11 |
H県中央卸売市場に入場予定のZ商品卸売業者の合併 |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,H県中央卸売市場Z商品部が新設されることに伴い,同県に
おいてZ商品卸売業を営む2社が合併し,同市場に卸売業者として単独
で入場しようとするものである。 |
| (2) |
一定の取引分野 |
|
当事会社2社から仕入れを行っている小売買参人の所在地は県内全域
に及んでいること及び県内には他の地方卸売市場がないことから,H県
全域におけるZ商品卸売分野に「一定の取引分野」が成立するものと判
断した。 |
| (3) |
本件の問題点等 |
|
| ア |
問 題 点 |
|
本件行為により合併新会社のシェアは,約85%かつ第1位となり,
他に有力な卸売業者かない。 |
| イ |
問題となり得る点についての指摘 |
|
本件について,当委員会は,当事会社に対し,H県のZ商品卸売分
野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の指摘
を行った。 |
| ウ |
当事会社の対応 |
|
上記指摘に対し,当事会社からは,本件行為を行わない旨の申出が
あった。 |
|
|
| 12 |
金融会社J社による製造・販売業者K社の株式取得 |
|
| (1) |
本件の概要 |
|
本件は,製造・販売業者K社が事業再構築を行うに際し,増資を企図
したことに対し,金融会社であるJ社は増資の引受けを検討したとこ
ろ,J社はK社の株式をその発行済株式総数の5%を超えて保有するこ
とになるため,J社はあらかじめ当委員会に対し第11条第1項ただし書
の規定による認可申請を行おうとするものである。
なお,J社は,増資引受けはK社の事業再構築を支援するための一時
的なものであり,再構築後の事業が軌道に乗り次第,第11条の制限を超
える部分の株式を売却する予定であるとしている。 |
| (2) |
認可の考え方等 |
|
| ア |
第11条第1項ただし書の認可については,第11条ガイドラインに
従って行うこととしている。これによれば,本件の場合は,従属業務
子会社,金融会社等のいずれの認可類型にも該当しない株式保有であ
るため,①申請会社による株式取得の必要性,②当該株式保有による
申請会社の事業支配力増大のおそれの有無及びその程度並びに③株式
発行会社の属する市場における競争への影響の3点を考慮して認可の
可否を決定することとなる。 |
| イ |
当委員会は,本件について,J社の増資引受けが不可欠である特別
な事情が存在するわけではないこと,株式保有は暫定的なものである
予定とはいえ,K社は金融業以外の事業活動を営んでおり,K社の規
模からみて当該株式保有によるJ社の事業支配力増大のおそれが強い
とみられることから,認可するに足る合理的な理由があるとは認めら
れないと判断し,この旨当事会社に対して指摘を行った。 |
| ウ |
当事会社の対応 |
|
上記指摘に対し,当事会社からは,本件行為を行わない旨の申出が
あった。 |
|
|