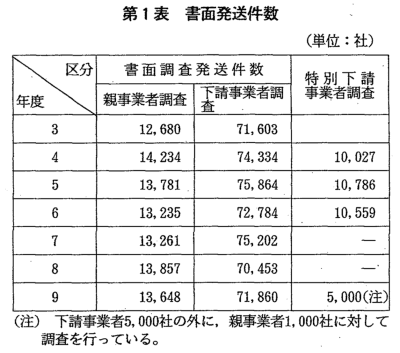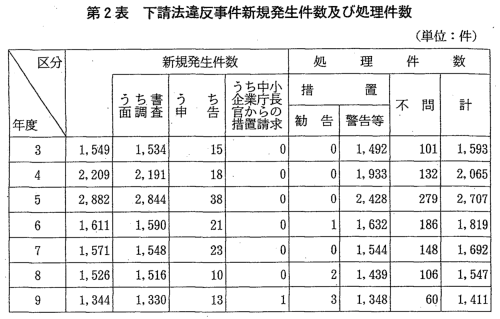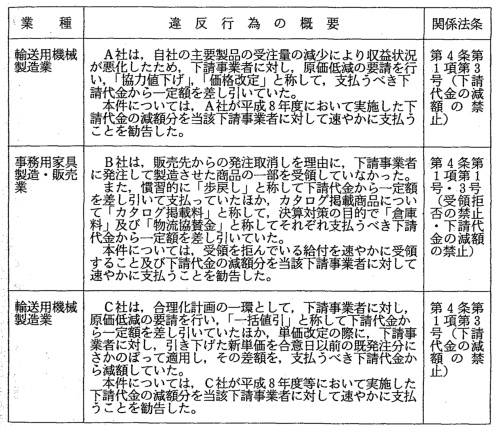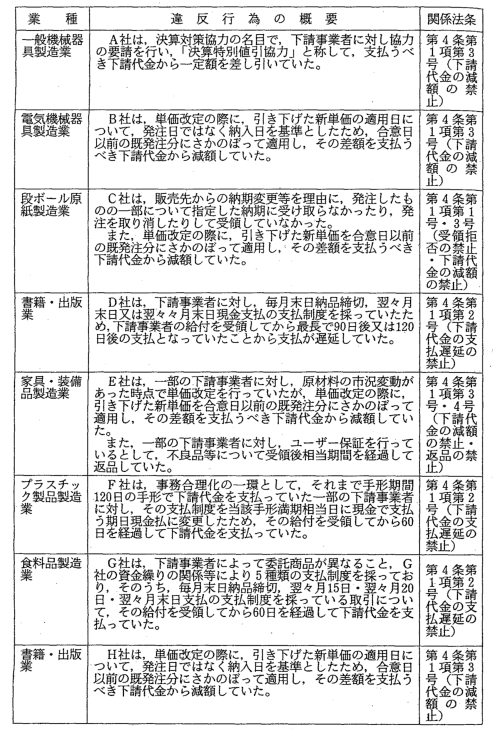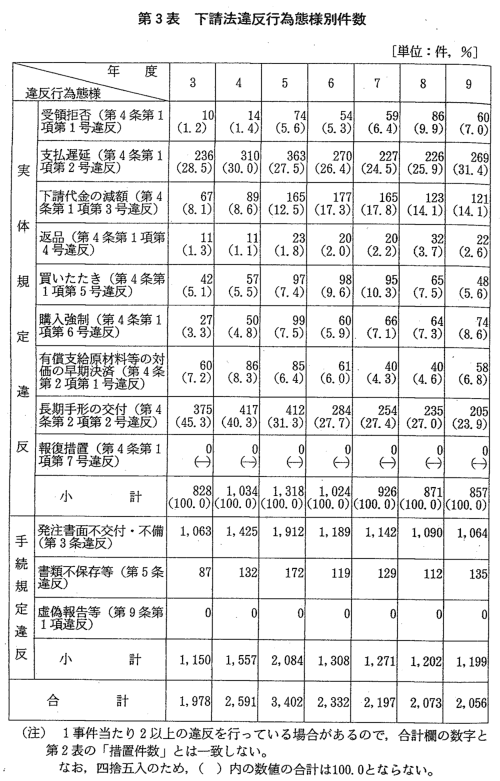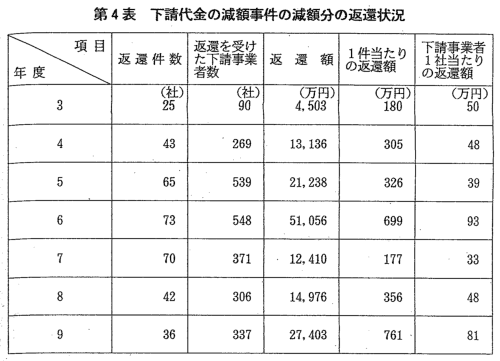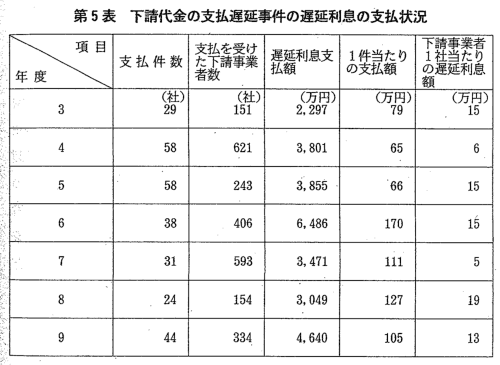第13章 下請法に関する業務
第1 概 説
下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等
の濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図
るとともに下請事業者の利益を保護することを目的として,独占禁止法にお
ける不公正な取引方法の規制の特別法として昭和31年に制定された。
下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1000万円を超え1億円
以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1000万円以下の事業者(下請事
業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業者へ
の発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2
年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した給付
の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2号),
③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いたたき(同
項第5号),⑥物品等の購入強制(同項第6号),⑦有償支給原材料等の対価
の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2号)
などの行為を行った場合には,当委員会は,その親事業者に対し,当該行為
を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告
する旨を定めている。
第2 違反被疑事件の処理
下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申
告が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として
製造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定
期的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実
施することにより,違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,附属資料10-1表及び10-2表)。
| 1 |
書面調査 |
|
平成9年度においては,資本金3000万円以上の主として製造業者12,648
社及び資本金1000万円超3000万円未満の製造業者1,000社の合計13,648社
に対して書面調査を実施した。また,資本金3000万円以上の親事業者と取
引している下請事業者のほぼ4分の1に相当する71,860社を対象に書面調
査を実施した。
さらに,平成9年度においては,これら定期的な調査に加え,消費税率
の引上げ及び地方消費税の導入に伴い,下請取引において消費税等の円滑
かつ適正な転嫁が行われているかどうかの実態を把握するため,親事業者
1,000社及び下請事業者5,000社に対して,特別に書面による調査を行った
(第1表)。
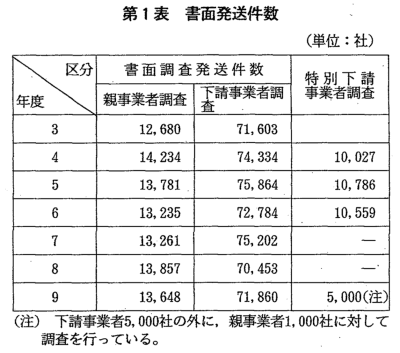
|
| 2 |
違反事件の新規発生件数及び処理件数 |
|
| (1) |
平成9年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は1,344件
である。このうち,書面調査により職権探知したものは1,330件であり,
下請事業者からの申告によるものは13件(新規発生件数全体の1.0%),
下請法第6条の規定に基づく中小企業庁長官からの措置請求は1件で
あった(第2表)。 |
| (2) |
平成9年度において,当委員会が下請法違反被疑義件を処理した件数
は1,411件であり,このうち,1,351件(95.8%)について違反行為又は
違反のおそれのある行為が認められたため,3件について同法第7条第
2項の規定に基づき勧告を行い,1,348件について警告の措置を採った
(第2表)。
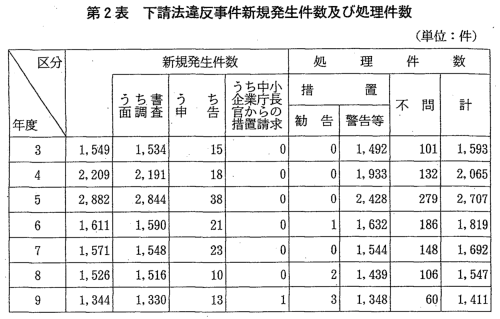
また,下請法違反を行った親事業者に対しては,違反行為の再発防止
のために,社内研修,監査等により社内体制を整備するよう指導した。 |
|
| 3 |
違反行為態様別件数 |
|
平成9年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別にみる
と,手続規定違反が1,199件(違反件数全体の58.3%)となっている。こ
のうち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付してい
ない,又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が
1,064件(同51.8%)となっている。
また,実体規定違反は,857件(違反件数全体の41.7%)となってお
り,このうち,下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号違反)が269件
(実体規定違反件数全体の31.4%),手形期間が120日(繊維業の場合は90
日)を超える長期手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号違
反)が205件(同23.9%),下請代金の減額(第4条第1項第3号違反)が
121件(同14.1%),購入強制(第4条第1項第6号違反)が74件(同8.6%)
となっている(第3表)。
下請代金の減額事件については,平成9年度中に,親事業者36社により
総額2億7403万円が337社の下請事業者に返還されており(第4表),支払
遅延が認められた事件については,親事業者44社により総額4640万円の遅
延利息が334社の下請事業者に支払われている(第5表)。 |
| 4 |
勧告又は警告を行った違反事例 |
|
平成9年度に勧告又は警告を行った事件のうち,主なものは次のとおり
である。
| (1) |
勧告の事例 |
|
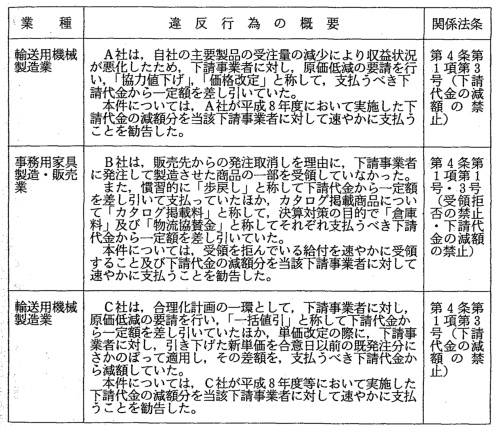
|
| (2) |
警告を行った主な違反事例 |
|
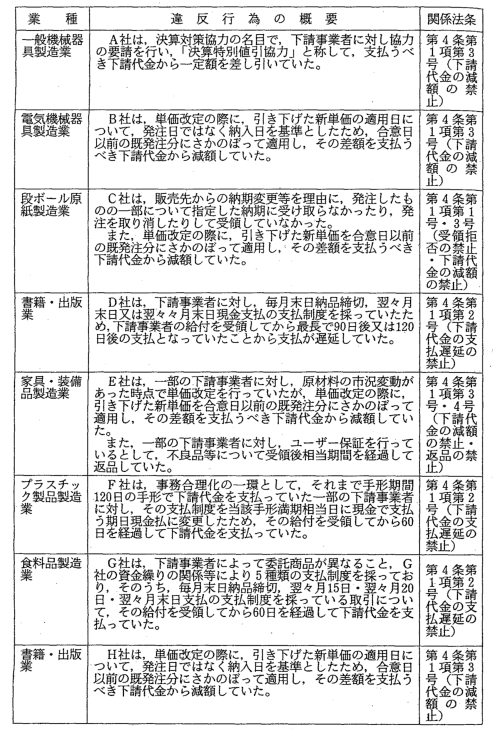 |
|
| 5 |
下請取引における消費税率の引上げ等の状況に関する調査について |
|
平成9年4月1日から消費税率の引上げ及び地方消費税の導入が行われ
た中で,下請取引において消費税等の円滑かつ適正な転嫁が行われている
かどうかの実態を把握し,親事業者が下請法に違反して,消費税率の引上
げ(消費税率の引上げと地方消費税の導入により,消費税と地方消費税を
合わせた税率が5%となることをいう。以下同じ。)分相当額の負担を下
請事業者に不当にしわ寄せをしていないかどうかを監視するため,平成9
年5月から6月にかけて,親事業者1,000社及び下請事業者5,000社を対象
に特別に書面調査を実施した。
調査の結果,消費税率の引上げ前の下請代金と比較した場合,親事業者
のほとんど(親事業者調査96.8%,下請事業者調査94.6%)が消費税率引
上げ分相当額を上乗せして支払っているものと認められた。これらの中に
は,従来の単価を引き下げた上で消費税率引上げ分相当額を上乗せしてい
るものもみられたが,単価引下げに当たり,消費税率引上げ分相当額を引
き下げることを理由としたものはほとんどみられなかった。
しかしながら,親事業者のごく一部にではあるが,「すべての製品につ
いて,消費税率の引上げ分相当額を上乗せした下請代金を支払っていな
い」等,下請法に違反するおそれのある行為が行われている疑いがみられ
た。これらの行為については,個別に事実確認を行い,下請法上の問題が
認められたものについては,所要の措置を講じた。 |
|
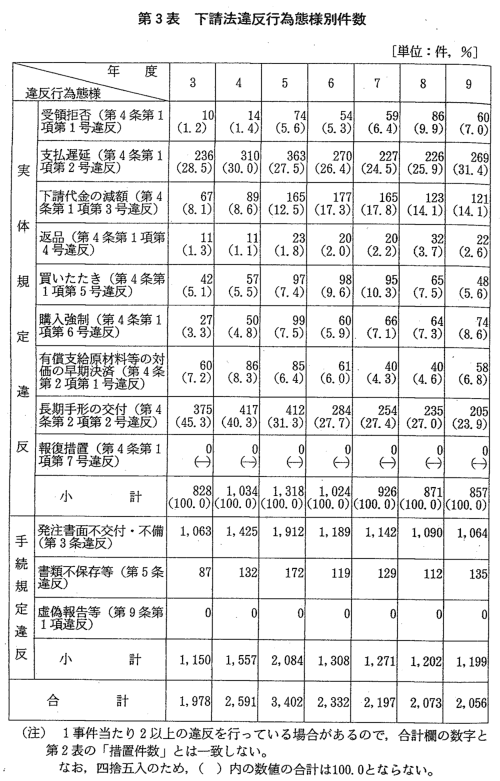
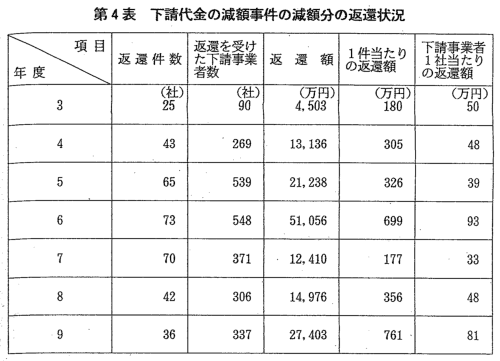
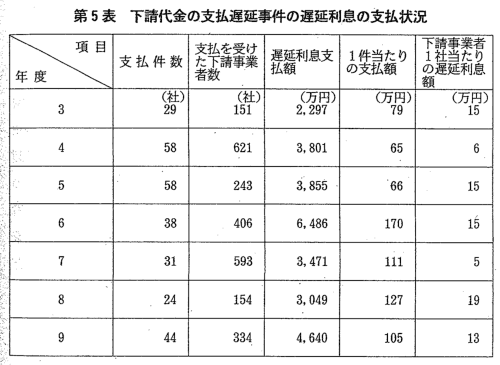
|
第3 下請代金の支払状況等
当委員会は,定期親事業者調査により報告された結果を基に,昭和33年
度以降,毎年,下請代金の支払状況等を取りまとめ,これを公表している。
平成9年度において親事業者調査の対象とした資本金3000万円以上の製造業
者等について,その下請取引の概要及び下請代金の支払状況をみると,次の
とおりである。
| 1 |
下請取引の実態 |
|
| (1) |
下請取引をしている割合 |
|
| ア |
下請取引をしている事業者の割合は72.4%であった。 |
| イ |
下請取引をしている事業者の割合を業種別にみると,「一般機械器
具製造業」(93.1%),「輸送用機械器具製造業」(92.6%),「電気機械
器具製造業」(91.8%)及び「精密機械器具製造業」(90.6%)におい
て9割を超えているが,「窯業・土石製品製造業」(341%)及び「木
材・木製品製造業(家具を除く)」(35.8%)などの業種ではその割合
は低い。 |
|
| (2) |
取引先下請事業者数 |
|
| ア |
親事業者の1事業所当たり取引先下請事業者の数は29社である。 |
| イ |
1事業所当たりの取引先下請事業者の数を業種別にみると,「精密
機械器具製造業」(1事業所当たり58社),「出版・印刷・同関連産
業」(同47社),「電気機械器具製造業」(同47社),「輸送用機械器具製
造業」(同44社)であり,概して下請取引をしている事業者の割合の
高い業種では取引先下請事業者数も多く,下請取引をしている事業者
の割合の低い「食料品製造業」(同7社),「木材・木製品製造業(家
具を除く)」(同9社),「飲料・飼料・たばこ製造業」(同10社)など
では,取引先下請事業者数も少ない傾向にある。 |
|
|
| 2 |
下請代金の支払状況等 |
|
| (1) |
支払期間 |
|
| ア |
納品締切日から支払日までの月数(以下「支払期間」という。)を
事業所ごとにみたものの平均は0.84か月(25.2日)となっており,総
体としてみると,納品締切日を月末とした場合,下請代金は翌月26日
までには支払われているということになる(附属資料10-4表)。 |
| イ |
支払期間が1か月を超えるもの(この場合は,納品されてからその
代金が支払われるまでの期間が608を超えることがあるので,下請法
第4条第1項第2号の規定に違反するおそれがあるものである。)
は,4.1%である(附属資料10-4表)。
なお,これらのケースはすべて違反被疑事件として調査の対象とし
ている。 |
|
| (2) |
現金支払割合 |
|
下請代金のうち,現金で支払われる割合(以下「現金支払割合」とい
う。)を親事業者の事業所ごとにみたものの平均は59.3%であり,総体
としてみると,下請代金の約60%は現金で支払われているということに
なる(附属資料10-4表)。 |
| (3) |
手形期間 |
|
下請代金を手形により支払っている場合の手形期間(親事業者の各事
業所が交付した手形のうち,最も期間が長い手形の手形期間について集
計)をみると,以下のとおりである(附属資料10-4表)。
「手形期間が90日以下のもの」 21.2%
「手形期間が90日超120日以下のもの」 67.2%
「手形期間120日超のもの」 11.6%
なお,「手形期間120日超のもの」は違反被疑事件として調査の対象と
している。 |
|
| 3 |
下請代金の支払状況の推移 |
|
下請代金の支払状況の推移をみると次のとおりであり,長期的には昭和
40年代以降,徐々に改善されてきている。 |
|
| (1) |
支払期間は,昭和30年代は1.0か月(締切日から30日)を超えていた
が,昭和40年代に入ると大幅に改善され,昭和50年代以降は0.8か月
(締切日から24日)前後で推移している(附属資料10-5表)。 |
| (2) |
現金支払割合は,昭和40年代前半までは低下傾向にあったが,昭和40
年代後半から徐々に高くなっており,近年は60%程度が現金で支払われ
る状態が定着している(附属資料10-7表)。 |
| (3) |
120日を超える手形を交付している事業所の割合は,昭和40年代前半
までは増加傾向にあったが,昭和45年度の約60%をピークに,それ以降
は減少傾向にあり,昭和56年度以降は20%前後となっている。特に平成
2年度以降は20%を下回る状態が続いている(附属資料10-6表)。 |
|
第4 下請法の普及・啓発等
| 1 |
違反行為の未然防止及び再発防止の指導 |
|
下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効
果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止するこ
とも肝要である。この観点から,以下のとおり各種の施策を実施し,違反行
為の未然防止を図っている。 |
|
| (1) |
下請取引適正化推進月間 |
|
毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中小企業庁と共同し
て,新聞,雑誌,テレビ,ラジオ等で広報活動を行うほか,全国各地に
おいて下請法に関する講習会を開催する等下請法の普及・啓発に努めて
いる。
平成9年度は,親事業者を対象に31都道府県(うち当委員会主催分18
都道府県〔18会場〕)において講習会を開催した(受講者は当委員会主
催分1,725名)。
また,当委員会は,下請取引を適正化するためには,取引のもう一方
の当事者である下請事業者にも下請法の趣旨内容を周知徹底する必要が
あることにかんがみ,昭和60年度以降,下請事業者を対象とした下請法
講習会を実施しており,平成9年度において11道県(11会場)で開催し
た(受講者数606名)。 |
| (2) |
下請法遵守の要請 |
|
最近の我が国経済は,景気は緩慢な動きを示し,景気の先行きに対し
て急速に不透明感が広がり,楽観を許さない状況となっている。特に中
小企業の景況は低迷しており,大企業との格差が広がっている。さらに,
年末の金融繁忙期においては下請中小企業の資金繰り等が悪化すること
が懸念されるため,平成9年12月12日,公正取引委員会委員長・通商産
業大臣連名で資本金1億円以上の親事業者約8,750社に対し下請法の遵
守を要請し,同時に関係約400団体に対し,傘下事業者への下請法の周
知徹底等を要請した。 |
| (3) |
下請法運用協力団体との連携 |
|
各業種における親事業者又は下請事業者の団体を下請法運用協力団体
として登録(平成10年3月末現在99団体)し,協力団体に対し下請法に
ついての説明会を開催したり,協力団体又は傘下の事業者が下請法遵守
マニュアルの作成等を行う際に当委員会が資料提供等の便宜を図ること
で,下請法違反行為の未然防止に役立てることとしている。
平成9年度においては,平成9年9月に下請法運用協力団体会議を開
催し,意見交換等を行った。 |
| (4) |
広報,相談・指導業務 |
|
購買・外注担当者らに対する社内研修の実施及び購買・外注担当者向
けの下請法に関する遵守マニュアルの作成を積極的に指導したほか,関
係団体等の研修会に講師の派遣,資料の提供等を行い,下請法の普及・
啓発を行った。 |
|
| 2 |
都道府県との相互協力体制 |
|
下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利
益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と
の協力が必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関する
都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及・啓発等の業務につ
いて協力を得ている。
平成9年度においては,平成9年7月に都道府県下請企業行政担当課長
会議を開催した。 |
| 3 |
下請取引改善協力委員 |
|
下請法の的確な運用に資するため,昭和4
0年度以降,当委員会の業務
に協力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している。平成9年
度における下請取引改善協力委員は101名である。
平成9年度においては,平成9年6月に全国会議を,平成10年3月にブ
ロック別会議をそれぞれ開催し,最近の下請取引の状況について意見を交
換した。 |
第5 下請法の運用上の問題に関する企業取引研究会における検討
当委員会は,下請法が制定されて40年が経過し,下請取引をめぐる経済環
境が大きく変化してきていることに対応して,下請取引の公正化と下請事業
者の利益の保護という下請法の目的に照らして適切な運用に資するため,平
成9年5月以降,企業取引研究会(座長 佐藤芳雄 豊橋創造大学学長・慶
應義塾大学名誉教授(当時))を開催し,同研究会において,下請法の運用
上の問題点及び対応策の検討を行い,同研究会の検討結果を取りまとめた報
告書「下請法の運用上の問題と今後の見直しの方向」を平成10年6月に公
表した。その概要は以下のとおりである。
| 1 |
下請取引をめぐる経済環境の変化 |
|
技術革新の進展や,経済のソフト化,情報化及び国際化の進展等による
経済環境の変化を背景として,親事業者は外注先の技術開発力等を重視し
て選別を進めるようになり,下請事業者に対する要求も多様化・高度化し
てきている。一方,下請事業者の側では,技術開発力・企画提案力のある
事業者とそうでない事業者の二極分化が進行しつつあるといわれており,
「下請け」ではなく親事業者の事業活動に「協力」しているという意識も
強くなっている。
このように下請取引関係は,最近では専門的・効率的な生産に関する社
会的分業の一形態ととらえられるようになっている。しかし,これは,従
前の特定の親事業者と下請事業者との支配・従属関係が消滅したというも
のではない。 |
| 2 |
下請法の現在の運用についての評価 |
|
| (1) |
下請法が親事業者に対し発注書面の交付とその記載どおりの取引条件
の履行を義務付けていることは,下請問題の解決に役立ち,下請事業者
の経営の安定化と企業としての成長に貢献してきただけでなく,製造業
における分業構造を専門化・効率化させることを通じて我が国製造業の
発展にも一定の貢献をしてきたものと評価できる。 |
| (2) |
発注書面の交付とその記載どおりの取引条件の履行を求めるという規
制の仕組みを維持することは下請取引を公正化するために重要である
が,このような規制の目的は,発注書面の交付自体ではなく,取引当事
者間の合意により取引条件を設定させるとともに,その合意された取引
条件を証拠化することにあるので,事前に合意された基本契約書等の書
面により取引条件が証拠化されている場合には,発注書面に記載がある
場合と同様の取扱いをしても差し支えないものと考えられる。
また,当委員会では,下請法第4条のうち受領拒否,支払遅延など親
事業者と下請事業者との間で取り決められた取引条件の履行に係る規定
については,事件処理の迅速化等の観点から,できるだけ形式的かつ画
一的な判断の下に運用を行っているが,発注書面の記載のみを重視して
下請法の運用をあまりに形式的・画一的に行うことは,下請事業者の受
注機会を減少させるなど,かえって下請事業者の利益を損なうおそれが
あると考えられる。
さらに,取引条件を事後的に変更することは下請事業者の利益を損な
うものであり,一般的に認められるものではないが,取引条件の事後的
な変更によって下請事業者が受ける影響は,価格,納期等の取引条件ご
とに異なるものであり,納期等については,上記の場合と同様に,合意
の下に事後的に変更したとしても,取引条件の履行に係る規定の趣旨に
反しないこともあると考えられる。 |
| (3) |
取引条件が不当なものであるか否かの判断は,各国の市場の相互依存
関係を含む市場における競争関係を踏まえて,個別具体的な取引関係に
即して行う必要があるが,取引条件の設定行為について個別具体的に違
反事実を認定した上で規制を行うことは,迅速な事案処理が困難となっ
たり,取引関係を損なうおそれがあることなどから,必ずしも適当では
ないと考えられる。
このため,当委員会としては,下請法第4条のうち買いたたきなど取
引条件の設定行為に係る規定については,違反行為の未然防止を重視し
た連用方針を継続することが適当であるが,違反行為の未然防止を図る
上でも,影響の大きい事案にあっては,勧告を行うこととすべきと考え
られる。 |
| (4) |
下請法違反行為の内容が独占禁止法上も問題となるおそれがあるよう
な場合に,資本金区分の差異により下請法の対象とならない事業者に対
する行為については是正が求められないときは,下請取引の公正化を図
る上でバランスを欠くこととなり適当ではないと考えられる。 |
|
| 3 |
今後の対応 |
|
| (1) |
発注書面の交付と,原則としてその書面に記載されたとおりの取引条
件の履行を求めるといった下請法の規制の仕組み及びそれを運用するに
当たってできるだけ形式的かつ画一的な処理に努めるという基本的考え
方自体は,下請取引の公正化のために必要不可欠なものであり,今後と
も維持すべきものである。ただし,現在のように下請取引における親事
業者と下請事業者との関係が多様化・流動化している状況の下では,そ
の運用が形式的・画一的なものにすぎる場合には,下請取引の円滑な実
施を阻害したり,下請事業者の受注機会を減少させるなどにより,か
えって下請事業者の利益を損なうこととなるおそれがあることも否定で
きない。
したがって,当委員会においては,このような規制の仕組みの趣旨が
取引当事者間の合意に基づく取引条件の設定と当該取引条件の証拠化に
あるとの考え方に基づき,発注書面以外の書面における契約事項や業界
における商慣習のほか,価格,納期等といった取引条件の相違をも踏ま
えて,「下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護」という下請法の
目的に照らして,下請法の運用を見直すことが望ましいと考えられる。 |
| (2) |
一方,下請代金の減額,支払遅延など取引条件の履行に係る規定につ
いて違反行為が行われた場合には,下請事業者の受ける影響が大きいこ
とにかんがみ,また,これらの違反行為の未然防止を図る上でも,下請
法上の正式な措置である勧告を積極的に行うこととすべきと考えられ
る。
また,取引条件の設定行為に係る規定については,今後とも違反行為
の未然防止を重視した下請法の運用を行うことが適当であると考えられ
るが,このような規定に違反する行為についても,その未然防止を図る
とともに違反行為に対する抑止力を強化するため,大規模な親事業者に
よる下請法違反事件など下請事業者に与える影響が大きい事案について
は,下請法上の正式措置である勧告を積極的に行うこととすべきと考え
られる。 |
| (3) |
さらに,下請法に違反する行為は独占禁止法にも違反するおそれがあ
るので,単に下請法の適用対象となる場合のみを是正の対象とするので
はなく,例えば,下請法違反事件の調査時において親事業者が下請法の
対象外の事業者に対しても同様の行為を行っていることが明らかになっ
たときには,当該行為について独占禁止法上問題があるか否かの検討を
行うこととすべきと考えられる。 |
|
第6 建設業の下請取引における不公正な取引方法の規制
建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認められるとき
は,建設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知
事又は中小企業庁長官が,当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な
措置を採ることを求めることができることとなっている。
なお,平成9年度においては,措置請求はなかった。