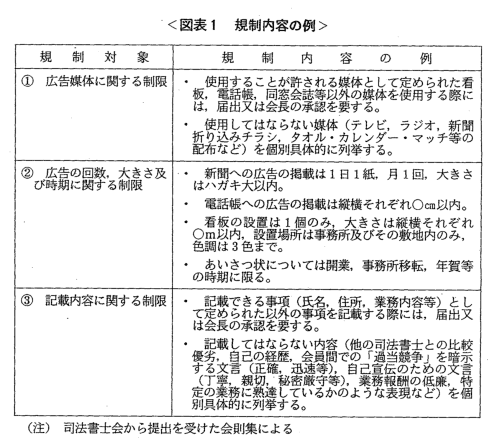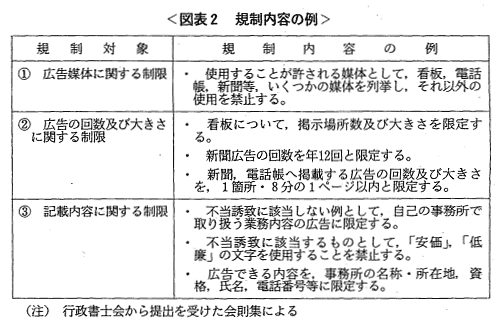| (1) |
司法書士の業務の概要 |
|
| ア |
司法書士は,平成9年4月1日現在,全国で約17,000人が登録をし
ており,その業務は,司法書士法(昭和25年法律第197号)により定
められている。 |
| イ |
司法書士として業務を行うには,国家試験(司法書士試験)に合格
するなど一定の資格を有する者が,日本司法書士会連合会(以下「日
司連」という。)に備えられている司法書士名簿への登録を行うとと
もに,事務所所在地を管轄する司法書士会に入会しなければならな
い。 |
| ウ |
アンケート調査によれば,平成8年における司法書士1人当たりの
平均業務受託件数は1,011件で,大部分は登記関係業務となってお
り,その顧客のほとんどは,二度目以降の固定的な顧客又は初めての
顧客であって,銀行,不動産業者等から紹介を受けた者となってい
る。また,司法書士は,行政書士,土地家屋調査士等,業務上の関連
が深い他の資格職業を兼業している場合が多い。 |
| エ |
司法書士法の規定に基づき,司法書士は法務局(地方法務局)の管
轄区域ごとに司法書士会を,全国の司法書士会は日司連を設立するこ
ととされている。司法書士会及び日司連(以下これらを「司法書士会
等」という。)は,司法書士の品位を保持し,その業務の改善進歩を
図るため,会員等の指導及び連絡に関する事務を行うこと等を目的と
しており,それぞれ法務大臣の認可を受けて会則を定めなければなら
ず,また,司法書士会の会則には,品位保持に関する規定,報酬に関
する規定等を記載しなければならないとされている。
なお,日司連では,各司法書士会を指導するため,司法書士会が制
定すべき会則のひな型(以下「会則基準」という。)を作成してお
り,その結果,各司法書士会の会則は,どれもほぼ同じ内容・表現と
なっている。 |
|
| (2) |
司法書士の事業活動に関する規制と司法書士による事業活動の実態 |
|
| ア |
広告・宣伝活動に関する規制 |
|
| (ア) |
法令による規制 |
|
司法書士法においては,司法書士は常に品位を保持して業務を行
わなければならないこと及び司法書士会の会則中には品位保持に関
する規定を記載しなければならないことが規定されている。また,
同法施行規則では,不当な手段によって嘱託を誘致することが禁止
されている。
司法書士法及び同法施行規則(以下これらを「司法書士法等」と
いう。)における品位保持及び不当な手段による嘱託の誘致の禁止
に関する規定を根拠として,司法書士会等では,会則及びその他の
諸規則等により,司法書士個人の広告・宣伝活動について自主規制
を行っている。 |
| (イ) |
司法書士会等による自主規制 |
|
日司連では,会則基準及び司法書士執務規範基準で,品位保持の
一環として,広告・宣伝活動に関する規定を設けており,「虚偽又
は誇大に類する宣伝及び広告」及び「品位を損なう広告,宣伝」を
禁止している。
また,司法書士会では,会則において,会則基準と同様の広告・
宣伝活動に関する規定を設けているほか,会則以外の諸規則等にお
いて,広告媒体,回数,大きさ,時期,記載内容等について,例え
ば図表1に挙げるように,法令が予定する本来の目的の範囲を逸脱
しているとも考えられるような詳細な規定を設けているものがあ
る。
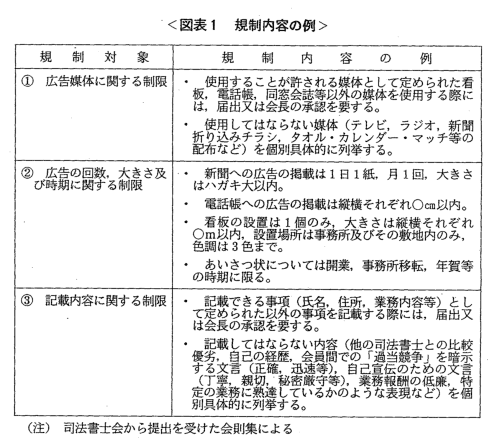 |
| (ウ) |
司法書士による広告・宣伝活動の実態 |
|
アンケート調査によれば,広告を行ったことがある司法書士は全
体の3割に満たず,残り約7割の司法書士は広告を行ったことがな
い。その理由としては,司法書士会が広告規制を行っていることを
挙げた者が47.5%,必要がないからとする者が45.1%,広告をして
も効果がないとする者が17.6%等となっている。また,司法書士会
の広告規制が司法書士による広告媒体,広告回数等の決定に少なか
らず影響していることがうかがえる。
司法書士が広告を行うことについては,4割強の司法書士が,広
告内容等については個々の司法書士が自主的に判断すればよいと考
えているが,他方で,品位保持のために何らかの規制が必要である
と考える司法書士も4割弱に上っている。また,司法書士会による
広告規制については,全体では4割強の司法書士が現在の広告規制
は適切であるとしているが,他方,4割弱の司法書士は,現在の広
告規制は撤廃又は緩和すべきであると考えている。 |
|
| イ |
報酬に関する規制 |
|
| (ア) |
司法書士報酬規定 |
|
司法書士法においては,司法書士会の会則に報酬に関する規定を
記載しなければならないこととされており,会則には,「司法書士
報酬規定」と題する報酬額表(以下「報酬規定」という。)が付さ
れている。報酬規定では,司法書士が行う業務内容等に即し,基本
報酬,手続報酬及び書類作成報酬に分けて報酬の目安が示されてい
る。報酬規定の改定は,数年に一度法務大臣の認可を受けて行われ
ているが,通常,日司連と法務省との間で合意に達した成案を日司
連から司法書士会に示し,それに基づき各司法書士会で改定を行う
ことから,報酬規定は全国一律のものとなっている。 |
| (イ) |
付随報酬 |
|
司法書士会では,多くの場合,報酬規定以外に,司法書士の業務
に付随して行われる戸籍謄・抄本等の取り寄せ,登記の立会等の事
務作業に対する報酬の基準を示す「付随事務の報酬基準」(以下.
「付随報酬表」という。)を定めているが,司法書士法等において
は,付随的な事務作業に係る報酬について各司法書士会が基準を定
めることができるとする明文の規定は存在しない。 |
| (ウ) |
報酬の減額に関する規制 |
|
司法書士法等においては,報酬の減額を禁止する明文の規定は存
在しない。日司連の作成する会則基準では,従来,嘱託を誘致する
目的で報酬額を減額してはならないと規定しており,これを受けた
各司法書士会の会則においても同一の規定が置かれていたが,日司
連では,報酬規定が司法書士の受ける報酬の目安にすぎないことを
明確にする趣旨から,会則基準の一部改正を行い,当該規定を削除
したところであり,各司法書士会においても,会則中にある同規定
を削除している。 |
| (エ) |
司法書士が収受する報酬 |
|
アンケート調査によれば,報酬規定に記載された基本報酬及び手
続報酬については,9割以上の司法書士が記載された範囲内の額に
収まっており,付随報酬についても,9割以上の司法書士が,司法
書士会から配布された付随報酬表を参考にして収受している。 |
|
|
| (3) |
行政書士の業務の概要 |
|
| ア |
行政書士は,平成9年4月1日現在,全国で約36,000人が登録して
おり,その業務は,行政書士法(昭和26年法律第4号)により定めら
れている。 |
| イ |
行政書士として業務を行うには,国家試験(行政書士試験)に合格
するなど一定の資格を有する者が,日本行政書士会連合会(以下「日
行連」という。)に備えられている行政書士名簿への登録を行うとと
もに,事務所所在地を管轄する行政書士会に入会しなければならな
い。 |
| ウ |
アンケート調査によれば,平成8年における行政書士1人当たりの
平均業務受託件数は612件で,大部分は,車庫証明・自動車登録関係
の業務となっており,その顧客のほとんどは,二度目以降の固定的な
顧客又は初めての顧客であって自動車販売業者等から紹介を受けた者
となっている。また,行政書士は,土地家屋調査士,社会保険労務
士,税理士,司法書士等,他の資格職業を兼業している場合が多い。 |
| エ |
行政書士法の規定に基づき,行政書士は都道府県の区域ごとに行政
書士会を,全国の行政書士会は日行連を設立することとされている。
行政書士会及び日行連(以下これらを「行政書士会等」という。)
は,行政書士の品位を保持し,その業務の改善進歩を図るため,会員
等の指導及び連絡に関する事務を行うこと等を目的としており,それ
ぞれ,都道府県知事又は自治大臣の認可を受けて,品位保持に関する
規定,行政書士の受ける報酬(基準)に関する規定等を記載した会則
を定めなければならないとされている。 |
|
| (4) |
行政書士の事業活動に関する規制と行政書士による事業活動の実態 |
|
| ア |
広告・宣伝活動に関する規制 |
|
| (ア) |
法令による規制 |
|
行政書士法においては,行政書士は信用又は品位を害するような
行為をしてはならないこと及び行政書士会等の会則中には,品位保
持に関する規定を記載しなければならないことが規定されている。
また,同法施行規則では,不正又は不当な手段で依頼を誘致するよ
うな行為が禁止されている。
一部の行政書士会では,行政書士法及び同法施行規則(以下これ
らを「行政書士法等」という。)における品位保持及び不正又は不
当な手段による誘致行為の禁止に関する規定を根拠として,行政書
士個人の広告・宣伝活動について自主規制を行っている。 |
| (イ) |
行政書士会等による自主規制 |
|
日行連の会則においては,品位保持に関する規定が定められてい
るが,広告・宣伝活動を制限する具体的な規定はみられない。
また,一部の行政書士会においては,不当誘致行為の禁止とし
て,「嘱託を誘致する目的で宣伝してはならない」旨を会則で規定
しているほか,会則以外の諸規則等において,広告媒体,回数,大
きさ,記載内容等について,例えば図表2に挙げるように,法令が
予定する本来の目的の範囲を逸脱しているとも考えられるような詳
細な規定を設けているものがある。
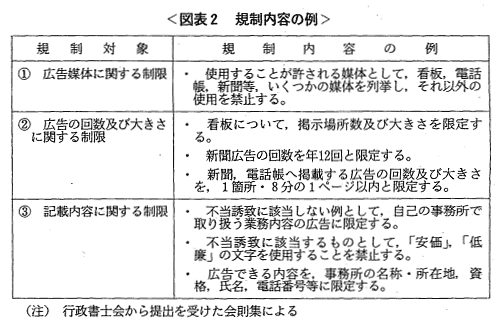
|
| (ウ) |
行政書士による広告・宣伝活動の実態 |
|
アンケート調査によれば,広告を行ったことがある行政書士は全
体の4分の1弱にすぎず,大部分の行政書士は広告を行ったことが
ない。その理由として最も多く挙げられたのは,必要がないからと
するものであった。
また,行政書士が広告を行うことについては,半数以上の行政書
士が,広告内容等については個々の行政書士が自主的に判断すれば
よいと考えている。また,行政書士会による広告規制については,
約4割の行政書士が,現行の広告規制は撤廃又は緩和すべきである
と考えているが,ほぼ同じ割合の行政書士は,現行の広告規制は適
切であると考えている。 |
|
| イ |
報酬に関する規制 |
|
| (ア) |
法令による規制 |
|
行政書士法においては,行政書士の受ける報酬について,各行政
書士会の会則で規定することとされており,各行政書士会の会則で
定める報酬については,日行連の会則で,その基準を定めるとされ
ている。 |
| (イ) |
行政書士会等による規制 |
|
日行連の会則等においては,報酬の基準に関し,①難易度に応じ
て区分した書類1枚当たりの作成料,②1時間当たりの手続代行
料,③1時間当たりの相談料,④実地調査に基づく1面当たりの図
面作成料について定めている。
行政書士会の会則においては,通常,別表において報酬額を定
め,当該報酬額を基準とする旨を規定している。会則の別表で定め
る報酬額(以下「基準報酬額」という。)については,各行政書士
会とも,おおむね日行連の会則で定める報酬の基準と同一の額と
なっている。 |
| (ウ) |
件別基準報酬額表等 |
|
行政書士会では,都道府県知事の認可を受けて定める基準報酬額
のほかに,個々の業務ごとの報酬額を積算した件別基準報酬額表や
業務別の報酬算定例を作成し,会員に対して配布している事例がみ
られるが,これらについては,基準報酬額とは異なり,都道府県知
事の認可は受けていない。 |
| (エ) |
報酬の減額に関する規制 |
|
行政書士法等及び日行連の会則においては,報酬の減額を禁止す
る明文の規定は存在しないが,一部の行政書士会では,会則で,不
当誘致行為の例として「報酬額の不当な割引」を禁止しているもの
がある。 |
| (オ) |
行政書士が収受する報酬 |
|
アンケート調査によれば,行政書士の半数以上は,行政書士会で
定める基準報酬額及び件別基準報酬額表等をそのまま適用して報酬
を収受していない状況にある。 |
|
|