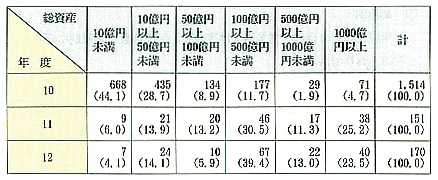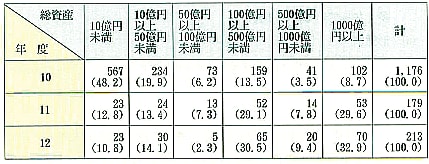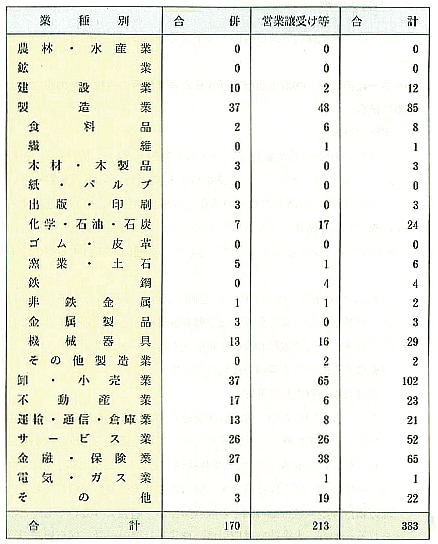平成12年度の株式保有等及び合併・営業譲受け等の主要事例は,次のとおりである。
1 (株)第一勧業銀行,(株)富士銀行及び(株)日本興業銀行の持株会社の設立による事業統合
(1) 本件の概要
本件は,(株)第一勧業銀行(以下「第一勧銀」という。),(株)富士銀行(以下「富士銀」という。)及び(株)日本興業銀行(以下「興銀」という。)の3行が,経済のグローバル化と金融自由化が本格的に進展する中,総合的な金融サービスを提供するため,共同で持株会社を設立し,「みずほフィナンシャルグループ」として,全面的に統合するものである。
3行は共同持株会社の下に3行を置くほか,3行の証券子会社3社(第一勧業証券(株),富士証券(株)及び興銀証券(株))と信託銀行子会社2社(第一勧業富士信託銀行(株)及び興銀信託銀行(株))が合併する。
(2) 金融機関を取り巻く環境の変化について
ア 金融市場の自由化の進展
近年,我が国においては,直接金融市場の活性化を図るための自由化が進み,企業が株式,社債等を発行して資金調達を行う環境が整備された結果,大企業を主たる顧客基盤としていた都市銀行等は,今後,中小企業・個人向け取引を一層増加させる必要に迫られており,地方銀行等の地域金融機関との競合関係が一層強まっていくものとみられる。他方,大企業向け取引は,株式・社債の引受,保有資産の証券化等の金融商品の提供,M&Aの仲介のウエイトが高まり,外資系の金融機関や国内の大手証券会社との競争が強まるものとみられる。
イ 情報技術の発展
情報技術の発展や通信インフラの整備により,銀行業においても,インターネット等新たな媒体を活用した業務展開がみられるほか,顧客データベースの構築等積極的な情報投資が競争上重要となっている。また,他業種企業から情報技術を利用した新たな形態での銀行業への参入が計画されている。
ウ バブル経済の崩壊
銀行は,バブル経済の崩壊により多額の不良債権が生じたことから,収益力を高め,不良債権を償却し,資産内容を健全にするため,事業の再構築が必要となっている。
(3) 独占禁止法上の検討
ア 金融分野における競争について(関係法条第10条及び第15条)
(ア) 一定の取引分野について
本件については,金融分野における競争への影響の検討に当たり,次のとおり一定の取引分野が成立すると判断した。
a 預金業務
主として全国市場について,全国に店舗を置いて営業展開する都市銀行(9行),長期信用銀行(3行)及び信託専業銀行(6行)で検討し,地域市場(都道府県)についてもその地域に店舗を置いて営業展開する地方銀行等を含めて検討することとした。
b 貸出業務
本件は,長期信用銀行である興銀と都市銀行である第一勧銀,富士銀との異業態間の銀行統合であるが,(1)長短分離規制が撤廃されたこと,(2)期限別貸出構成が同質化していること等を勘案すれば,提供する金融機能は同質のものと判断されるところ,主として全国市場について,全国に店舗を置いて営業展開する都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行で検討し,地域市場(都道府県)についてもその地域に店舗を置いて営業展開する地方銀行等を含めて検討することとした。
c 外国為替業務
外貨の売買を行う外国為替取引は,銀行が,輸出業者や個人の有する外貨と国内通貨である円を交換したり,輸入業者や個人の有する円と銀行自身が有する外貨を交換することにより,顧客から手数料を収受する「対顧客取引」と銀行相互間での外貨の調達や銀行自身が外貨により資金運用を行う「インターバンク取引」とに分けられるところ,いずれも,東京外国為替市場で活動する全金融機関ベースで検討することとした。
d 証券業務
株式,債券業務については,それぞれ,引受,売買において一定の取引分野が成立すると判断される。
企業経営や財務戦略上の種々の課題に対し最適と考えられる金融商品やサービスを提供する投資銀行(インベストメントバンク)業務については,証券会社のほか銀行等の異業態の金融機関が参入していることから,全市場参加者ベースで検討することとした。
e 信託業務
信託銀行が営む業務について,全信託銀行ベースで検討することとした。
(イ) 競争への影響の検討
上記(ア)で画定した取引分野のうち,競争への影響が大きい預金,貸出し,債券の引受・売買及び信託業務について検討したところ,検討の結果は次のとおりであり,いずれの取引分野においても競争を実質的に制限することとはならないと判断される。
a 預金業務について
都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行の18行ベースで,本件統合による3行のシェアを合算すると,20数%で,その順位は第1位となり,第2位の都市銀行との格差は8%強となるほか,複数の都市銀行等が統合を予定していることから,今後,集中度が高まると見込まれる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| (a) |
株式投資信託の新規設定が急増するなど,現在の低金利下で個人預金が投資信託等の代替的な金融商品に流入し,隣接市場である証券会社,投資信託委託会社,保険会社等が提供する預金を代替する金融商品が競争圧力となっていること。 |
| (b) |
隣接市場である郵便貯金(平成11年3月末における貯金残高は約250兆円)が競争圧力となっていること。 |
| (c) |
低コストを反映した高い利回りを実現するインターネット専業銀行やコンビニエンスストアを利用した24時間サービスを行う消費者利便訴求型の銀行の参入が予定されており,これらが今後,有力な競争業者となっていくことが見込まれること。 |
| (d) |
現在の低金利下で,資産運用手段として株式等他の金融商品に見劣りしないよう,各銀行は金利優遇商品や懸賞付き商品など独自性のある多様な預金商品を提供し,預金獲得競争を展開していること。 |
| (e) |
大手都市銀行等の有力な競争業者が存在すること。
また,東京都においては,3行のシェアは20%を超え,その順位は第1位となるが,上記(a)〜(e)の状況に加え,都市銀行,地方銀行等を合わせて127の銀行が事業活動を行っているほか,信用金庫等の多数の系統金融機関も存在している。 |
b 貸出業務について
都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行の18行ベースで,本件統合による3行のシェアを合算すると,25%強で,その順位は第1位となり,第2位の都市銀行との格差は約14%となるほか,複数の都市銀行等が統合を予定していることから,今後,集中度が高まると見込まれる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| (a) |
資金調達手段が多様化され,大企業は社債,コマーシャルペーパー,売掛債権流動化等の間接金融にはよらない資金調達を進めており,隣接市場からの競争圧力が働くこと。 |
| (b) |
一般に,信用リスクが低く,貸出額の大きい大企業向け貸出しは,縮小傾向にあるところ,資金調達の一部に間接金融を利用する大企業に対しては,(a)の状況の下で,複数の大手都市銀行等の有力な競争業者が存在すること。 |
| (c) |
中小企業向け貸出しが3行の主要な収益基盤の一つとなることが見込まれるところ,一般に,大企業と比べて信用リスクが高いとされる中小企業向け貸出しは,貸出資産の劣化・縮小を防ぐため,常に新たな貸出先の獲得が必要とされることから,大手都市銀行等の有力な競争業者との間で活発な競争が行われるものと見込まれること。 |
| (d) |
個人向け貸出しは,多様なローン商品の開発,金利優遇,手続利便の向上等をめぐり,大手都市銀行等の有力な競争業者との間で活発な競争が行われるものと見込まれること。
また,東京都においては,3行のシェアは25%を超え,その順位は第1位となるが,上記(a)〜(d)の状況に加え,都市銀行,地方銀行等を合わせて,127の銀行が事業活動を行っているほか,信用金庫等の多数の系統金融機関も存在しており,大企業,中小企業ともに取引先金融機関の変更が可能な状況にある。 |
c 債券の引受・売買業務について
3行の証券子会社の合併により,社債の引受高シェアは,20%弱で,その順位は第1位となる。また,3行と結合関係のある証券会社を加えた場合の社債の引受高,公社債の売買高は,合算すると,それぞれ,25%弱・第1位,10%強・第1位となる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| (a) |
今後,企業の資金調達手段として直接金融の伸張が期待され,証券市場の需要拡大により競争は活発化すると見込まれること。 |
| (b) |
商品開発や販売力等の事業能力が高い大手証券会社等が有力な競争業者として存在すること。 |
| (c) |
公社債の引受・売買業務においては,銀行の証券子会社の躍進が著しいところ,これら有力な競争業者が存在すること。 |
| (d) |
外資系証券会社が当該分野で業績を大きく伸ばしていること。 |
d 信託業務について
合併を行う3行の信託銀行子会社に,富士銀の子会社である安田信託銀行(株)を合算してシェアをみると,信託全体では10%強で,その順位は第4位となるほか,有価証券信託,金銭債権信託及び不動産信託において第1位となる。
しかしながら,信託全体としては,有力な競争業者が複数存在しているところ,長期化する低金利や規制緩和により信託商品の銀行窓口販売が解禁されるなど資産運用手段として信託分野は拡大しており,競争が活発に行われている。
また,個別の信託分野をみると,次のような状況が認められる。
| (a) |
有価証券信託及び金銭債権信託については,親銀行からの受託が多いこと。 |
| (b) |
不動産信託については,統合によるシェアの増加は0.5%にとどまるほか,大手信託銀行等の有力な競争業者が存在すること。 |
イ 事業支配力の過度の集中について(関係法条第9条)
| (ア) |
持株会社については,独占禁止法第9条において,事業支配力が過度に集中することとなるものの設立又は転化が禁止されているが,当委員会は,「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の考え方」(平成9年12月公正取引委員会。以下「9条ガイドライン」という。)に従って,事業支配力が過度に集中することとなる持株会社かどうかを判断することとしている。
具体的には,持株会社グループが9条ガイドラインに掲げる3つの禁止類型のうち,いずれかに該当する場合に事業支配力が過度に集中することとなるとされている。 |
| (イ) |
3行の持株会社グループ(第一勧銀,富士銀,興銀+国内の子会社+実質子会社)が9条ガイドラインの3つの類型に該当するかについて以下の検討を行ったところ,いずれの禁止類型にも該当しないことから,本件持株会社は事業支配力が過度に集中することとはならないと判断した。
a 第1類型
持株会社グループの規模が大きく(持株会社グループの総資産合計額が15兆円超),かつ,相当数(5以上)の主要な事業分野のそれぞれにおいて別々の大規模な会社(単体総資産が3000億円超)を有する場合が要件であるところ,金融会社を除いたグループの総資産合計額は15兆円を超えない。
b 第2類型
大規模金融会社(単体総資産額が15兆円超)と,金融又は金融と密接に関連する業務を営む会社以外の大規模な会社(単体総資産額が3000億円超)を有する場合が要件であるところ,総資産が3000億円を超える事業会社が存在しない。
c 第3類型
相互に関連性のある相当数(5以上(規模が極めて大きい事業分野に属する有力な会社を有する場合3以上))の主要な事業分野のそれぞれにおいて別々の有力な会社(シェア10%以上又は売上高上位3位以内)を有する場合が要件であるところ,金融に関連する事業分野において,銀行以外に有力な会社が存在しない。
|
(4) 産業界に与える影響について
本件統合により,3行は,上場会社約2,300社(銀行,保険会社を除く。)のうち,約1,600社(約70%)に対して融資を行うこととなる。また,このうち3行からの融資額の合算が第1位となる上場会社は約700社弱(約30%)となる。
このため,本件統合が産業界に与える影響について,3行から融資を受ける事業者(上場会社及び中堅・中小会社)等に対し,アンケート調査及びヒアリング調査を実施した。
調査結果の主なポイントは,次のとおりである。
ア 本件統合の評価
事業会社へのアンケートの結果,本件統合に対する期待として,5割強の事業者が「金融サービスの向上」や「安定的な資金供給」をあげている。一方,本件統合による懸念は特にないとする事業者は15%弱にとどまり,「サービスの低下」,「借入条件の悪化」等何らかのマイナスの影響があるとの懸念を有している。
イ 個別事業者の経営に与える影響
| (ア) |
本件統合により,設備資金及び運転資金の調達の手段を変えるとする事業者は4割程度あった。他方,設備資金及び運転資金の調達で代替的な資金調達手段がなく,資金調達の構成を変えられないとする事業者は,全体の2割強にのぼっている。 |
| (イ) |
統合後,3行合算の借入比率が,従来の借入比率第1位の銀行を上回る事業者のうち7割の事業者は,融資姿勢の変化に伴うリスクを回避するため,借入比率の調整を行うとしている。 |
| (ウ) |
借入条件については,半数の事業者は,本件統合による影響は特にないとしているものの,1割強の事業者は,不利になるとみている。 |
| (エ) |
本件統合により,預金等借入以外の取引や社債引受の要請等が現にある又は今後強まると見込んでいる事業者は4割から5割と高い比率となっている。 |
ウ 業界再編への影響
アンケートの結果,7割弱の事業者が「特段の変化はない」としており,本件統合が事業者の属する各業界の再編に影響を与えるとみているものは少なかった。
エ 企業集団内取引への影響
| (ア) |
富士銀は同行の主要取引先28社の社長をメンバーとして芙蓉会を,また,第一勧銀は同行の主要取引先48社の会長・社長をメンバーとして三金会を主催し,定期的に会合を開催している。 |
| (イ) |
本件統合が,こうした企業集団にどのような影響を与えるかについてアンケート調査したところ,企業集団内外の取引の変化については,企業集団内外の事業者とも8割以上が特に変わらないとしており,企業集団が解消するとみている事業者は少なかった。また,企業集団の今後の動向については,企業集団に所属する事業者の5割強が,企業集団内の事業者同士の結び付きが維持・強化されるとの見方を有しており,結び付きが弱まるものとみている事業者の割合を上回った。 |
(5) 独占禁止法及び競争政策上の取組
ア 独占禁止法及び競争政策上の問題点の指摘
当委員会は,上記(4)の調査結果を踏まえ,3行に対して,以下のとおり,独占禁止法及び競争政策上の問題点の指摘を行った。
(ア) 事業経営への関与について
| a |
本件調査の過程において,事業規模が拡大する3行に対し,融資比率及び出資比率が高まる事業者は,銀行が以下のような行為を行う等,その事業経営への関与を懸念している。
| (a) |
預金等借入以外の取引を行う(あるいは増やす)よう要請すること。 |
| (b) |
社債引受幹事を特定の証券会社とするよう要請すること。 |
| (c) |
社債の管理を当事会社で行わせるよう要請すること。 |
|
| b |
融資比率や出資比率の高まりを背景として,上記のような行為を行い,当該「要請」に応じない場合不利益な取扱いをする旨を示唆する等,3行の営業活動いかんによっては,不公正な取引方法(第19条)につながるおそれがあることから,今後の事業活動に際しては,自社の影響力を背景として,取引先事業者に不利益を被らせるような行為がないように所要の対応が図られる必要がある。 |
(イ) 企業集団について
当委員会の実施した累次の企業集団調査においては,集団内取引の割合は年々減少している等の実態がみられるところ,今般の調査によれば,上記(4)のとおり,企業集団内の取引に変化がなく企業集団内の事業者同士の結び付きが維持・強化されるとの見方が集団内外の事業者において多く,企業集団に属していることをもって取引先等の選別が行われ,排他的,閉鎖的な取引関係となるとの懸念があることから,これを払拭するために,所要の対応が図られる必要がある。
イ 3行からの申出
上記の問題点の指摘に対して,3行からは以下の申出があった。
(ア) 事業経営への関与について
融資比率や出資比率の高まりを背景として取引を要請することに対する懸念については,現状でも独占禁止法遵守についての役職員への周知徹底等の体制を整えるなど,コンプライアンスの徹底に努めているところ,統合後も引き続きこれに努めるとともに,新設される持株会社において,指摘のあったような行為を行わないようグループ全体のコンプライアンス統括機能を全うするための体制作りを行う。
(イ) 企業集団について
みずほフィナンシャルグループは,中立的かつ開かれた金融グループとして事業活動を行うこととしており,同グループが中心となって特定の排他的な企業集団を形成していくことは考えていない。平成14年春に予定している傘下銀行の統合・再編時までに,銀行を中心に運営される形での企業グループは,解消を含め,運営の見直しを行う。
具体的には,芙蓉会については,富士銀が事務局・幹事役を外れ,開催場所についても同行本店から他所に変更することを決定している。また,三金会も,運営方法について同様の方向で見直しを行う。
(6) 当委員会の今後の対応
| ア |
本件の事業統合について,相談のあった持株会社の設立,その下に3行を置くこと,3行の証券子会社3社及び信託銀行子会社2社の合併については,独占禁止法上の規定に違反するおそれはないと認められた。
また,平成14年春を目途とする当事行の更なる再編については,必要に応じて,改めて検討することとする。 |
| イ |
本件統合が産業界に与える影響に関して,当委員会が指摘を行った問題点に対する当事行からの申出については,その実施状況を十分注視していくとともに,独占禁止法に違反すると認められる行為がある場合には,これに対して厳正に対処していくこととする。 |
2 日本製紙(株)及び大昭和製紙(株)の持株会社の設立による事業統合
(1) 本件統合の概要
本件は,日本製紙(株)と大昭和製紙(株)が,情報・通信技術の革新に基づく紙需要の変化,経済のグローバル化による国際競争の激化等に対応するため,両社の親会社となる共同持株会社を設立して事業を統合するものである。
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
紙は,製造設備の面においては,同一の抄紙機で各種の紙を製造できるものの,ユーザー側からすると,個別の品種ごとにそれぞれの用途に合わせた品質・機能を有していることから,本件統合においては,紙全体で一定の取引分野が成立するとともに,上級印刷紙コート紙といった個別品種ごとにも検討する必要があるものと判断した。
イ 競争への影響
(ア) 市場シェア
本件統合により,当事会社グループ全体のシェアは,紙市場全体において,約32%で,その順位が第1位となり,また,印刷情報用紙全体において,約35%で,その順位が第1位となるところ,上記アで画定した市場のうち,本件統合により,新聞巻取紙,上級印刷紙,微塗工印刷用紙,コート紙,軽量コート紙,PPC用紙等の紙の主要品種の分野において,合算の生産数量シェアが30%ないし40%を超え,また,当事会社と第2位メーカーとの2社の累積シェアが6割前後ないしこれを超えることとなる。
(イ) 価格改定行動
メーカーの価格改定行動について,これまでの状況をみると,当事会社を含む上位メーカーが値上げを行い,他のメーカーはこれに追随するとの実態がみられる。
(ウ) ユーザー等の状況
メーカー・代理店から紙を購入する卸商及びユーザーについてみると,新聞社や大手印刷業者などの大口ユーザーがあるものの,中小の卸商や印刷業者も多く,これら中小の卸商及びユーザーは,購入ロットが小さいことから価格交渉力が強いとはいえない。また,出版社は,定期刊行物等に用いられる定期品については,安定供給を重視する上,一度決まった銘柄を変更することはほとんどなく,価格の変化に応じて取引先を変更するような取引実態にはない。
(エ) 輸入
輸入については,例えば,印刷情報用紙についてみると,平成8年頃には需要動向から輸入数量は60万トンを超えたが,その後は減少傾向となり,平成11年には,国内の生産量約1100万トンに対して,21万トン程度にとどまっていたところ,最近の状況では,IT関連の需要が旺盛なことから,インドネシア等からの輸入数量が増加している実態がみられ,国内の需給及び価格の状況によっては,ある程度輸入品が増加するといった一定の相関関係が認められる。
(オ) 流通
紙の流通市場においては,当事会社を含め上位メーカーが大手代理店等に出資している実態がみられる。
(カ) その他
新聞巻取紙及びPPC用紙については,当事会社以外にも複数の有力メーカーが存在することに加えて,購買力の高いユーザーが複数購買を行っていること,輸入品の競争圧力が働きやすいといった状況が認められる。
ウ 問題点の指摘
上記の状況を踏まえ,当委員会は,当事会社に対し,以下のとおり問題点の指摘を行った。
(ア) 本件統合が競争に及ぼす影響
本件統合により,上級印刷紙,微塗工印刷用紙,コート紙,軽量コート紙等の紙の主要な品種の分野において,当事会社の市場支配力の形成及び市場の寡占化の進展による当事会社を含めた上位メーカーの協調的行動が懸念され,競争が実質的に制限されることとなるおそれがある。
(イ) 流通分野への影響
紙の流通市場においては,当事会社を含め上位メーカーが大手代理店に出資している実態がみられることから,流通段階における競争がメーカー段階の競争に影響を及ぼすことが十分に期待できない状況にある。
エ 当事会社の申し出た措置
上記の指摘に対し,当事会社からは,本件統合後においても,紙の分野における市場構造が引き続き競争的なものとなるようにするため,第三者に対する事業の譲渡等の抜本的な措置を講じるとして,以下のような問題解消措置の申出があった。
(ア) 生産分野における問題解消措置
需要の拡大が見込まれるコート紙,上級印刷紙等の印刷情報用紙の主要品種を対象として,当事会社グループ全体の紙の生産数量590万トンの8%強の年産50万トン相当の生産設備及び営業を3年以内を目途に第三者に譲渡する。
(イ) 流通分野における問題解消措置
紙の流通分野において,紙の取扱シェアの大きい大手代理店3社に対する出資比率を引き下げる。
オ 当委員会の判断
(ア) 生産分野について
当事会社から申出のあったコート紙,上級印刷紙等の年産50万トン相当の設備及び営業の第三者への譲渡が実行された場合,両社の印刷情報用紙全体におけるシェアは,約35%から30%程度となるとともに,第2位メーカーとの格差も5%程度となる
また,当事会社から譲渡対象として申出のあったコート紙,上級印刷紙等は,今後も市場が拡大すると見込まれるとともに,市況品であり,その価格動向が他の品種の価格動向に及ぼす影響が大きい品種である。
さらに,最近の市場を取り巻く環境の変化として,大手商社や代理店が輸入紙を取り扱うようになってきており,PPC用紙をはじめインドネシア等からの輸入数量も増加してきている。ユーザー側においても,安定供給が保証されれば輸入品を取り扱いたいとする印刷業者や出版社も多い。
以上の事情を総合的に勘案した場合,当事会社から申出のあった問題解消措置が着実に実行されれば,一定の取引分野における競争が実質的に制限されることとはならないものと考えられる。
(イ) 流通分野について
流通分野における問題解消措置については,大手代理店への出資比率が引き下げられることとなれば,流通段階における競争がメーカー段階の競争を促進することが期待できるものと考えられる。
(3) 今後の対応
上記の当事会社の措置及び最近の市場を取り巻く環境の変化を踏まえた場合,当事会社から申出のあった措置が着実に実行されれば,本件統合により,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。
今後,当委員会は,紙の市場の競争状況を含め,当事会社の問題解消措置の履行状況を十分に把握していくこととする。
3 (株)北洋銀行及び(株)札幌銀行の持株会社の設立による事業統合
(1) 本件統合の概要
本件統合は,北海道を営業基盤とする(株)北洋銀行(以下「北洋銀行」という。)及び(株)札幌銀行(以下「札幌銀行」という。)が,重複店舗及び事務集中部門の統廃合等による経営効率化等を目的として,当事会社が共同で持株会社を設立して事業を統合するものである。
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
(ア) 役務の範囲
預金業務及び貸出業務のそれぞれについて,一定の取引分野が成立すると判断した。
(イ) 地理的範囲
北洋銀行及び札幌銀行の営業活動地域等からみて,北海道全域において一定の取引分野が成立すると判断した。また,地域経済の実態等からみて,北海道内の地域別にも,一定の取引分野が成立すると判断した。
イ 競争への影響
本件統合により,預金業務及び貸出業務について,北海道全域及び北海道内の一部の地域における本件統合後の当事会社の合算シェアが高くなる(北海道全域における全金融機関ベースでのシェアは,預金業務が20%弱,貸出業務が30%弱となる。)。
しかしながら,近年,我が国においては金融市場の自由化が進みつつあるところ,直接金融の進展により企業の資金調達手段が多様化するとともに,都市銀行等による中小企業向け取引の拡充等の動きにより,都市銀行や地方銀行という枠を超えた競争が活発化する動きがみられる。
また,地方銀行,信用金庫等の地域金融機関においても,個人・企業に対して多様な商品・サービスの提供等を行う動きがあり,地域金融機関間での競争も活発化しつつある。
これらの状況に加えて,北海道全域には,預金業務及び貸出業務において,都市銀行,地方銀行等の有力な競争業者が存在するほか,地域別にも信用金庫,農業協同組合等の系統金融機関と競合している状況が認められる。
上記の事情を総合的に勘案すれば,上記アで画定したいずれの取引分野についても,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。
4 (株)三和銀行,(株)東海銀行及び東洋信託銀行(株)の持株会社の設立による事業統合
(1) 本件の概要
本件は,(株)三和銀行(以下「三和銀行」という。),(株)東海銀行(以下「東海銀行」という。)及び東洋信託銀行(株)(以下「東洋信託」という。)の3行が,ミドル・リテール分野を中心に,総合金融サービスを提供するため,共同で持株会社(持株会社の名称は,「(株)UFJホールディングス」)を設立し,「UFJグループ」として,全面的に統合するものである。
また,平成14年1月を目途に,持株会社の下で三和銀行と東海銀行が合併し,信託関連業務を東洋信託へ,東洋信託の預金・貸出業務を合併後の銀行へ早い時期に統合することを検討している。
(2) 独占禁止法上の検討
ア 金融分野における競争について(関係法条第10条)
(ア) 一定の取引分野について
本件については,金融分野における競争への影響の検討に当たり,次のとおり一定の取引分野が成立すると判断した。
a 預金業務
主として全国市場について,全国に店舗を置いて営業展開する都市銀行(9行),長期信用銀行(3行)及び信託専業銀行(6行)ベースで検討し,地域市場(都道府県)については,その地域に店舗を置いて営業展開する地方銀行等を含めて検討することとした。
b 貸出業務
主として全国市場について,全国に店舗を置いて営業展開する都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースで検討し,地域市場(都道府県)については,その地域に店舗を置いて営業展開する地方銀行等を含めて検討することとした。
c 外国為替業務
外国為替取引は,「対顧客取引」と「インターバンク取引」とに分けられるところ,いずれも,東京外国為替市場で活動する全金融機関ベースで検討することとした。
d 証券業務
株式及び債券に係る引受業務及び売買業務のそれぞれにおいて,一定の取引分野が成立すると判断した。
e 信託業務
信託銀行が営む業務について,全信託銀行ベースで検討することとした。
(イ) 競争への影響の検討
上記(ア)で画定した取引分野のうち,競争への影響が大きい預金及び貸出業務についての検討の結果は次のとおりであり,いずれの取引分野においても競争を実質的に制限することとはならないと判断される。
a 預金業務について
本件統合による都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースでの合算シェアは20%弱で,その順位は第3位となる。また,他の都市銀行等が統合を予定していることから,上位行の集中度が高まることとなる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| (a) |
個人預金が株式,投資信託等の代替的な金融商品に流入し,隣接市場を形成する証券会社,投資信託委託会社,保険会社等が提供する金融商品が競争圧力となっていること。 |
| (b) |
隣接市場を形成する商品である郵便貯金(平成12年3月末における貯金残高は約260兆円)が競争圧力となっていること。 |
| (c) |
低コストを反映した高い利回りを実現するインターネット専業銀行やコンビニエンスストアを利用した24時間サービスを行う銀行としての他業種からの参入が予定されていること。 |
| (d) |
各銀行は金利優遇商品や懸賞付き商品など独自性のある多様な預金商品を提供し,預金獲得競争を展開していること。 |
| (e) |
都市銀行等の有力な競争業者が存在すること。 また,地域市場についてみた場合,当事行の合算シェアが第1位となる都道府県はない。 |
b 貸出業務について
本件統合による都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースでの合算シェアは15%強で,その順位は第3位となる。また,他の都市銀行等が統合を予定していることから,上位行の集中度が高まることとなる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| (a) |
資金調達手段が多様化され,大企業は社債,コマーシャルペーパー,売掛債権流動化等の間接金融にはよらない資金調達を進めており,隣接市場からの競争圧力が働くこと。 |
| (b) |
(a)の状況の下で,一般に,信用リスクが低く,貸出額の大きい大企業向け貸出しは,縮小傾向にあるところ,資金調達の一部に間接金融を利用する大企業に対する貸出しについては,他の都市銀行等の有力な競争業者が存在すること。 |
| (c) |
都市銀行等が中小企業向け貸出しの強化・拡大を図っており,活発な競争が行われるものと見込まれること。 |
| (d) |
個人向け貸出しは,多様なローン商品の開発,金利優遇,手続利便性の向上等をめぐり,他の都市銀行等の有力な競争業者との間で活発な競争が行われるものと見込まれること。 |
また,愛知県においては,当事行の合算シェアが20%を超え,その順位は第1位となるが,上記(a)〜(d)の状況に加え,同県には地方銀行,信用金庫等多数の地域金融機関が存在しており,大企業向け貸出し及び中小企業向け貸出しともに競争が活発な状況にあると認められる。 イ 事業支配力の過度の集中について(関係法条 第9条)
| (ア) |
持株会社については,独占禁止法第9条において,事業支配力が過度に集中することとなるものの設立又は転化が禁止されているが,当委員会は9条ガイドラインに従って,事業支配力が過度に集中することとなる持株会社かどうかを判断することとしている。
具体的には,持株会社グループが9条ガイドラインに掲げる3つの禁止類型のうち,いずれかに該当する場合に事業支配力が過度に集中することとなるとされている。 |
| (イ) |
当事行の持株会社グループ(三和銀行,東海銀行及び東洋信託並びにこれら3行の国内の子会社及び実質子会社)が9条ガイドラインの3つの禁止類型に該当するか検討を行ったところ,いずれの禁止類型にも該当しないことから,本件統合により事業支配力が過度に集中することとはならないと判断した。 |
(3) 産業界に与える影響について
本件統合により,当事行は,上場会社約2,300社(金融会社を除く。)のうち,1,400社弱(60%弱)に対して融資を行うこととなる。また,このうち当事行からの融資額の合算が第1位となる上場会社は約250社(約11%)となる。
このため,本件統合が産業界に与える影響について,当事行から融資を受ける事業者(上場会社及び中堅・中小会社)等に対し,アンケート調査及びヒアリング調査を実施した。
調査結果の主なポイントは,次のとおりである。
ア 本件統合の評価
事業会社へのアンケートの結果,本件統合に対する評価として,40%強の事業者が「情報提供能力等の向上」や「サービスの向上」を挙げている。一方,本件統合に対する懸念として,20%強が「競争の減退」を挙げたほか,「経営関与が強まる」を選択したものは約15%に上った。
イ 個別事業者の経営に与える影響
| (ア) |
本件統合により,設備資金及び運転資金の調達の手段を変えるとする事業者は,それぞれ,約40%及び45%強であった。他方,設備資金及び運転資金の調達で代替的な資金調達手段がなく,資金調達の構成を変えられないとする事業者は,全体の25%程度に上った。 |
| (イ) |
本件統合後,融資姿勢の変化に伴うリスクを回避するため,借入比率の調整を行うとしている事業者は,約40%に上った。 |
| (ウ) |
借入条件については,60%弱の事業者は,本件統合による影響は特にないとしているものの,15%強の事業者は,不利になると回答した。 |
| (エ) |
本件統合により,預金等借入以外の取引の要請,社債引受幹事を特定の証券会社とすることの要請等が現にある又は今後強まると見込んでいる事業者は25%強から35%強と高い比率となっている。 |
ウ 業界再編への影響
アンケートの結果,70%の事業者が「特段の変化はない」としている。
エ 企業集団内取引への影響
| (ア) |
三水会(三和系)は,三和銀行,東洋信託等計44社の相談役・会長・社長をメンバーとして,定期的に会合を開催している。 |
| (イ) |
本件統合が,こうした企業集団にどのような影響を与えるかについてアンケート調査したところ,企業集団内外の取引の変化については,企業集団内外の事業者とも90%以上が特に変わらないとしており,企業集団が解消するとみている事業者は少なかった。また,企業集団の今後の動向については,企業集団に所属する事業者の75%強が,企業集団内の事業者同士の結び付きが維持・強化されるとの見方を有している。 |
(4) 独占禁止法及び競争政策上の取組
ア 独占禁止法及び競争政策上の問題点の指摘
当委員会は,上記(3)の調査結果を踏まえ,当事行に対して,次のとおり,独占禁止法及び競争政策上の問題点の指摘を行った。
(ア) 事業経営への関与について
| a |
本件調査の過程において,事業規模が拡大する当事行からの融資比率及び出資比率が高まる事業者は,銀行が次のような行為を行うこと等,自己の事業経営への関与を懸念している。
| (a) |
預金等借入以外の取引を行う(あるいは増やす)よう要請すること。 |
| (b) |
社債引受幹事を特定の証券会社とするよう要請すること。 |
| (c) |
社債の管理を当事行に行わせるよう要請すること。 |
|
| b |
融資比率や出資比率の高まりを背景として,上記のような行為を行い,当該「要請」に応じない場合不利益な取扱いをする旨を示唆する等,当事行の事業活動いかんによっては,不公正な取引方法(第19条)につながるおそれがあることから,今後の事業活動に際しては,自社の影響力を背景として,取引先事業者に不利益を被らせるような行為がないように所要の対応が図られる必要がある。 |
(イ) 企業集団について
当委員会の実施した累次の企業集団調査においては,集団内取引の割合は年々減少している等の実態がみられるところ,今般の調査によれば,上記(3)のとおり,企業集団内の取引に変化がなく企業集団内の事業者同士の結び付きが維持・強化されるとの見方が集団内外の事業者において多く,企業集団に属していることをもって取引先等の選別が行われ,排他的・閉鎖的な取引関係となるとの懸念がある。
イ 当事行からの申出
上記の指摘に対して,当事行からは次の申出があった。
(ア) 事業経営への関与について
貸出比率や出資比率の高まりを背景として各種取引を要請することに対する懸念については,現状においても,独占禁止法の遵守を全役職員に周知徹底を図るなど,コンプライアンスの充実・強化を徹底しているところである。
また統合後も,役職員一人一人が高いコンプライアンス意識を持つことが,顧客からの強い支持と市場からの高い信認につながるとの考えのもと,持株会社を中心としたグループ全体のコンプライアンスの充実・強化を図っていくことで,懸念されている行為の防止に努めていく。
(イ) 企業集団について
UFJグループとして,排他的な企業集団を形成する意思はなく,また,東海銀行の親密企業等であるからといって,三水会への加入を促進する考えはない。企業間の統合については,各企業が独自で検討・実施することであると考えており,三水会に属する企業と東海銀行の親密企業の統合を支援・促進していこうとは考えていない。
(5) 当委員会の今後の対応
| ア |
本件統合について,相談のあった持株会社の設立及びその傘下に三和銀行,東海銀行及び東洋信託を置くことについては,独占禁止法上の規定に違反するおそれはないと認められた。
また,平成14年1月を目途とする当事行の更なる再編については,必要に応じて,改めて検討することとする。 |
| イ |
本件統合が産業界に与える影響に関して,当委員会からの指摘に対する当事行からの申出については,その実施状況を十分把握していくとともに,独占禁止法に違反すると認められる行為がある場合には,これに対して厳正に対処していくこととする。 |
5 (株)東京三菱銀行,三菱信託銀行(株)及び日本信託銀行(株)の持株会社の設立による事業統合
(1) 本件の概要
本件は,(株)東京三菱銀行(以下「東京三菱銀行」という。),三菱信託銀行(株)(以下「三菱信託」という。)及び日本信託銀行(株)(以下「日本信託」という。)の3行が,顧客の多様な金融ニーズに対して,業態を超えた多角的な金融サービスを提供すること等を目的として,共同で持株会社(持株会社の名称は,「(株)三菱東京フィナンシャル・グループ」)を設立し,全面的に統合するものである。
また,平成13年10月を目途に,持株会社の下で三菱信託,日本信託及び東京信託銀行(株)(以下「東京信託」という。)が合併することとしている。
(2) 独占禁止法上の検討
ア 金融分野における競争について(関係法条 第10条)
(ア) 一定の取引分野について
本件については,金融分野における競争への影響の検討に当たり,次のとおり一定の取引分野が成立すると判断した。
a 預金業務
主として全国市場について,全国に店舗を置いて営業展開する都市銀行(9行),長期信用銀行(3行)及び信託専業銀行(6行)ベースで検討し,地域市場(都道府県)については,その地域に店舗を置いて営業展開する地方銀行等を含めて検討することとした。
b 貸出業務
主として全国市場について,全国に店舗を置いて営業展開する都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースで検討し,地域市場(都道府県)については,その地域に店舗を置いて営業展開する地方銀行等を含めて検討することとした。
c 外国為替業務
外国為替取引は,「対顧客取引」と「インターバンク取引」とに分けられるところ,いずれも,東京外国為替市場で活動する全金融機関ベースで検討することとした。
d 証券業務
株式及び債券に係る引受業務及び売買業務のそれぞれにおいて,一定の取引分野が成立すると判断した。
e 信託業務
信託銀行が営む業務について,全信託銀行ベースで検討することとした。
(イ) 競争への影響の検討
上記(ア)で画定した取引分野のうち,競争への影響が大きい預金,貸出及び信託業務についての検討の結果は次のとおりであり,いずれの取引分野においても競争を実質的に制限することとはならないと判断される。
a 預金業務について
本件統合による都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースでの合算シェアは20%弱で,その順位は第4位となる。また,他の都市銀行等が統合を予定していることから,上位行の集中度が高まることとなる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| (a) |
個人預金が株式,投資信託等の代替的な金融商品に流入し,隣接市場を形成する証券会社,投資信託委託会社,保険会社等が提供する金融商品が競争圧力となっていること。 |
| (b) |
隣接市場を形成する商品である郵便貯金(平成12年3月末における貯金残高は約260兆円)が競争圧力となっていること。 |
| (c) |
低コストを反映した高い利回りを実現するインターネット専業銀行やコンビニエンスストアを利用した24時間サービスを行う銀行としての他業種からの参入が予定されていること。 |
| (d) |
各銀行は金利優遇商品や懸賞付き商品など独自性のある多様な預金商品を提供し,預金獲得競争を展開していること。 |
| (e) |
都市銀行等の有力な競争業者が存在すること。 また,地域市場についてみた場合,当事行の合算シェアが第1位となる都道府県はない。 |
b 貸出業務について
本件統合による都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースでの合算シェアは15%弱で,その順位は第4位となる。また,他の都市銀行等が統合を予定していることから,上位行の集中度が高まることとなる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| (a) |
資金調達手段が多様化され,大企業は社債,コマーシャルペーパー,売掛債権流動化等の間接金融にはよらない資金調達を進めており,隣接市場からの競争圧力が働くこと。 |
| (b) |
(a)の状況の下で,一般に,信用リスクが低く,貸出額の大きい大企業向け貸出しは,縮小傾向にあるところ,資金調達の一部に間接金融を利用する大企業に対する貸出しについては,他の都市銀行等の有力な競争業者が存在すること。 |
| (c) |
都市銀行等が中小企業向け貸出しの強化・拡大を図っており,活発な競争が行われるものと見込まれること。 |
| (d) |
個人向け貸出しは,多様なローン商品の開発,金利優遇,手続利便性の向上等をめぐり,他の都市銀行等の有力な競争業者との間で活発な競争が行われるものと見込まれること。
また,地域市場についてみた場合,当事行の合算シェアが第1位となる都道府県はない。 |
c 信託業務について
信託業務については,三菱信託,日本信託及び東京信託の合算シェアをみると,信託全体では20%弱・第1位となるほか,年金・財形信託において第1位となる。
しかしながら,信託全体としては,高度なノウハウを有しフルラインで信託商品を提供する信託専業銀行等有力な競争業者が複数存在している。また,低金利の長期化や規制緩和による信託商品の銀行窓口販売の解禁などから,資産運用手段として信託分野は拡大しており,競争が活発に行われている。
また,個別の信託分野をみると,年金・財形信託については,今後拡大が見込まれる年金市場において信託銀行同士の競争に加え,生命保険会社の提供する年金保険商品からの競争圧力が激しくなることが予想される。
イ 事業支配力の過度の集中について(関係法条 第9条)
| (ア) |
持株会社については,独占禁止法第9条において,事業支配力が過度に集中することとなるものの設立又は転化が禁止されているが,当委員会は9条ガイドラインに従って,事業支配力が過度に集中することとなる持株会社かどうかを判断することとしている。
具体的には,持株会社グループが9条ガイドラインに掲げる3つの禁止類型のうち,いずれかに該当する場合に事業支配力が過度に集中することとなるとされている。 |
| (イ) |
当事行の持株会社グループ(東京三菱銀行及び三菱信託並びにこれら2行の国内の子会社及び実質子会社)が9条ガイドラインの3つの禁止類型に該当するか検討を行ったところ,いずれの禁止類型にも該当しないことから,本件統合により事業支配力が過度に集中することとはならないと判断した。 |
(3) 産業界に与える影響について
本件統合により,当事行は,上場会社約2,300社(金融会社を除く。)のうち,1,900社弱(約80%)に対して融資を行うこととなる。また,このうち当事行からの融資額の合算が第1位となる上場会社は約290社(約12%)となる。
このため,本件統合が産業界に与える影響について,当事行から融資を受ける事業者(上場会社及び中堅・中小会社)等に対し,アンケート調査及びヒアリング調査を実施した。
調査結果の主なポイントは,次のとおりである。
ア 本件統合の評価
事業会社へのアンケートの結果,本件統合に対する評価として,40%超の事業者が「サービスの向上」や「安定的な資金供給」を挙げた。一方,本件統合に対する懸念として,20%弱が「競争の減退」を挙げたほか,「経営関与が強まる」を選択したものは約25%に上った。
イ 個別事業者の経営に与える影響
| (ア) |
本件統合により,設備資金及び運転資金の調達の手段を変えるとする事業者は,それぞれ,約40%及び35%強であった。他方,設備資金及び運転資金の調達で代替的な資金調達手段がなく,資金調達の構成を変えられないとする事業者は,それぞれ,全体の20%強及び30%弱に上った。 |
| (イ) |
本件統合後,融資姿勢の変化に伴うリスクを回避するため,借入比率の調整を行うとしているものは,30%弱に上った。 |
| (ウ) |
借入条件については,60%強の事業者は,本件統合による影響は特にないとしているものの,15%強の事業者は,不利になると回答した。 |
| (エ) |
本件統合により,預金等借入以外の取引の要請,社債管理受託会社を自行にする要請等が現にある又は今後強まると見込んでいる事業者は約35%から約45%と高い比率となっている。 |
ウ 業界再編への影響
アンケートの結果,約75%の事業者が「特段の変化はない」としている。
エ 企業集団内取引への影響
| (ア) |
三菱金曜会(三菱系)は,東京三菱銀行,三菱信託等計28社の会長・社長をメンバーとして,定期的に会合を開催している。 |
| (イ) |
本件統合が,こうした企業集団にどのような影響を与えるかについてアンケート調査したところ,企業集団内外の取引の変化については,企業集団内外の事業者とも90%以上が特に変わらないとしており,企業集団が解消するとみている事業者は少なかった。また,企業集団の今後の動向については,企業集団に所属する事業者の約90%が,企業集団内の事業者同士の結び付きが維持・継続されるとの見方を有している。 |
(4) 独占禁止法及び競争政策上の取組
ア 独占禁止法及び競争政策上の問題点の指摘
当委員会は,上記(3)の調査結果を踏まえ,当事行に対して,次のとおり,独占禁止法及び競争政策上の問題点の指摘を行った。
(ア) 事業経営への関与について
| a |
本件調査の過程において,事業規模が拡大する当事行からの融資比率及び出資比率が高まる事業者は,銀行が次のような行為を行うこと等,自己の事業経営への関与を懸念している。
| (a) |
預金等借入以外の取引を行う(あるいは増やす)よう要請すること。 |
| (b) |
社債引受幹事を特定の証券会社とするよう要請すること。 |
| (c) |
社債の管理を当事行に行わせるよう要請すること。 |
|
| b |
融資比率や出資比率の高まりを背景として,上記のような行為を行い,当該「要請」に応じない場合不利益な取扱いをする旨を示唆する等,当事行の事業活動いかんによっては,不公正な取引方法(第19条)につながるおそれがあることから,今後の事業活動に際しては,自社の影響力を背景として,取引先事業者に不利益を被らせるような行為がないように所要の対応が図られる必要がある。 |
(イ) 企業集団について
当委員会の実施した累次の企業集団調査においては,集団内取引の割合は年々減少している等の実態がみられるところ,今般の調査によれば,上記(3)のとおり,企業集団内の取引に変化がなく企業集団内の事業者同士の結び付きが維持・継続されるとの見方が集団内外の事業者において多く,企業集団に属していることをもって取引先等の選別が行われ,排他的・閉鎖的な取引関係となるとの懸念がある。
イ 当事行からの申出
上記の指摘に対して,当事行からは次の申出があった。
(ア) 事業経営への関与について
これまでコンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つと考え,体制の整備と行内への浸透に鋭意取り組んできている。統合後も不公正な取引方法などの独占禁止法に違反する行為を行うことがないように,引き続きコンプライアンスの徹底に努めていく。また,新設する持株会社においてもコンプライアンス担当部署を設置,グループ全体のコンプライアンス機能を統括し,傘下銀行等のコンプライアンスの状況をモニタリングすることにより,独占禁止法遵守の更なる徹底を図る。
(イ) 企業集団について
三菱金曜会については,統合後も銀行中心の運営を行うつもりはない。三菱金曜会に属する企業内の統合等については,第一義的には,関係する企業内で主体的に検討される事項と認識しており,銀行から能動的に三菱金曜会メンバー間の統合を支援・推進していくことは考えていない。
(5) 当委員会の今後の対応
| ア |
本件統合について,相談のあった持株会社の設立及びその傘下に東京三菱銀行,三菱信託及び日本信託を置くことについては,独占禁止法上の規定に違反するおそれはないと認められた。
また,平成13年10月を目途とする当事行の更なる再編については,必要に応じて,改めて検討することとする。 |
| イ |
本件統合が産業界に与える影響に関して,当委員会からの指摘に対する当事行からの申出については,その実施状況を十分把握していくとともに,独占禁止法に違反すると認められる行為がある場合には,これに対して厳正に対処していくこととする。 |
6 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)によるジェイサット(株)の株式取得
(1) 本件の概要
ア 相談の概要
本件は,エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)(以下「NTT−C」という。)が,衛星通信事業を行っているジェイサット(株)(以下「JSAT」という。)に自社が保有する衛星2機の持分を譲渡するとともに,18.6%出資するものである。
イ 衛星通信市場の概要
| (ア) |
衛星通信事業は,第一種電気通信事業のうち,通信衛星により通信回線を設定し,これを専用回線として顧客に提供するものであり,地上局(送信局)から送られた電波を通信衛星に搭載されたトランスポンダ(電波中継器)で増幅し,地上局(受信局)に送信するものである。
第一種電気通信事業者が,国内サービスに使用中の静止衛星は,平成11年度末現在10機(JSAT5機,NTT−C2機,競争業者3機)である。 |
| (イ) |
新たな衛星を打ち上げる場合には,衛星の軌道位置・周波数について,国際調整が必要となる。
また,平成12年の電波法改正により,今後,後継機の免許申請を含め,同一の軌道位置・周波数に複数の事業者から電気通信業務用人工衛星局の免許申請があった場合には,競願処理手続において,手続の透明性や電波の有効利用等の観点から比較審査が行われることとなる。 |
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
本件においては,衛星による専用サービスは,同報性があること等の地上網の専用線サービスと異なる特徴を有していること,衛星による専用サービスのユーザーは地上局を設置する必要があるなど衛星通信サービスには特別な設備を要すること,衛星による専用サービスは地上網の専用線サービスと料金体系が異なること,また,衛星による専用サービスについては,衛星の軌道位置及び照射範囲等により,国内通信に向いているものと国際通信に向いているものに分かれていることから,衛星による国内専用サービスに一定の取引分野が成立すると判断した。
イ 競争への影響
(ア) 競争業者
NTT−Cは,現在,保有する衛星2機を自社内利用に用いているところ,当該衛星を用いて衛星通信サービスを行う場合には,有力な競争単位となり得るところ,本件行為により,衛星による国内専用サービスの競争単位は,JSATと競争業者の2社になる。
(イ) 隣接市場からの競争圧力
料金体系,同報性等の違いがあるものの,地上網を用いた専用線サービスは,衛星専用サービスと同じ用途の使用ができ,今後も光ケーブルの敷設,技術革新が進み,価格も低下していくと考えられることから,衛星による専用サービスに対する競争圧力は一定程度高まっていくと考えられる。
(ウ) 総合的事業能力
地上網を用いた専用線サービスにおいて圧倒的地位を有するNTT−Cが,本件行為により衛星通信分野において衛星の総数の3分の2を有することとなるJSATに出資することにより,NTT−Cの地上網とJSATの衛星網を組み合わせたシステム提案等が容易となり,JSATの総合的事業能力が高くなる。
ウ 問題点の指摘及び当事会社の対応
当委員会は,当事会社に対して,本件行為により,JSATの総合的事業能力が高くなることから,衛星による国内専用サービス分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の指摘を行った。
これに対し,当事会社からは,以下の措置を講ずる旨の申出があった。
| (ア) |
NTT−CとJSATとの間において行われる取引については,他の衛星通信事業者の取引と公平かつ適切な条件で行う。なお,衛星通信事業者と接続してサービスを提供する際は,接続協定等により適切な接続料金,技術的条件を定め,各衛星通信事業者と公平な条件で接続する。 |
| (イ) |
JSATがNTT−Cの購買力を使用することのないよう,共同資材調達は行わない。 |
| (ウ) |
NTT−CからJSATに対し,JSATが営業活動を行う際にNTT−Cの販売力を不当に使用できるような補助は行わない。 |
| (エ) |
NTT−CとJSATのタイアップ広告は実施しない。また,JSATが広告宣伝を行う場合には,NTT−Cのロゴ使用等,NTT−Cの広告宣伝力を使用できるような補助は行わない。 |
エ 当委員会の判断
当事会社が申し出た措置が講じられれば,本件行為により,アで画定した一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。
7 三菱瓦斯化学(株)と日本パーオキサイド(株)による共同生産会社の設立
(1) 本件の概要
本件は,三菱瓦斯化学(株)(以下「三菱瓦斯化学」という。)と日本パーオキサイド(株)(以下「日本パーオキサイド」という。)が,製造コストの引下げ等を目的として,共同出資により,過酸化水素の生産会社(以下「新会社」という。)を設立し,新プラントを建設するものである。
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
過酸化水素は,漂白剤をはじめ,工業薬品,医薬品など幅広い用途で使用されるが,本件においては,過酸化水素の製造販売分野に一定の取引分野が成立するものと判断した。
イ 競争への影響
当事会社のシェアを合算した場合,生産数量シェアでは約55%となる。また,販売数量シェアでは約50%弱となる。
しかしながら,以下の事情を総合的に勘案すれば,本件行為により,上記アで画定した取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。
| (ア) |
当事会社は,それぞれの既存工場の生産及び販売活動については,引き続き両社が独自に行い,新会社についても生産活動のみにかかわるものであり,物流を含め販売活動については,両社が独自に行うとしており,また,新会社を通じて当事会社の販売に関する情報交換が行われないようにするため,両社の営業部署に所属する者は,新会社の役員にしない等の措置を講ずる旨の申出があったこと。 |
| (イ) |
本件は,共同出資により生産会社を設立するものであるが,生産,事務経理等の新会社の業務は三菱瓦斯化学に委託すること,また,新会社における生産は,三菱瓦斯化学の製造技術により行われるが,その製造技術は日本パーオキサイド及び新会社には開示されないこと。 |
| (ウ) |
日本パーオキサイドは,将来の需要増加や経済情勢の変化に応じて,独自にプラントを新設できる権利を合弁契約上保持していること。 |
| (エ) |
過酸化水素市場においては,以下の事情が認められること。
| a |
競争業者の生産能力には余裕があり,また,競争業者の中には,輸入できる体制を整えているものが存在すること。 |
| b |
過酸化水素メーカー各社の製品に品質差はなく,ユーザーは,価格競争及び安定供給等のために複数メーカーから購入し,購入した製品を同じタンクに混ぜ合わせて使用していることから,いわゆる使い慣れの問題はなく,ユーザーは,取引先の変更が容易に行えること。 |
| c |
販売数量シェアが10%を超える有力な競争業者が複数存在すること。 |
|
8 日立電線(株)及び住友電気工業(株)の共同出資会社の設立による電力用電線事業の統合
(1) 本件統合の概要
本件は,日立電線(株)と住友電気工業(株)が,電力用電線の需要の減少等に対応するため,高圧用の電力用電線事業の合理化・効率化を推進し,安定した事業基盤の確保を図るために共同出資会社を設立し,両社の電力用電線事業を統合するものである。
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
電力用電線は,送電用電線と配電用電線に分類される。このうち,送電用電線は,さらに,鋼心アルミより線(以下「ACSR」という。),光ファイバー複合架空地線(以下「OPGW」という。)等の架空送電線と高圧・超高圧電力用電線に分類される。
本件においては,電線の製造方法,性能,用途等から,(ア)ACSR,(イ)OPGW,(ウ)66kV以上の高圧・超高圧電力用電線及び(エ)中・低圧の配電用電線のそれぞれの製造・販売について,一定の取引分野が成立すると判断した。
イ 競争への影響
(ア) 市場シェア
本件統合により,送電用電線の各市場(ACSR,OPGW,66kV以上の高圧・超高圧電力用竜線をいう。以下同じ。)における両社の出荷数量シェアが,いずれも40%前後となり,その順位が第1位となることに加えて,上位3社の累積シェアが7割から8割程度となる。
配電用電線については,当事会社の合算シェアが約35%で,その順位が第1位となるが,シェアが10%を超える有力な事業者が複数存在するほか,国内には電線メーカーが多数存在する。
(イ) 輸入及びユーザー等の状況
電力用電線の主要なユーザーは電力会社であるところ,輸入については,低圧の配電用電線等について一部行われているものの,超高圧の電力用電線については電線自体の購入と敷設工事が一括して発注されていること等から,電力用電線全体では1%程度と低い割合にとどまっている。
ウ 問題点の指摘及び当事会社の対応
| (ア) |
当委員会は,上記の状況を踏まえた場合,アで画定した取引分野のうち,送電用電線の各市場について,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨,当事会社に対し問題点を指摘した。
これに対し,当事会社からは,電力用電線の研究開発及び生産については統合の対象とするが,電力会社等に対する販売事業については,引き続き,両社がそれぞれ行うこととする旨の申出があった。 |
| (イ) |
当委員会は,当事会社による当委員会からの問題点の指摘を踏まえた統合内容及び電力会社がコスト抑制の観点から電力用電線の購入に当たり価格志向を強めてきている等の最近の市場環境を踏まえた場合,本件統合により,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。 |
9 三井化学(株)及び武田薬品工業(株)の共同出資会社の設立によるウレタン事業等の統合
(1) 本件統合の概要
本件は,三井化学(株)(以下「三井化学」という。)と武田薬品工業(株)(以下「武田薬品」という。)が,欧米企業の競争力強化に対抗するため,両社の事業を統合することにより収益力を強化するとともに,生産,物流及び販売におけるコスト削減等を図ることを目的として共同出資会社を設立し,両社のウレタン事業を統合するものである。
武田薬品は,共同出資会社の営業開始5年後には,当該共同出資会社の持分全株式を三井化学に譲渡することとしている。
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
本件においては,統合の対象であるウレタン原料ごとに一定の取引分野が成立すると判断した。
イ 競争への影響
上記アで画定した取引分野のうち,競争への影響が大きいと考えられる軟質ウレタンフォーム等の原料であるTDIの製造・販売分野についての検討結果は,次のとおりである。
(ア) 市場シェア
本件統合により,TDIに係る両社の販売数量シェアが60%弱でその順位が第1位となる上,上位3社の累積集中度が約90%となる。また,当事会社のTDIの生産能力シェアが80%程度となる。
(イ) 競争業者の状況
TDI市場においては,販売数量シェアで10%を超える競争業者が2社存在する。
また,国内メーカーのTDI生産の稼働率は高いところ,生産数量の7割程度を輸出している当事会社に比べ,国内の競争業者の輸出比率は低いことから,競争業者が現在の販売数量以上に国内に供給する余力は少ない。
(ウ) 輸入
輸入については,近年ではほとんど実績はない。
また,ユーザーが輸入をするためには,港湾地区のタンクが必要であるところ,これを自ら手当てするとなると相当量の輸入をする必要があることから,大手ユーザーを除けばユーザーが自ら輸入を行う環境が十分には整っていない。
(エ) ユーザーの状況等
TDIはメーカー間に品質差がないところ,ユーザーである大手ウレタンフォームメーカー等は複数メーカーから購入している。
また,ユーザーは,海外市況や原料であるナフサの価格動向等を踏まえ,メーカーと価格交渉を行っている。
ウ 問題点の指摘及び当事会社の対応
| (ア) |
当委員会は,上記の状況を踏まえた場合,TDIの製造・販売分野について,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の問題点を当事会社に対し指摘した。
これに対し,当事会社からは,次の問題解消措置を講ずる旨の申出があった。
| a |
国内市場の十数パーセントに相当する7,000トンのTDIについて,2年以内に長期的生産受委託契約を締結することにより,コストベースでの引取権を競争業者に提供する。 |
| b |
当事会社が保有する港湾地区のタンクをユーザー等の希望に応じ提供する。 |
|
| (イ) |
当委員会は,当事会社の問題解消措置が講じられた場合,ユーザーが複数購買を行っている状況の下で,競争業者が当該引取権分の供給力を増加させることにより,国内市場における当事会社に対する競争力が強化されること,また,アジア地区等においてTDIプラントの新増設が計画されているといった状況から,タンクの提供を受けることによって輸入が容易となることが期待できることを踏まえれば,本件統合により,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。 |
10 第二電電(株),ケイディディ(株)及び日本移動通信(株)の合併(新会社名 ケイディーディーアイ(株))
(1) 本件の概要
本件は,第一種電気通信事業者である第二電電(株),ケイディディ(株)及び日本移動通信(株)が,電気通信事業における規制緩和,技術革新等の環境変化を踏まえ,国際通信,国内通信及び移動体通信(携帯電話及びPHS)を全国で提供する体制を整えることを目的に合併するものである。
電気通信事業については,国際通信と国内通信に大別され,さらに国内通信については,地域通信及び長距離通信に分類される。
電気通信分野においては,規制緩和が進展したこと等から,新規参入が相次ぎ,また,外資規制の緩和等により内外の事業者間の資本参加,業務提携等が進み,事業者間で活発な競争が行われている。
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
本件においては,国際通信分野,長距離通信分野及び移動体通信分野のそれぞれについて,一定の取引分野が成立すると判断した。
また,移動体通信分野については,全国を9に分けたブロックごとに事業の認可が与えられており,事業者はそれぞれのブロック内で事業活動を行っていることから,ブロックごとについて検討の対象とした。
イ 競争への影響
以下の事情を総合的に勘案すれば,本件合併により,アにおいて画定したいずれの取引分野においても,競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。
(ア) 国際通信分野
当事会社のうちケイディディ(株)は,電気通信自由化前において唯一の国際通信事業者であったことから,現在でもなお国際通信分野において高いシェアを有しており,当事会社の国際通信分野におけるシェアは,合算すると60%超であり,その順位は第1位となる。
しかしながら,本件合併によるシェアの増加分はごくわずかであり,かつ,国際的に総合的事業能力の高い外国事業者から出資を受けた競争業者が複数存在する。
また,国際通信分野においては,新規事業者の参入により価格競争が活発に行われてきた結果,通話料は数次にわたり大幅に低下してきており,最近においても,外資系事業者を含め有力な事業者が参入し,引き続き競争が活発に行われている。
さらに,国内の電気通信分野において極めて有力な事業者グループに属する会社が国際通信分野に参入したところ,当該会社は現時点では参入したばかりであるものの,当該グループの国内の電気通信分野における地位等にかんがみれば,当該会社は潜在的に非常に高い競争力を有しているものと評価でき,今後国際通信分野において有力な事業者となっていくことが見込まれる。
加えて,「公専公」の解禁により第二種電気通信事業者の参入が本格化し,競争圧力として機能すると考えられる。
(イ) 長距離通信分野
当事会社の長距離通信分野におけるシェアは,合算すると20%弱であり,その順位は第2位となる。
しかしながら,他に第1位で60%超のシェアを有する事業者をはじめ有力な競争業者が複数存在する。
また,長距離通信分野においては,価格競争が活発に行われてきたところ,最近においても,有力な事業者が参入し,引き続き競争が活発に行われている。
(ウ) 移動体通信分野
本件合併によって,当事会社の合算シェアは,関東ブロックにおいて25%超,東海ブロックにおいて30%超となり,その順位はいずれも第2位となる。
しかしながら,両ブロックにおいて5割程度のシェアを占める第1位の事業者を含め,有力な競争業者が複数存在する。
また,移動体通信分野においては,価格競争が活発に行われてきたところ,最近においては,価格競争に加え,技術,付加価値サービスなどの面における競争も活発に行われている。
11 (株)住友銀行と(株)さくら銀行の合併等
(1) 本件の概要
本件は,(株)住友銀行(以下「住友銀行」という。)及び(株)さくら銀行(以下「さくら銀行」という。)が,銀行業界の再編の進展等による競争の激化等に対処するため,住友銀行を存続会社として合併するものである(新会社の名称は「(株)三井住友銀行」)。
また,当事行は,さくら銀行の証券子会社であるさくら証券(株)の営業のすべてを,住友銀行の関連証券会社である大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ(株)へ営業譲渡する。
(2) 独占禁止法上の検討(関係法条 第15条及び第16条)
ア 一定の取引分野について
本件については,金融分野における競争への影響の検討に当たり,次のとおり一定の取引分野が成立すると判断した。
(ア) 預金業務
主として全国市場について,全国に店舗を置いて営業展開する都市銀行(9行),長期信用銀行(3行)及び信託専業銀行(6行)ベースで検討し,地域市場(都道府県)については,その地域に店舗を置いて営業展開する地方銀行等を含めて検討することとした。
(イ) 貸出業務
主として全国市場について,全国に店舗を置いて営業展開する都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースで検討し,地域市場(都道府県)については,その地域に店舗を置いて営業展開する地方銀行等を含めて検討することとした。
(ウ) 外国為替業務
外国為替取引は,「対顧客取引」と「インターバンク取引」とに分けられるところ,いずれも,東京外国為替市場で活動する全金融機関ベースで検討することとした。
(エ) 証券業務
株式及び債券に係る引受業務及び売買業務のそれぞれにおいて,一定の取引分野が成立すると判断した。
イ 競争への影響の検討
上記アで画定した取引分野のうち,競争への影響が大きい預金,貸出し及び債券の引受業務についての検討の結果は次のとおりであり,いずれの取引分野においても競争を実質的に制限することとはならないと判断される。
(ア) 預金業務について
本件合併等による都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースでの合算シェアは20%強で,その順位は第2位となる。また,他の都市銀行等が統合を予定していることから,上位行の集中度が高まることとなる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| a |
個人預金が株式,投資信託等の代替的な金融商品に流入し,隣接市場を形成する証券会社,投資信託委託会社,保険会社等が提供する金融商品が競争圧力となっていること。 |
| b |
隣接市場を形成する商品である郵便貯金(平成12年3月末における貯金残高は約260兆円)が競争圧力となっていること。 |
| c |
低コストを反映した高い利回りを実現するインターネット専業銀行やコンビニエンスストアを利用した24時間サービスを行う銀行としての他業種からの参入が予定されていること。 |
| d |
各銀行は金利優遇商品や懸賞付き商品など独自性のある多様な預金商品を提供し,預金獲得競争を展開していること。 |
| e |
都市銀行等の有力な競争業者が存在すること。
|
また,地域市場についてみた場合,当事行の合算シェアが第1位となる都道府県はない。 (イ) 貸出業務について
本件合併等による都市銀行,長期信用銀行及び信託専業銀行ベースでの合算シェアは約20%で,その順位は第2位となる。また,他の都市銀行等が統合を予定していることから,上位行の集中度が高まることとなる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| a |
資金調達手段が多様化され,大企業は社債,コマーシャルペーパー売掛債権流動化等の間接金融によらない資金調達を進めており,隣接市場からの競争圧力が働くこと。 |
| b |
aの状況の下で,一般に,信用リスクが低く,貸出額の大きい大企業向け貸出しは,縮小傾向にあるところ,資金調達の一部に間接金融を利用する大企業に対する貸出しについては,他の都市銀行等の有力な競争業者が存在すること。 |
| c |
都市銀行等が中小企業向け貸出しの強化・拡大を図っており,活発な競争が行われるものと見込まれること。 |
| d |
個人向け貸出しは,多様なローン商品の開発,金利優遇,手続利便性の向上等をめぐり,他の都市銀行等の有力な競争業者との間で活発な競争が行われるものと見込まれること。 |
また,兵庫県においては,結合関係のある地方銀行のシェアを加算すると,当事行のシェアが30%を超え,その順位は第1位となるが,上記a〜dの状況に加え,同県には地方銀行,信用金庫等多数の地域金融機関が存在しており,大企業向け貸出し及び中小企業向け貸出しともに競争が活発な状況にあると認められる。 (ウ) 債券の引受業務について
当事行と結合関係のある証券会社を加えた場合,社債の引受高の合算シェアが約20%で,その順位は第1位となる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| a |
今後,企業の資金調達手段として直接金融が伸張し,証券市場が拡大することにより,競争は活発化すると見込まれること。 |
| b |
商品開発力,販売力等の事業能力が高い大手証券会社等が有力な競争業者として存在すること。 |
| c |
公社債の引受業務においては,銀行の証券子会社の躍進が著しいところ,これら有力な競争業者が存在すること。 |
| d |
外資系証券会社が当該分野で業績を大きく伸ばしていること。 |
(3) 産業界に与える影響について
本件合併等により,当事行は,上場会社約2,300社(金融会社を除く。)のうち,1,400社強(60%強)に対して融資を行うこととなる。また,このうち当事行からの融資額の合算が第1位となる上場会社は350社弱(約15%)となる。
このため,本件合併等が産業界に与える影響について,当事行から融資を受ける事業者(上場会社及び中堅・中小会社)等に対し,アンケート調査及びヒアリング調査を実施した。
調査結果の主なポイントは,次のとおりである。
ア 本件合併等の評価
事業会社へのアンケートの結果,本件合併等に対する評価として,約40%の事業者が「情報提供能力等の向上」を挙げた。一方,本件合併等に対する懸念として,30%弱が「サービスの低下」を挙げた。
イ 個別事業者の経営に与える影響
| (ア) |
本件合併等により,設備資金及び運転資金の調達の手段を変えるとする事業者は,それぞれ,約40%及び約35%であった。他方,設備資金及び運転資金の調達で代替的な資金調達手段がなく,資金調達の構成を変えられないとする事業者は,全体の25%程度に上った。 |
| (イ) |
本件合併等後,融資姿勢の変化に伴うリスクを回避するため,借入比率の調整を行うとしている事業者は,半数以上に上った。 |
| (ウ) |
借入条件については,60%強の事業者は,本件合併等による影響は特にないとしているものの,15%弱の事業者は,不利になると回答した。 |
| (エ) |
本件合併等により,預金等借入以外の取引の要請,社債引受幹事を特定の証券会社とすることの要請等が現にある又は今後強まると見込んでいる事業者は30%弱から40%強と高い比率となっている。 |
ウ 業界再編への影響
アンケートの結果,約70%の事業者が「特段の変化はない」としている。
エ 企業集団内取引への影響
| (ア) |
白水会(住友系)は,住友銀行等計20社の社長をメンバーとし,二木会(三井系)は,さくら銀行等計25社の社長をメンバーとして,定期的に会合を開催している。 |
| (イ) |
本件合併等が,こうした企業集団にどのような影響を与えるかについてアンケート調査したところ,企業集団内外の取引の変化については,企業集団内外の事業者とも80%以上が特に変わらないとしており,企業集団が解消するとみている事業者は少なかった。また,企業集団の今後の動向については,企業集団に所属する事業者の80%強が,企業集団内の事業者同士の結び付きが維持・強化されるとの見方を有している。 |
(4) 独占禁止法上及び競争政策上の取組
ア 独占禁止法上及び競争政策上の問題点の指摘
当委員会は,上記(3)の調査結果を踏まえ,当事行に対して,次のとおり,独占禁止法上及び競争政策上の問題点の指摘を行った。
(ア) 事業経営への関与について
| a |
本件調査の過程において,事業規模が拡大する当事行からの融資比率及び出資比率が高まる事業者は,銀行が次のような行為を行うこと等,自己の事業経営への関与を懸念している。
| (a) |
預金等借入以外の取引を行う(あるいは増やす)よう要請すること。 |
| (b) |
社債引受幹事を特定の証券会社とするよう要請すること。 |
| (c) |
社債の管理を当事行に行わせるよう要請すること。 |
|
| b |
融資比率や出資比率の高まりを背景として,上記のような行為を行い,当該「要請」に応じない場合不利益な取扱いをする旨を示唆する等,当事行の事業活動いかんによっては,不公正な取引方法(第19条)につながるおそれがあることから,今後の事業活動に際しては,自社の影響力を背景として,取引先事業者に不利益を被らせるような行為がないように所要の対応が図られる必要がある。 |
(イ) 企業集団について
当委員会の実施した累次の企業集団調査においては,集団内取引の割合は年々減少している等の実態がみられるところ,今般の調査によれば,上記(3)のとおり,企業集団内の取引に変化がなく企業集団内の事業者同士の結び付きが維持・強化されるとの見方が集団内外の事業者において多く,企業集団に属していることをもって取引先等の選別が行われ,排他的・閉鎖的な取引関係となるとの懸念がある。
イ 当事行からの申出
上記の指摘に対して,当事行からは次の申出があった。
(ア) 事業経営への関与について
独占禁止法に違反する行為がないように,引き続き,コンプライアンス・マニュアル等の関連規定の制定,教育・研修の実施,役職員向けマニュアル・ハンドブックの配布等の施策を行内で実施することにより,法令遵守について役職員への周知体制を徹底し,自律的な法令遵守機能が働くよう最尽力していく。
(イ) 企業集団について
排他的な企業集団を形成する意図は持っておらず,白水会と二木会を統合する考えはない。白水会・二木会の運営についても,銀行中心の運営を行うつもりはない。また,白水会・二木会に属する企業間の統合を支援・促進していく考えはなく,新銀行が主導的に白水会・二木会内の事業者間の結び付きを強化・拡大するような動きをすることはない。
(5) 当委員会の今後の対応
| ア |
住友銀行とさくら銀行の合併及び両行の証券子会社と関連証券会社との間の営業譲渡については,独占禁止法上の規定に違反するおそれはないと認められた。 |
| イ |
本件合併等が産業界に与える影響に関して,当委員会からの指摘に対する当事行からの申出については,その実施状況を十分把握していくとともに,独占禁止法に違反すると認められる行為がある場合には,これに対して厳正に対処していくこととする。 |
12 日本短資(株),山根短資(株)及び名古屋短資(株)の合併について(新会社名 セントラル短資(株))
(1) 本件の概要
| ア |
本件は,日本短資(株),山根短資(株)及び名古屋短資(株)の3社が,低金利政策の長期化や即時グロス決済の導入等の短期金融市場の変化に対して,重複部門,拠点の統合等による経営の効率化及びより強固となる財務基盤を背景に積極的な業務展開を図るために合併するものである。 |
| イ |
短期金融市場は,金融機関が資金決済取引を行うインターバンク市場と,一般事業会社及び金融機関が短期的な資金運用を行うオープン市場とに大別される。
インターバンク市場はコール市場(有担保・無担保)と手形市場とに,オープン市場は譲渡性預金(CD)市場,コマーシャルペーパー(CP)市場,短期国債証券(TB)市場,債券レポ(貸借取引)市場等に大別されるものの,短期資金を取り扱うという点では同一の機能を果たしており,代替性が認められる。 |
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
本件においては,インターバンク市場及びオープン市場のそれぞれにおいて一定の取引分野が成立するものと判断した。
イ 競争への影響
本件合併においては,以下の事情を総合的に勘案すれば,アで画定した取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。
(ア) インターバンク市場
当事会社のインターバンク市場における取扱高シェア(短資会社6社ベース)は,合併後45%強で,その順位は第1位となる。
しかしながら,次のような状況が認められる。
| a |
主要な資金の取り手である都市銀行は,即時グロス決済制度の導入前から,短資会社を経由しないで金融機関同士で直接行う資金決済取引(以下「DD取引」という。)を増加させている。DD取引の規模は,コール市場における取引高の3割程度に上っており,今後もさらに増加するものと見込まれ,これらDD取引の競争圧力が存在する。 |
| b |
最近では,上記のような市場環境を踏まえ,大口取引先からの手数料の値下げ圧力が強くなっていることから,短資会社の仲介手数料の引下げ競争が進んでいる。 |
| c |
手形市場では,日銀が手形オペの参加資格を銀行や系統金融機関にも広げたことから,新規参入がなされている。 |
(イ) オープン市場
オープン市場における主要な取引(CD,CP,TB等)の取扱高について,銀行,証券会社等金融機関を含めた全市場参加者ベースのシェアをみると,当事会社のシェアは,市場全体で15%弱にとどまる。
また,オープン市場においては,短資会社は,他の市場参加者と同じくディーリング取引の当事者の1つとして参加するものであり,都市銀行や大手証券会社といった有力な競争者が多数存在する。
13 日鉱金属(株)と三井金属鉱業(株)の銅製錬関連事業に関する共同出資会社の設立等
(1) 本件の概要
| ア |
日鉱金属(株)(以下「日鉱金属」という。)と三井金属鉱業(株)(以下「三井金属」という。)は,銅製錬関連事業について,コスト競争力の向上を図り,国際競争力を確保することを目的として,原料調達の共同化,生産受委託の拡大等を行うとともに,当事会社の銅製錬関連事業製品を販売する共同出資会社(出資比率は日鉱金属が65%,三井金属が35%)を設立するものである。 |
| イ |
銅は,LME(ロンドン金属取引所)で取引される国際商品であり,LMEで品位基準を定めている。我が国で製造される銅の品位は99.99%以上である。
国内の価格は,LME価格に連動して推移しており,また,銅は,国内の販売数量に占める輸入数量の割合が高く,近年においては約20%前後で推移している。
銅の主たるユーザーは,電線メーカー及び伸銅品メーカーである。 |
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
本件においては,銅の製造販売分野に一定の取引分野が成立すると判断した。
イ 競争への影響
本件行為により,当事会社の合算シェアが,製造分野で約40%で,その順位が第1位となり,また,販売分野で約30%で,その順位が第1位となる。
しかしながら,以下の事情を総合的に勘案すれば,本件行為により,アで画定した取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。
| (ア) |
銅は,内外メーカーによる品質の差はなく,また,国産品と輸入品の価格差もないことから,輸入品の割合が高く,近年においても輸入品が国内需要の約20%前後を占めており,輸入品が競争圧力として働いていると考えられること。 |
| (イ) |
銅の国内販売価格は,LME価格と連動して推移している状況にあることから,大手銅製錬メーカーであっても,市場価格を左右することは困難であること。 |
| (ウ) |
国内における生産数量シェアが20%を超える大手の競争業者を含め,10%を超す有力な競争業者が複数存在し,これらは,販売数量でも10%を超すシェアを有していること。 |
| (エ) |
大口ユーザーである電線メーカー等は,複数購買を行っているとともに,自ら海外のいわゆる産銅メジャー等から銅を輸入していること。 |
14 A社によるB社の株式取得
(1) 本件の概要
本件は,X製品の製造販売分野で第1位のA社が,第4位のB社の発行済株式総数の過半数を取得しようとするものである。
(2) 独占禁止法上の考え方
ア 一定の取引分野
本件における一定の取引分野については,X製品は,品種ごとに性能,用途,価格帯等が異なることから,X製品の品種ごとに成立するものと判断した。
イ 競争への影響及び問題となり得る点についての指摘
当委員会は,当事会社に対し,以下の事情を総合的に判断すると,アで画定したX製品の各品種の製造販売分野において競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の指摘を行った。
(ア) 当事会社の地位及び市場の状況
本件行為によって,X製品の各品種の製造販売分野において,当事会社の合算シェアが40%を超えるものが複数あり,一部の品種では,当事会社の合算シェアが70%超となる。
また,これらの品種では,上位3社の累積集中度が70%ないし90%程度と高くなる。
(イ) 輸入
X製品は,現在,一部輸入されているものがあるものの,その割合は低く,増加傾向も認められない。
また,X製品は保守・メンテナンスが重要であり,海外製品の仕様が国内とは異なっているため国内仕様に変更する必要もあることから,今後とも輸入が国内市場に与える影響は小さい。
(ウ) ユーザーの状況
ユーザーは都道府県単位で活動しており,中小規模の事業者が多く,価格交渉力が強いとはいえない。
ウ 当事会社の対応
当事会社に対し,上記の点を指摘したところ,当事会社からは,本件行為を行わない旨の申出があった。
|