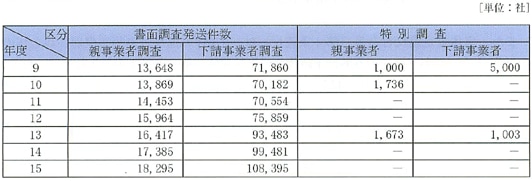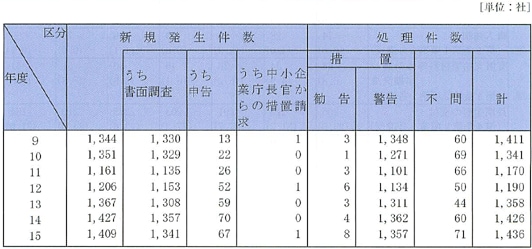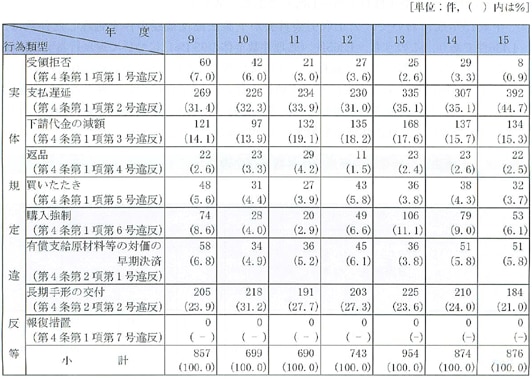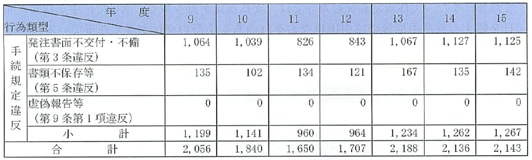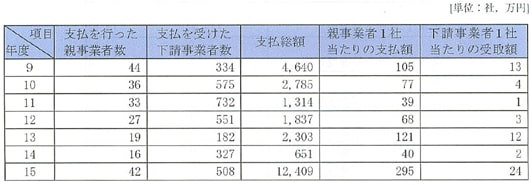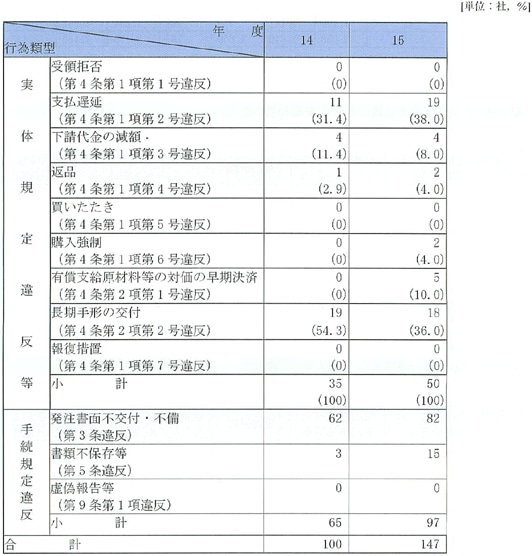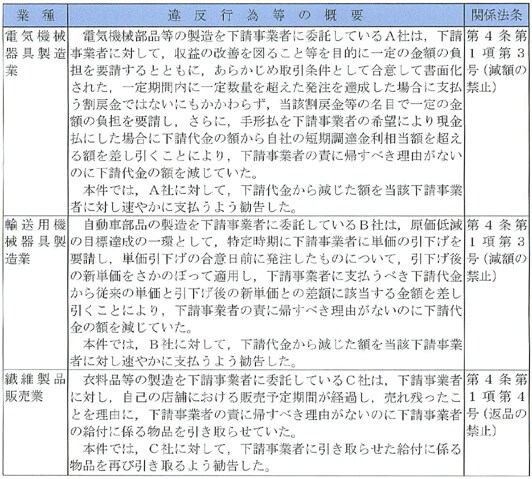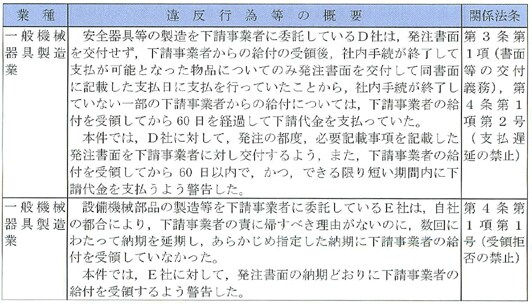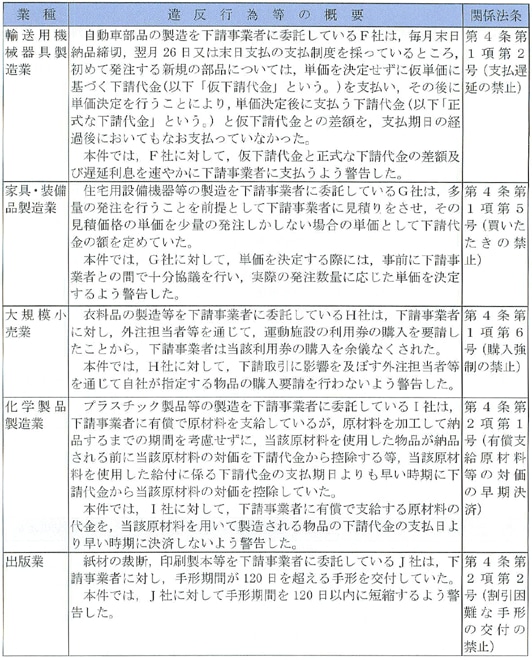|
1 調査の趣旨
下請法は,平成15年6月に改正が行われ,新たにソフトウェア制作業,テレビ番組制作業等における情報成果物の作成に係る下請取引及びビルメンテナンス業等における役務の提供に係る下請取引が同法の対象となった。これらの業種における取引慣行等の中には,下請法の施行後においては,同法に違反することとなるものがあることも見込まれることから,このような点を踏まえ,ソフトウェア制作業,テレビ番組制作業,広告制作業及びビルメンテナンス業における下請取引の実態を調査し,下請法上問題となる取引慣行を指摘するとともに,下請法の内容を詳細に紹介することにより,関係事業者による同法違反行為の未然防止に資するため,調査結果を公表した(平成16年2月13日公表)。
2 調査方法
ソフトウェア制作業3,103社〔回収率34.0%〕,テレビ番組制作業1,000社〔同42.7%〕,広告制作業1,000社〔同35.1%〕,ビルメンテナンス業2,509社〔同34.3%〕
平成15年10月31日発送,11月18日締切り
(ソフトウェア制作業〔3団体,50社〕,テレビ番組制作業〔3団体,35社〕,広告制作業〔3団体,35社〕,ビルメンテナンス業〔10団体,35社〕)
3 調査結果及び主な留意点
下請法第3条第1項は,親事業者に対して,必要記載事項を記載した書面を,発注時に,直ちに交付することを義務付けている。
調査結果によると,親事業者が発注の際に書面を交付する状況は,
| ○ |
ソフトウェア制作業では,書面で発注するものが9割強あるが,発注の際に直ちに書面を交付するものは約4割にとどまっている。 |
| ○ |
テレビ番組制作業では,書面で発注するものが約4割にとどまり,残りは口頭等で発注している。 |
| ○ |
広告制作業では,書面で発注するものが約2割にとどまり,残りは口頭等で発注している。 |
| ○ |
ビルメンテナンス業では,書面で発注するものが9割弱あり,そのうち,発注の際に直ちに書面を交付するものが約9割となっている。 |
改正下請法の施行後は,親事業者は同法に定められる必要記載事項をすべて記載した書面を,発注後直ちに交付しなければならない(例外的に,発注時に内容が確定できないことに正当な理由がある事項に限り,記載せずに書面を交付することが認められる)。したがって,特に,テレビ番組・広告制作業のように口頭発注が一般的な業界や,ソフトウェア制作業のように発注書面の交付が遅れがちな業界においては,関係事業者は,発注時に必要記載事項を記載した書面を交付することができるように発注体制を見直す必要がある。
下請法第4条第1項第3号は,親事業者が,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減ずることを禁止している。
調査結果によると,親事業者の下請代金の減額の状況は,
| ○ |
ソフトウェア制作業では,発注元が親事業者に支払う代金の引下げによる減額が時々あるとするものが1割弱となっている。 |
| ○ |
テレビ番組制作業では,親事業者の経営の悪化による減額が時々あるとするものが1割弱となっている。 |
| ○ |
広告制作業では,発注元が親事業者に支払う代金の引下げによる減額が時々あるとするものが2割弱,親事業者の経営の悪化による減額があるとするものが約1割となっている。 |
| ○ |
ビルメンテナンス業では,発注元のテナント退去等による減額が時々あるとするものが約2割,発注元が親事業者に支払う代金の引下げによるものがあるとするものが約1割となっている。 |
親事業者が,上記の理由により下請代金を減額することは,下請法上,問題となる。調査対象4業種においては,これらの下請代金の減額が頻繁に生じているとまではいえないものの,関係事業者においては,改正下請法の施行を機に,これらの事由により下請代金を減額することのないよう,さらに留意することが重要である。
下請法第4条第1項第2号は,親事業者に対して,情報成果物の受領(役務の提供)後60日以内に定めた支払期日に代金を支払うことを義務付けている。
調査結果によると,親事業者の下請代金の支払い遅延状況は,
| ○ |
ソフトウェア制作業では,検査の未了による支払遅延が時々あるとするものが約1割となっている。 |
| ○ |
テレビ番組制作業では,親事業者の事務処理の遅れによる支払遅延が時々あるとするものが2割弱,下請代金交渉の遅れによるものが1割弱となっている。 |
| ○ |
広告制作業では,親事業者の事務処理の遅れによる支払遅延が時々あるとするものが3割弱,下請代金交渉の遅れによるものが2割強,発注元の代金支払の遅れによるものが2割弱,親事業者の経営の悪化によるものが約1割,検査の未了によるものが1割強となっている。 |
| ○ |
ビルメンテナンス業では,親事業者の事務処理の遅れによる支払遅延が時々あるとするものが1割強となっている。 |
親事業者が,上記の理由により支払期日に代金を支払わない場合は,下請法上問題となる。調査対象4業種においては,これらの理由による支払遅延が頻繁に生じているとまではいえないが,関係事業者においては,改正下請法の施行を機に,下請代金の支払いを遅延することのないよう,更に留意することが重要である。とりわけ,広告制作業のように多くの理由で支払遅延が起こっている業界においては,特に注意が必要である。
下請法第4条第2項第4号は,親事業者が,下請事業者の作業の途中で発注内容を変更することにより,又は下請事業者から情報成果物を受領した(役務の提供を受けた)後にそれをやり直させることにより,下請事業者の利益を不当に害することを禁止している。
調査結果によると,関係事業者における発注内容の変更及びやり直しの状況については,
| ○ |
ソフトウェア制作業では,発注内容の変更があるとするものが6割強あるが,そのうち,費用を下請事業者が全額負担するものが1割弱,費用負担を協議して決めるとするものが5割強となっている。また,親事業者又は発注元の意向によるやり直しが時々あるとするものが3割前後あるが,そのうち,費用を下請事業者が全額負担するものが1割弱,両者が協議して決めるとするものが約5割となっている。 |
| ○ |
テレビ番組制作業では,発注内容の変更が時々あるとするものが6割強あり,そのうち,費用負担を協議するが,おおむね下請事業者が全額負担するものが1割強となっている。また,親事業者又は発注元の意向によるやり直しが時々あるとするものが約3割あり,そのうち,費用負担を協議するが,おおむね下請事業者が全額負担するものが約1割となっている。 |
| ○ |
広告制作業では,発注内容の変更が時々あるとするものが7割弱あるが,そのうち,費用負担を協議するが,おおむね下請事業者が全額負担するものが約1割となっている。また,親事業者又は発注元の意向によるやり直しが時々あるとするものが約7割あり,そのうち費用負担を協議するが,おおむね下請事業者が全額負担するものが1割強となっている。 |
| ○ |
ビルメンテナンス業では,発注内容の変更があるとするものが約3割あり,そのうち,費用を下請事業者がほとんど又は全額負担するものが,それぞれ1割前後となっている。また,発注元の意向によるやり直しが時々あるとするものが4割弱あり,そのうち,費用を下請事業者が全額負担するものが約4割,費用負担を協議して決定するものが6割弱となっている。 |
親事業者が,親事業者又は親事業者の顧客の意向等,下請事業者の責めに帰さない理由により,費用を負担せずに発注内容を変更し又はやり直させることは,下請事業者に不当に不利益を与え下請法上問題となる。調査対象4業種においては,発注内容の変更,やり直しがかなり多いところ,各業種の関係事業者においては,下請事業者の責めに帰さない理由により発注内容を変更したり,やり直させたりする場合は,その費用を負担することで,下請事業者に不当に不利益を与えないようにすることが重要である。
4 公正取引委員会の対応
公正取引委員会では,個々の事業者が,調査結果等を踏まえ,改正下請法違反行為の未然防止に向けた十分な準備を進めることができるよう,調査対象4業種の関係18団体に対し,構成事業者等に対する周知を要請した。
|