第1 本件の概要
本件は,電力用電線ケーブル等の製造販売業を営む住友電気工業株式会社(以下「住友電工」という。)及び日立電線株式会社(以下「日立電線」という。)が,両社が平成13年に折半出資により設立した,株式会社ジェイ・パワーシステムズ(以下「JPS」という。)に電力用電線の国内の電力会社向け販売事業を譲渡することを計画したものである。
本件の関係法条は,独占禁止法第16条である。
第2 製品の概要
電力用電線は,電気エネルギーを輸送することを役割とする電線であり,送電用電線と配電用電線に大別される。
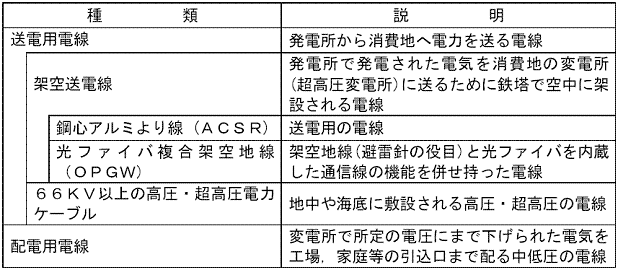
上表の各電力用電線は,それぞれ性能・用途等が基本的に異なるものである。
なお,配電用電線は,屋外用ビニル絶縁ケーブル,引込用ビニル絶縁電線等多くの種類があるが,電線メーカー各社はいずれも基本的にこれらの製品を製造しており,その基本的な製造方法は同一であって,製品相互の製造の切替えが容易である。
第3 一定の取引分野
電力用電線の性能,用途等が基本的に異なることから,本件における一定の取引分野の商品の範囲は,ACSR,OPGW,66KV以上の高圧・超高圧電力ケーブル及び配電用電線のそれぞれの製造・販売分野について画定される。
また,当事会社は全国で事業活動を行っており,特段の事情もないことから,地理的範囲は全国に画定される。
第4 取引分野ごとの検討
送電用電線の需要先のほとんどが電力会社であり,かつ,本件統合の対象が国内の電力会社向けの販売であることから,国内の電力会社向けを中心に検討した。
なお,取引分野ごとの検討に当たっては,別途計画されている同業他社の統合が実行された場合を想定している。
1 送電用電線について
(1) ACSRについて
ア 市場の状況
ACSRの平成15年度の国内出荷額は約50億円であるが,国内需要は,著しい減少傾向にあり(平成15年度の市場規模は,平成12年度の約3分の1),今後もこの傾向は続く見込みである。
本件統合により,当事会社の合算出荷数量シェア・順位は約40%・第1位となる(統合後のHHI 約3,200・HHIの増加分 約800)。ただし,年度ごとのシェアの変動が大きいため,平成12年度から平成15年度のシェアを加重平均した(他の種類の電力用電線についても同じ。)。
| 順位 | 会社名 | シェア |
|---|---|---|
| 1 | A社 | 約30% |
| 2 | B社 | 約30% |
| 3 | 日立電線 | 約20% |
| 4 | 住友電工 | 約20% |
| その他 | 0~5% | |
| (1) | 当事会社合算 | 約40% |
| 合計 | 100% |
(出所:調査結果を基に当委員会において作成)
(注)1 その他には輸入も含む。
(注)2 四捨五入しているため,合計は一致しない。
イ 考慮事項
(ア) ユーザーの購買方法
電力会社は,著しい需要の減少から,年間に一括して発注先を決定する年間契約方式を基本として,一部にスポット契約により発注先を決定している。その際,電力会社は,ACSRの原材料となるアルミの国際市況等をベースにして自社でも購入単価を積算しており,基本的に当該単価を基準に入札価格又は見積価格を評価している。
また,各電力会社の上位発注先は,当事会社を含む大手電線メーカーがほとんどであるが,受注資格を得るための型式審査(いずれの電力会社でも実施している事前の製品検査)に合格しているメーカーには,他の一部国内メーカーや海外メーカーも存在しており,一部の電力会社は実際に輸入品を採用している。
(イ) ユーザーの取引先変更の容易性
型式審査に合格している電線メーカーの製品には品質差はないため,電力会社は取引先の変更は容易であり,電力会社ごとにみると取引先電線メーカーの順位及び受注比率は毎年度変動していると認められる。
(ウ) ユーザーの価格交渉力
電力会社は,前記年間契約方式により低い見積価格を提示したメーカーへの配分を多くした上で,基本的に個別物件ごとに競争見積り等を行い,その結果により決定した発注先の電線メーカーに対して,更に単価の引下げを要請している。当該要請を受けて,電線メーカーは,提出した見積り等の価格よりも低い価格で契約していることなどから,電力会社に強い価格交渉力が認められる。
(エ) 輸入・輸出の状況
a 輸入
輸入品を採用した実績のある電力会社も数社みられるが,輸入量は僅かである。その理由は,需要が少なく,海外メーカーが積極的に参入しようとはしていないためである。
b 輸出
国内需要が著しく減少している中で稼動を維持するために輸出を行っているが,輸出対象はおおむね大型事案のみであり,また,大型事案は海外メーカーと競合することから,今後はそれほど受注は増加しない状況にある。
(オ) 電線メーカーの供給余力
国内の需要の著しい減少に伴い稼働率は低下しており,平成15年度の総出荷量(国内出荷に輸出を加えたもの。以下同じ。)を基にすれば,統合後の稼働率は全体で約30%である。これは,当該業界において製造統合が行われる以前の平成12年度の水準を下回るものであり,市場には電線メーカー全体で総出荷量の2倍以上に当たる供給余力の存在が認められる。
(2) OPGWについて
ア 市場の状況
OPGWの平成15年度の国内出荷額は約10億円であるが,国内需要は,著しい減少傾向にあり(平成15年度の市場規模は,平成12年度の約4分の1),今後もこの傾向は続く見込みである。
本件統合により,当事会社の合算出荷数量シェア・順位は約40%・第2位となる(統合後のHHI 約4,000・HHIの増加分 約650)。
| 順位 | 会社名 | シェア |
|---|---|---|
| 1 | C社 | 約50% |
| 2 | 日立電線 | 約25% |
| 3 | 住友電工 | 約15% |
| 4 | D社 | 約10% |
| (2) | 当事会社合算 | 約40% |
| 合計 | 100% |
(出所:調査結果を基に当委員会において作成)
(注) 四捨五入しているため,合計は一致しない。
イ 考慮事項
(ア) ユーザーの購買方法
電力会社は,著しい需要の減少から,年間に一括して発注先を決定する年間契約方式を基本として,一部にスポット契約により発注先を決定している。その際,電力会社は,自社でもOPGWの購入単価を積算しており,基本的に当該単価を基準に入札価格又は見積価格を評価している。
なお,海外品とは仕様が異なるため,型式審査に合格している海外メーカーは存在せず,発注先は当事会社を含む大手電線メーカーに限られている。
(イ) ユーザーの取引先変更の容易性
型式審査に合格している電線メーカーの製品には品質差はないため,電力会社は取引先の変更は容易であり,電力会社ごとにみると取引先電線メーカーの順位及び受注比率は毎年度変動していると認められる。
(ウ) ユーザーの価格交渉力
電力会社は,前記年間契約方式により低い見積価格を提示したメーカーへの配分を多くした上で,基本的に個別物件ごとに競争見積り等を行い,その結果により決定した発注先の電線メーカーに対して,単価の引下げを要請している。当該要請を受けて,電線メーカーは,提出した見積り等の価格よりも低い価格で契約していることなどから,電力会社に強い価格交渉力が認められる。
(エ) 輸入・輸出の状況
a 輸入
国内メーカーと海外メーカー間に技術差はないが,個別の電力会社ごとに仕様が異なること及び需要が少なく,参入するメリットがないため,型式審査に合格している海外メーカーがないことから輸入実績はない。
b 輸出
国内需要が著しく減少しているために稼動を維持するために輸出を行っているが,仕様も異なる上に,海外の需要も少ないので輸出数量は多くはない。
(オ) 電線メーカーの供給余力
国内の需要の著しい減少に伴い稼働率は低下しており,平成15年度の総出荷量を基にすれば,統合後の稼働率は全体で約10%である。これは,当該業界において製造統合が行われる以前の平成12年度の水準を下回るものであり,市場には電線メーカー全体で総出荷量の7倍以上に当たる供給余力の存在が認められる。
(3) 66KV以上の高圧・超高圧電力ケーブルについて
ア 市場の状況
66KV以上の高圧・超高圧電力ケーブルの平成15年度の国内出荷額は約110億円であるが,国内需要は,減少傾向にあり(平成15年度の市場規模は平成12年度の約7割),今後もこの傾向は続く見込みである。
本件統合により,当事会社の合算出荷数量シェア・順位は約40%・第1位となる(統合後のHHI 約3,600・HHIの増加分 約850)。
| 順位 | 会社名 | シェア |
|---|---|---|
| 1 | E社 | 約35% |
| 2 | 住友電工 | 約25% |
| 3 | F社 | 約20% |
| 4 | 日立電線 | 約15% |
| その他 | 0~5% | |
| (1) | 当事会社合算 | 約40% |
| 合計 | 100% |
(出所:調査結果を基に当委員会において作成)
(注) 四捨五入しているため,合計は一致しない。
イ 考慮事項
(ア) ユーザーの購買方法
電力会社は,著しい需要の減少から,年間に一括して発注先を決定する年間契約方式を基本として,一部大口件名については個別の件名ごとに発注先を決定している。その際,電力会社は,66KV以上の高圧・超高圧電力ケーブルの原材料となる銅の国際市況等をベースにして自社でも購入単価を積算しており,基本的に当該単価を基準に入札価格又は見積価格を評価している。
なお,技術力を要するため,競争入札の参加条件である型式審査に合格しているメーカーは,当事会社を含む大手電線メーカーに限られている。
(イ) ユーザーの取引先変更の容易性
型式審査に合格している電線メーカーの製品には品質差はないため,電力会社は取引先の変更は容易であり,電力会社ごとにみると取引先電線メーカーの順位及び受注比率は毎年度変動していると認められる。
(ウ) ユーザーの価格交渉力
電力会社は,前記年間契約方式により低い見積価格を提示したメーカーへの配分を多くした上で,基本的に個別物件ごとに競争見積り等を行い,その結果により決定した発注先の電線メーカーに対して,更に単価の引下げを要請している。当該要請を受けて,電線メーカーは,提出した見積り等の価格よりも低い価格で契約していることなどから,電力会社に強い価格交渉力が認められる。
(エ) 輸入・輸出の状況
a 輸入
国内メーカーと海外メーカーの技術差があるため輸入実績はない。
b 輸出
国内需要が減少している中で稼働率を維持するために,総出荷量の過半を輸出している。
(オ) 電線メーカーの供給余力
国内需要が減少している中で,稼働率は輸出の増減により左右されているが,平成15年度の総出荷量を基にすれば,統合後の稼働率は全体で約40%である。これは,当該業界において製造統合が行われる以前の平成12年度とほぼ同水準となっており,市場には電線メーカー全体で総出荷量のほぼ1.5倍に当たる供給余力の存在が認められる。
2 配電用電線について
(1) 市場の状況
配電用電線の平成15年度の国内出荷額は約1300億円(うち,電力会社向けは約400億円)であるが,国内需要は,減少傾向にあり(平成15年度の市場規模は平成12年度の約8割),今後もこの傾向は続く見込みである。
本件統合により,当事会社の合算出荷数量シェア・順位は約25%・第2位となる(統合後のHHI 約1,850・HHIの増加分 約350)。ただし,資料の制約により輸入数量が把握できなかったため,実際の集中度はこれより小さいと考えられる。
| 順位 | 会社名 | シェア |
|---|---|---|
| 1 | G社 | 約30% |
| 2 | 住友電工 | 約15% |
| 3 | H社 | 約10% |
| 4 | I社 | 約10% |
| 5 | 日立電線 | 約10% |
| 6 | J社 | 約 5% |
| その他 | 約15% | |
| (2) | 当事会社合算 | 約25% |
| 合計 | 100% |
(出所:調査結果を基に当委員会において作成)
(注)1 当事会社のシェアには,関連会社の出荷数量を含んでいる。
(注)2 四捨五入しているため,合計は一致しない。
(2) 考慮事項
ア 市場シェア10%以上の有力な事業者が存在するほか,地域ごとに多数の電線メーカーが存在する。
イ 電線メーカー間に品質差がない。
ウ 輸入については,正確な数量は不明であるが,輸入品と国内品との間に品質差はなく,実際にも韓国,台湾等のメーカーから輸入が行われている。
エ 本件国内販売部門の統合対象である電力会社には,前記のとおり強い価格交渉力が認められる。
第5 独占禁止法上の評価
1 送電用電線について
ACSR,OPGW及び66KV以上の高圧・超高圧電力ケーブルのいずれの市場においても次のことが認められる。
(1) 取引先変更の容易性
型式審査に合格しているメーカー間には製品の品質差はなく,主たるユーザーである電力会社の取引先変更は容易であり,実際に取引先を変更している事実も認められる。
(2) 電線メーカー各社の稼働率及び供給余力の存在
いずれの製品においても需要減が認められ,また,今後においても需要の回復は見込めない状況にある。このような状況のもと,電線メーカー全体で輸出を含めた総出荷量の1.5から7倍程度に当たる十分な供給余力が認められる。
(3) ユーザーの価格交渉力
ユーザーである電力会社は,規制緩和に伴う電力自由化への対応及び最近の電力需要の減少から経営の効率化をより一層図るため,設備投資額を毎年大きく減少させており,それに伴い電力用電線の発注数量も同様に大きく減少している。
電力会社は,それまでは個別物件ごとに発注してきた発注方法を,年間発注を基本とする競争見積り等による単価契約に変更し,電線メーカー各社を競争させている。また,最も安価な価格を提示した電線メーカーの見積価格等で契約するのではなく,アルミ又は銅の国際市況をベースにして,自社で単価を積算して,当該積算単価により近い金額にまで個々に契約金額の引下げ交渉を行い,値下げをさせている事実が認められる。さらに,価格に応じてメーカーごとの購入割合を変動させるなどして,各電力会社とも電線メーカーとの取引シェアがおおむね毎年変動している事実も認められる。したがって,電力会社は強い価格交渉力を有していると認められる。
(4) 総合評価
以上の点を総合的に評価した結果は次のとおりである。
ア 単独行動による競争の実質的制限についての検討
各社の製品間には品質差がない上,各社とも総需要量からみて十分な生産能力を持ち,かつ,稼働率が低く,十分な供給余力が認められることから,当事会社が単独で,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる行動を採ることは困難であると考えられる。
イ 協調的行動による競争の実質的制限についての検討
輸入圧力の存在は認められないものの,電力需要が大きく減少し,今後も大幅な回復の見込みがない中で,国内メーカー間には製品の品質差がないことから,ユーザーである電力会社は取引先の変更が容易であるとともに,いずれの電力会社も低廉な価格での調達を重視した発注方法を取るようになっており,実際,価格に応じて購入先割合を大きく変動させたり,また,電線メーカーから提示された見積価格等からさらに個々に値下げ交渉を行い,値下げをさせたりしている状況が見受けられることから,電力会社は強い価格交渉力を維持でき,当事会社が他社と協調して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる行動を採ることは困難であると考えられる。
2 配電用電線について
全国的に事業を行っている有力な競争業者のほか地域ごとに多数の電線メーカーが存在しており,電線メーカー間には品質差もなく,また,海外メーカーからの輸入も行われており,取引先変更は容易である。さらに販売部門統合の対象である電力会社は強い価格交渉力を有していると認められる。以上の点を総合的に勘案すれば,本件統合により,配電用電線の取引分野において,当事会社が単独で又は他社と協調して競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。
第6 結論
以上の状況から,本件統合により,ACSR,OPGW,66KV以上の高圧・超高圧電力ケーブル及び配電用電線の各取引分野について,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。





