フィンテックを活用した金融サービスに関するアドボカシー活動
①家計簿サービス等及び②QRコード等を用いたキャッシュレス決済について、競争政策上の課題を把握するため実態調査を実施(令和2年度)
↓
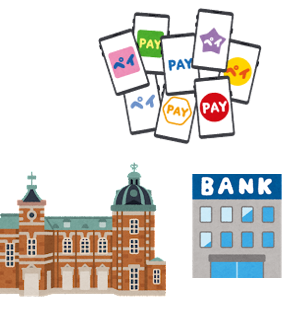
【①家計簿サービス等に関する実態調査報告書】における提言事項
・電子決済等代行業者(家計簿サービス等を提供する事業者)の銀行へのアクセス確保
【②QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書】における提言事項
・リテール決済インフラ(コード決済事業者が銀行口座からのチャージ等を行う際に事実上利用が不可欠なインフラ)の利用料金の設定・更新系APIの活用
・銀行間手数料(銀行が他行宛てに送金する場合に発生する送金手数料)に係る取引慣行の見直し
・全銀ネットのガバナンス体制の強化・取引の透明性の確保
・資金決済システムへの資金移動業者のアクセス開放に向けた検討
↓
【公表後の社会的変化】
・銀行がNTTデータに支払うリテール決済インフラ(CAFIS)の利用料金について、令和2年10月1日に改定され、処理1件あたり最大3.15円から1円に引き下げられた。
・銀行間手数料について、3万円未満は1回117円、3万円以上は同162円から、令和3年10月以降は一律62円に引き下げられた。
・メガバンクをはじめ、ネット系や地銀・第二地銀においても、多数の銀行が他行宛の振込手数料の引下げを実施。
↓
↓
フォローアップ調査では上記提言事項について、
○ 銀行は、業務の安定性や持続性が確保される範囲で、自行の参照系API(残高照会など口座情報を参照するためのAPI)接続料に係る標準料金体系を策定し、電子決済等代行業者から求めがあった場合には、適用する参照系API接続料の合理性について説明することが望ましい
○ 関係団体の取組等による更新系API(振込など口座情報を更新するためのAPI)の仕様統一に向けた検討の場の設置、銀行自身が整備している更新系APIのラインナップの公開、各行における更新系API接続の担当部門の明確化等が行われることが望ましい
○ 銀行は、銀行間手数料が適用されていた頃からの慣習に基づき合理的理由なく振込手数料の区分を維持している場合には、振込手数料を統一することで生じるシステム改修コスト、顧客への影響等を十分に勘案しつつ、現状の見直しの検討を行うべき
などの競争政策上の課題を明らかにし、フォローアップ調査報告書を公表(令和4年度)
↓
引き続き、銀行と電子決済等代行業者及び銀行とノンバンクのコード決済事業者との間の取引等を注視し、更なるフォローアップを行い、競争政策上の観点から提言を行う。
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
電話 03-3581-5483(直通)





